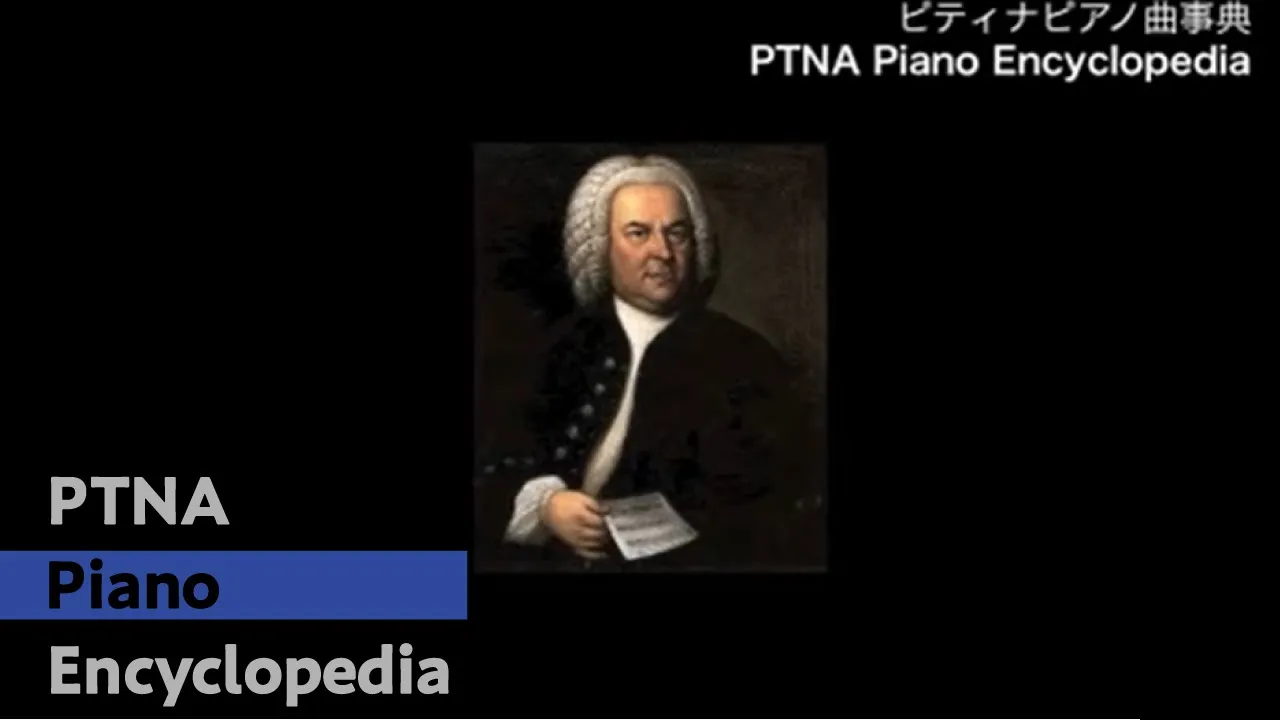【初級~中級向け】ピアノで弾きたい!バッハのおすすめ曲まとめ
「音楽の父」とも呼ばれるヨハン・ゼバスティアン・バッハが活躍したのは、ピアノが普及する前のバロック時代。
つまり、バッハ自身はピアノのための曲を作曲しておらず、現在ピアノで演奏されているバッハ作品のほとんどが、チェンバロ用の楽曲なのです!
複数のメロディラインが重なり合って構成されたバロック時代のポリフォニー音楽は、一見難しいと思われ敬遠されがちですが、実はバッハの作品になかにも比較的難易度が低く取り組みやすい作品が数多く存在します。
そこで本記事では、ピアノ初心者から中級者の方にオススメのバッハ作品をピックアップ!
バッハの音楽が好きな方や、バロック音楽に挑戦してみたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
【初級~中級向け】ピアノで弾きたい!バッハのおすすめ曲まとめ(1〜10)
平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第1番 ハ長調 BWV 846 プレリュードJ.S.Bach

音楽の父と称される偉大な作曲家、ヨハン・セバスチャン・バッハ。
『メヌエット』や『G線上のアリア』に次ぐ有名な作品で、難易度としては中級クラスです。
本作はやや変わった作品で、コンクールでは抑揚をつけない淡々とした演奏の方が評価される傾向にあります。
最初の右手の16分音符やペダルの操作で強弱がつきやすいので、そういった部分を軽やかに演奏することを意識することで、より良い演奏になるでしょう。
ぜひチェックしてみてください。
インヴェンション 第2番 ハ短調 BWV 773J.S.Bach

『インヴェンション』の第2番として知られるこのハ短調の作品は、バロック時代の対位法技術が凝縮された魅力的な1曲です。
1723年にまとめられた教育的作品集の一部で、右手と左手が2小節ずれてカノン形式で対話する構造となっています。
短い作品ながら声部の入れ替わりや転調も含まれ、演奏者には各声部の独立性とバランスが求められます。
ハ短調という調性が生み出す内省的で厳格な雰囲気も印象的で、単なる練習曲を超えた芸術性を持っています。
対位法の美しさを学びたい方や、バロック音楽の奥深さに触れたい方におすすめです。
技術的な挑戦と音楽的表現力を同時に養える、学習者にとって貴重なレパートリーとなるでしょう。
フランス組曲 第4番 BWV 814 ガヴォットJ.S.Bach

フランス舞曲の軽やかなリズムを堪能できるバロック時代の名曲がこちらです。
1722年から1725年の間に作曲された組曲の第4楽章として親しまれ、4分の2拍子の明快で躍動感があふれる舞曲として構成されています。
二音ずつの音型が連続する簡潔なモチーフの繰り返しが特徴で、バッハ特有の対位法的な美しさと宮廷舞曲としての優雅さが見事に融合しています。
チェンバロ用に書かれた原曲ですが現代ではピアノでの演奏が一般的で、明快なリズム感と繊細なタッチが求められます。
バロック音楽に挑戦したい方や、舞曲の魅力を体感したい方におすすめです。
平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第6番 BWV851 前奏曲とフーガJ.S.Bach

『平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第6番 BWV851 前奏曲とフーガ』は、多くのピアノ学習者がバロック音楽の勉強のために取り組む『平均律クラヴィーア曲集』のなかの1曲です。
この曲集は、フーガの難易度をベースに演奏の可否を判断するほど、フーガが重視されている作品。
逆をいえば、前奏曲はフーガほど難易度が高くないともいえます。
各声部に出てくるトリルが硬い音にならないよう、基礎練習やストレッチをしてから練習に臨むことをオススメします!
主よ、人の望みの喜びよJ.S.Bach

癒やしの音楽、そして「ピアノで弾いてみたい」と憧れる人が多い作品として知られている『主よ、人の望みの喜びよ』。
ヨハン・セバスティアン・バッハが作曲した教会カンタータのなかのメロディーで、合唱付きで演奏されることもあります。
この曲はさまざまなアレンジで出版されているため、自分のレベルに合わせて楽譜を選択できるのも、初級~中級向けの作品としてオススメな理由の一つ。
天井の高い教会に響き渡る音色をイメージし、1音1音を味わいながら弾いてみてくださいね。
ポロネーズ ト短調(BWV Anh.119)J.S.Bach

アンナ・マグダレーナ・バッハのための音楽帳に収められたこの楽曲は、ポーランドの民族舞曲ポロネーズの形式を採用した短くも魅力的な作品です。
ト短調の調性が生み出す哀愁が漂う雰囲気と、3拍子の荘重なリズムが印象的で、シンプルながらも深い感情表現が込められています。
1725年に妻のために作られた音楽帳の一曲として、家庭的な温かさと教育的配慮が感じられる内容となっています。
典型的なA-A-B-Bの二部形式で構成され、演奏時間は約1分程度と取り組みやすく、技術的な練習だけでなく表現力を養いたい方にもぴったりです。
バロック音楽特有のポリフォニーに挑戦してみたい方や、品格がある舞曲を学びたい方におすすめの一曲でしょう。
フランス組曲 第6番 BWV817 ガボットJ.S.Bach

バロック時代に作曲された組曲の中でも、この楽曲は明快な2拍子のリズムと親しみやすい旋律が魅力です。
1722年から1725年頃に教育目的で書かれた作品で、フランス風の優雅さとドイツ的な構築性が見事に融合しています。
宮廷舞踏の雰囲気を現代に伝える貴重な楽曲として、演奏者には表現力と技術の両方が求められますが、難しいフレーズや技巧的な部分が少ないため取り組みやすいのが特徴です。
ピアノを始めて間もない方やバロック音楽に挑戦してみたい方におすすめで、音色や表現を重視しながら練習することで、当時の宮廷の雰囲気を感じながら演奏できるでしょう。