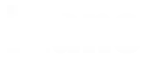ブラームスのピアノ曲|難易度低め&挑戦しやすい作品を厳選!
ヨハン・ゼバスティアン・バッハ、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンとともに「ドイツ音楽の三大B」と称される、ロマン派を代表する作曲家、ヨハネス・ブラームス。
古典的な形式を好んだブラームスらしい重厚な作品たちが、長きにわたり多くの方から愛され続けています。
本記事ではそんなブラームスのピアノ曲のなかから、比較的難易度が低くピアノ学習者がチャレンジしやすい作品をご紹介します。
ブラームスの作品が好きな方や、これから挑戦してみたいと思っている方は、ぜひ参考にしてくださいね!
ブラームスのピアノ曲|難易度低め&挑戦しやすい作品を厳選!(1〜10)
6つの小品 Op.118 第2曲 間奏曲 イ長調Johannes Brahms

ブラームスが晩年に作曲したピアノ小品集からの1曲。
優しく穏やかな旋律で、秋冬の情景を思わせる切なくも美しいメロディが印象的です。
1893年に作曲され、親友クララ・シューマンに捧げられました。
三部形式で構成され、中間部では短調への転調が印象的なコントラストを生み出しています。
内声のメロディラインを明瞭に表現することが求められ、指の独立と繊細な表現力を磨きたい方にオススメ。
ブラームスの成熟した音楽性に触れたい方に、ぜひチャレンジしていただきたい1曲ですね。
2つのラプソディ Op.79 第2番Johannes Brahms

ブラームスが1879年に作曲した本作は、低音域で打ち鳴らされるオクターブの主題が特徴的。
3連符の暗くうごめくような動きを持つ旋律が対照的に登場し、この楽想が中間部でも発展的に扱われています。
ソナタ形式の要素が色濃く反映されており、本作を通じてブラームスの深い音楽的洞察が感じられますね。
古典的な形式美を尊重しつつも、ロマン派らしい情熱的な表現が魅力的です。
技術的にも表現力の面も挑戦したい方にオススメの1曲ですよ。
4つの小品 Op.119 第1曲 間奏曲 ロ短調Johannes Brahms

きらびやかでありながら淡さもただよう旋律が印象的なブラームスの名作『4つの小品』。
今回はその中でも第1曲の間奏曲をご紹介します。
この作品は中級者に差し掛かった初級者にとってオススメの作品で、ゆったり次の伴奏にそなえて左手の準備ができることが特徴的。
その代わり跳躍が少しあるので、目視だけに頼らない演奏を心がける必要があります。
大きな経験値となる作品ですので、ぜひチェックしてみてください。
7つの幻想曲 Op.116 第6曲 間奏曲 ホ長調Johannes Brahms

本作は晩年に入ってからの初めての小品として知られており、現在ではブラームスの集大成として多くのクラシック愛好家たちに愛されています。
ピアノ曲としての難易度は初心者でも取り組めるレベルで、子供のピアノ発表会でもたまに耳にしますね。
対位法に近い構成を取っているので、ピアノの基礎的かつ本質的なテクニックを学べるのも、オススメできる要素の1つです。
ぜひ挑戦してみてください。
ワルツ 第15番 Op.39-15「愛のワルツ」Johannes Brahms

15番のなかでも最も有名な作品『ワルツ 第15番 Op.39-15「愛のワルツ」』。
ピアノ発表会などでも頻繁に耳にする楽曲ですね。
そんなこの作品のポイントは、右手も左手も和音が多い点にあります。
とくに右手は、和音をそのまま弾いているだけではメロディが埋もれてしまいがちに。
メロディの音だけ際立たせることは訓練が必要ですが、ピアノを弾くうえでとても重要なスキルなので、ぜひこの機会にその技術を磨いてみてください!
8つの小品 Op.76 第3曲 間奏曲 変イ長調Johannes Brahms

ブラームスの後期の作品のなかで避けては通れない名作『8つの小品』。
ピアノ発表会でも頻繁に耳にする名作ですね。
そんな『8つの小品』から今回は第3曲の間奏曲をご紹介します。
第3曲は第7曲と並んで、『8つの小品』のなかでも最も演奏しやすい作品として知られています。
メロディだけでなく、左手のベースラインで音楽の流れをつくるイメージを持つと、立体的な演奏になりますよ。
3つの間奏曲 Op.117 第1曲 変ホ長調Johannes Brahms

若きブラームスが作り上げた名作『3つの間奏曲』。
ピアノをオーケストラの一員として使用したことで知られる作品で、現在でも多くのピアニストたちに演奏されています。
その中でも特にオススメしたいのが、こちらの『3つの間奏曲 Op.117 第1番』。
『3つの間奏曲』自体はテクニックを必要とする難易度の高い作品なのですが、第1番に関しては初心者にも演奏しやすい構成にまとめられています。
ぜひ挑戦してみてください。