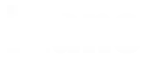【難易度低め】易しく弾けるメンデルスゾーンのピアノ曲。おすすめのピアノ曲
ドイツのロマン派の作曲家であり、指揮者、ピアニスト、オルガニストとしても活躍したフェリックス・メンデルスゾーン。
ヴァイオリン協奏曲やピアノ独奏曲など数々の名作を生みだしながら、ヨハン・セバスチャン・バッハの音楽の復興やライプツィヒ音楽院の設立などの活動も精力的に行い、19世紀の音楽界に多大な影響を与えた人物でもあります。
本記事では、そんな偉大な作曲家メンデルスゾーンの作品の中から、比較的難易度の低いピアノ作品を厳選して紹介します。
コツコツと練習すれば必ず弾けるようになるのでぜひ最後までご覧ください!
【難易度低め】易しく弾けるメンデルスゾーンのピアノ曲。おすすめのピアノ曲(1〜10)
幻想曲 嬰ヘ短調 Op.28「スコットランドソナタ」Felix Mendelssohn

ファンタジックな音楽性で人気を集める偉大な作曲家、フェリックス・メンデルスゾーン。
ピアノ中級者にとってはおなじみの作曲家で、レベルに合った作品を多く生み出しています。
その一つが、こちらの『幻想曲 嬰ヘ短調 Op.28「スコットランドソナタ」』。
メンデルスゾーンの特徴である華やかな音楽性が魅力で、第3楽章では非常にロマンティックな旋律を味わえます。
ポイントは第3楽章冒頭の高速で弾く6連符。
両手で鳴らさなければならないこの部分の練習は必須ですが、リピートが多いという側面もあるため、上達してきたクラシックが好きなピアノ中級者のピッタリな楽曲といえるでしょう。
ロンド・カプリチオーソ ホ長調 作品14, MWV U 67 第1番 アンダンテFelix Mendelssohn

優雅で抒情的なアンダンテから始まり、軽快で繊細なプレスト部分へと展開するメンデルスゾーンによる作品は、15歳という若さで原形が作られた傑作です。
アンダンテ部分では透明感のある美しい旋律が歌い上げられ、まるで無言歌のような親しみやすさを感じさせます。
プレスト部分では軽やかなパッセージが躍動感に溢れ、まるで精霊たちが踊るかのような雰囲気を醸し出しています。
本作は難易度の面でも取り組みがしやすく、シンプルな構造と美しい旋律は、クラシック音楽にこれから親しもうとする人にぴったりです。
ゆっくりとしたテンポから練習を始めれば、着実な上達を実感できる素晴らしい作品となっています。
子供のための6つの小品(クリスマス小品集)作品72 第1曲 ト長調 アレグロ・ノン・トロッポ MWV U 171Felix Mendelssohn

メンデルスゾーンの子ども向け、初心者でも弾きやすいピアノ曲集といえば『無言歌集』もしくは『6つの子供の小品』です。
こちらの『6つの子供の小品』はタイトル通り子どもたちの練習曲としても定番のピアノ曲集であり、ソナチネ程度の難易度で挑戦しやすいですし、大人になってからピアノを始めて「ロマン派のピアノを弾いてみたい」と考えている方にもおすすめできますね。
本稿で紹介しているのは『6つの子供の小品』の第1曲で、優雅なワルツのリズムとスタッカートを多用したフレーズが特徴的な楽曲です。
1分程度の短い作品で臨時記号も少なく、基本的なテクニックを押さえておけば初級レベルの方でも十分対応できるはず。
スタッカートはあくまで軽やかに歯切れがよく、あまり力を入れ過ぎないように注意しましょう!
無言歌集 第2巻 Op.30 第3曲 慰めFelix Mendelssohn

比較的難易度が低く、子どもの練習用の教材としても使われる『無言歌集』ですが、全48曲の中で多少難易度も変わってきます。
こちらの『第2巻 作品30 慰め』はおそらく最も難易度が低い部類の楽曲ですから、初めて『無言歌集』に取り組むにはもってこいの作品と言えそうですね。
複雑な構造の楽曲ではないのですが、スラーや強弱記号はしっかり意識して弾いてみてください。
やや地味なタイプの作品ですし淡々と弾いてしまいがちなのですが、落ち着いてゆっくりとしたテンポながらあまり遅くなりすぎず、所々しっかり表情をつけてあげることで楽曲の上品な美しさが表現できるようになりますよ。
無言歌集 第1巻 Op.19 第6曲 ヴェネツィアの舟歌 第1Felix Mendelssohn

船頭が船上で口ずさんでいたという、水の都ヴェネツィアのゴンドラの舟歌を模した「バルカロール」をクラシックの分野にいち早く取り入れたとされるのが、メンデルスゾーンだったということはご存じでしょうか。
『無言歌集』には3曲の『ヴェネツィアの舟歌』が収められており、特に有名とされるのは第3番なのですが、今回は比較的難易度の弾くいというテーマに沿って『無言歌集』の第1巻に収められた『ヴェネツィアの舟歌 第1』を紹介します。
舟歌の特徴でもある8分の6拍子のリズムで、波間にたゆたっているゴンドラの動きが左手の伴奏で見事に表現されていますね。
複雑な技法もなく、音符をなぞるだけなら簡単ではありますが、8分の6拍子というリズムに慣れることが重要です。
6拍ではなく2拍で取ることを意識して、左手の伴奏も一定だからといって機械的になりすぎず、先ほど述べたようにゴンドラの動きをイメージしながら弾いてみてください。
無言歌集 第2巻 Op.30 第1曲 瞑想Felix Mendelssohn

変ホ長調のゆっくりと穏やかな旋律が印象的な本作は、1835年5月にボンで出版された『無言歌集』の中の一曲です。
静かな瞑想のような雰囲気を持つ本作は、豊かな抒情性とともに、技巧的には比較的平易な作りとなっています。
三部形式で統一感のある構成と、シンプルながらも深い感情表現を持ち合わせており、ピアノ学習者の表現力を養う教材としても重宝されています。
レパートリーの幅を広げたい方や、落ち着いた雰囲気の曲を探している方にぴったりの一曲です。
リヴィア・レーヴによる1986年の録音は、フランスの「ディスク大賞」を受賞しており、繊細な表現で高い評価を得ています。
アルバムの綴り Op.117Felix Mendelssohn

どこか物悲しくも情熱的な雰囲気が特徴的なこちらの『アルバムの綴り』は、1837年に作曲されたピアノ独奏曲です。
中間部は転調してメロディが柔らかなものへと変化するさまも美しく、全体的に作曲者の曲に込めたエモーションを感じ取れるようなロマンチックな作品なのですね。
実際に弾くとなるとピアノを始めて慣れ始めた初級者には難しく、中級者程度の方でないと太刀打ちできないかもしれません。
主要なテーマの部分ではひたすら左手が6連符の伴奏を弾き続けるため、慣れないうちは片手ずつ練習していくことをおすすめします。
先に触れた中間部では逆に左手はコードの和音メイン、右手が3連符を中心に弾いてくという変化も注意しつつ、強弱記号もしっかりと把握した上で自分なりに楽曲を表現できるように頑張りましょう!