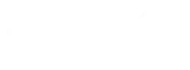運動会で昔から定番で人気のパン食い競走。
コースの途中にパンがつるされていて、手を使わず口でくわえてゴールまで走るというユニークな競技ですよね。
しかし「どうせやるなら独自のアレンジを加えてさらに盛り上がるものにしたい!」そんなニーズに応えるため、この記事ではパン食い競走のアレンジを紹介していきます。
ルール上のアレンジ、パンのつるし方のアレンジ、さらにパン以外のものをつるすアイデアの3つの視点でアイデアを集めましたので、ぜひ参考にしてください。
- 【ユニーク】子供も大人も楽しめる運動会のおもしろい種目
- 幼稚園の運動会に!障害物競走のアイデア一覧
- 小学1年生から6年生まで楽しめる遊びアイデア【室内&野外】
- 【白熱】しっぽ取りのアレンジルールまとめ
- パン食い競争をアレンジ!楽しく盛り上がるおもしろアイデアを一挙紹介
- 【運動会を親しみやすく!】ユニークな競技名。ジャンルごとの面白い種目名
- 【中学生向け】体育祭にオススメの面白い競技を一挙紹介!
- おもしろ親子競技!保育園の運動会が盛り上がるアイデア集
- 【ダンシング玉入れ】運動会にオススメの玉入れの楽しい曲
- 【運動会】かけっこに合う曲。子供たちが走りたくなる曲【定番&J-POP】
- 【子供向け】盛り上がるクラス対抗ゲーム。チーム対抗レクリエーション
- 運動会で盛り上がる応援歌!子どもたちにもオススメのモチベ上げ曲集
- 【行進・かけっこ・ダンス】運動会を盛り上げる元気ソング&最新曲
ルールのアレンジ(1〜10)
両手を縛る
パンを取るときつい手を使いたくなってしまうかもしれませんが、こちらのパン食い競争はそれをはじめから避けるため、手をしばっておこないます。
走るうえでもハンデになりそうなこの手しばりパン食い競争ですが、くれぐれもケガに注意して、手をしばるものはハンカチやタオルなどやわらかい布にし、何かあった時はすぐにほどけるようにしましょう。
ぐるぐるバット
バラエティ番組などの企画としても定番のぐるぐるバットをパン食い競走に取り入れてみてはいかがでしょうか。
パンを取る前にバットを軸にしてうつむき、決められた数だけ回転してからパンを取りに行きましょう。
目が回ってしまい、思うようにパンが取れない様子は、参加者だけでなく見ている人も楽しめることでしょう。
バランスを崩して転倒してしまうこともあるので、マット敷いておくなど安全面には気をつけていただきたいですね。
手でパンに触れたら失格
パン食い競争は口でパンをくわえて取るのが本式、とされていますよね。
その場合、とったパンは口にくわえたままゴールするというルールを固定してしまいましょう。
最後まで手を触れないことがパン食い競争の緊張感を最大に高めてくれます。
普段口だけを使って作業をする、ということは普通の方ならそうないことでしょうから、器用さも問われます。
このようにあと一つのしばりを作るというのはおもしろいのでぜひ一度試してみてください。
数字が書かれたカードをつるしてゴール後に引き換え
本物のパンをつるすのは大変だし衛生的にも抵抗がある方にオススメな方法がこちら。
数字が書かれたカードをマジックハンドで取り、その番号のパンと交換する、というもの。
年齢によってはマジックハンドの操作も難しかったりするのですが、うまく取れてパンと交換するときはとても嬉しいしテンションもあがりそうです。
最初からこの番号は〇〇パンです、と知らせるのもモチベーションが上がっていいかもしれません。
一度挑戦してみてください。
おんぶ
個人競技のイメージがあるパン食い競走に団体戦の要素を加えてみると、違った楽しみが見えるかもしれません。
そのアイディアがおんぶをした状態でパン食い競走をおこなうというもの。
背負う側は重量によって走りにくくなると同時に、上の人がパンを取りやすくなるような適切な位置を探し出さなければいけません。
背負われる人がしっかりと声をかけるなど、お互いの歩み寄りと素早い意志疎通が勝つための重要なポイントですね。
マジックハンドでつかむ
パンを口ではなくマジックハンドでつかんでみましょう。
マジックハンドはなかなかうまく力を入れにくかったり、はさんでも力の入れ方がむずかしくて落としてしまったりするので、口で取るより難易度が上がるかもしれません。
この思うようにならない感を楽しんでください。
また、マジックハンドは割りばしで手作りもできますので、手作りの体育祭を目指す場合は作ってみてもいいですよね。
100均で売っているものを使うとそれはそれで経費も掛からず便利です。
巨大なフランスパンをつるす
パン食い競争といえばだいたいがアンパンやクロワッサン、ロールパン程度の大きさのものが多いですが、ここでは大きなフランスパンで試してみましょう。
あまりの大きさにつるしてある時点でまわりから笑いがおきそうです。
落としてしまわないように慎重にくわえたら、くわえたままゴールという難易度の高いルールを作ってもいいですし、脇に挟んでゴール、などというのも楽しそうです。
ぜひフランスパンを手に入れて、明日の朝食にしてみてください。