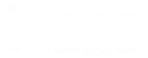【現代曲】ピアノの不思議な響きに惹かれるクラシック作品を厳選!
クラシックの現代曲といえば「複雑すぎる響き」「目を疑う超絶技巧」「理解不能……」このようなイメージをお持ちの方も多いはず。
確かに、クラシック音楽が行き着いた「現代における最終形態」ともいえる現代曲には、解釈の難しい作品も数多く存在しますが、作曲家の意図や作曲の背景を知ることで、曲の魅力が見えてくることもあります。
今回は、そんな難解と思われがちな現代曲の中から、ピアノ独奏のために作曲された作品をご紹介します。
現代曲に挑戦してみたい方や、ぜひチェックしてくださいね!
- 【中級レベル】華やかな旋律が印象的なピアノの名曲を厳選!
- 【スクリャービンのピアノ曲】現代音楽の先駆者が遺した名曲を厳選
- 【上級者向け】聴き映え重視!ピアノ発表会で弾きたいクラシック音楽
- 【和風のピアノ曲】日本らしさが心地よいおすすめ作品をピックアップ
- 【印象派】色彩豊かなピアノの名曲を厳選~ドビュッシー・ラヴェル~
- 【中級者向け】挑戦!ピアノ発表会で聴き映えするおすすめの名曲
- 【フランクのピアノ曲】近代音楽の父による珠玉の名作を厳選
- 【本日のピアノ】繊細な音色で紡がれる珠玉の名曲・人気曲
- 【上級者向け】ピアノ発表会で挑戦すべきクラシックの名曲を厳選
- 【名作クラシック】涙が出るほど美しい珠玉の名曲を一挙紹介
- 【ピアノ発表会向け】簡単なのにかっこいいクラシック作品
- 【難易度低め】ラフマニノフのピアノ曲|挑戦しやすい作品を厳選!
- ピアノで弾けたらかっこいい!魅力抜群の名曲たちをピックアップ
【現代曲】ピアノの不思議な響きに惹かれるクラシック作品を厳選!(1〜10)
ムジカ・リチェルカータGyörgy Ligeti

現代音楽の先駆者として知られるハンガリーの作曲家、ジェルジュ・リゲティさん。
彼は当時の社会主義体制下で表現の自由が制限されるなかでも独自の音楽スタイルを追求し、1956年のオーストリアへの亡命後は、ケルンの電子音楽スタジオで新しい音楽に触れたことで、さらなる革新へと向かいました。
そんなリゲティの初期の代表作が、ピアノのための11の小品からなる『ムジカ・リチェルカータ』です。
各楽章は実験的な手法で作曲され、特定の音程やリズム、ハーモニーを用いて静寂と苦悩の動きを表現しています。
厳しい検閲下で生まれ、20世紀のクラシック音楽に大きな影響を与えた本作は、現代音楽に興味がある方や、ピアノ曲の新しい可能性を探求したい方にオススメの1曲です。
ピアノソナタHenri Dutilleux

フランスの作曲家、アンリ・デュティユーさんは、20世紀後半を代表する作曲家のひとり。
彼の音楽は、ドビュッシーやラヴェルの影響を受けつつ、ジャズのエッセンスも取り入れた独自のモダニズムスタイルを確立しました。
1948年に発表された『ピアノソナタ』は、デュティユーが自らの音楽的アイデンティティを示した記念碑的な作品といえるでしょう。
本作は、形式的な厳格さと和声の探究を特徴としており、印象主義とソビエト音楽が融合した独特の音楽世界を作り上げています。
彼の妻であるピアニストのジュネヴィエーヴ・ジョワに献呈されたこの作品は、ピアノという楽器の可能性を追求した意欲作であり、現代音楽の傑作として高く評価されています。
アルゼンチン舞曲集 Op.2 第1曲「年老いた牛飼いの踊り」Alberto Ginastera

アルゼンチンを代表する20世紀の作曲家、アルベルト・ヒナステラさん。
彼の初期の代表作である『アルゼンチン舞曲集 Op.2』は、アルゼンチンの民族音楽の要素を独自のスタイルで展開した意欲作です。
中でも第1曲は、右手が白鍵、左手が黒鍵のみを使うという特殊な手法で、2つの調が同時に響き合う不思議な魅力を持っています。
民族色豊かな響きと前衛的な技法が融合した、ユニークで味わい深いこの作品は、ピアノの新しい可能性に挑戦したい人方にオススメです。
【現代曲】ピアノの不思議な響きに惹かれるクラシック作品を厳選!(11〜20)
ロマンス武満徹

現代音楽の巨匠であり、日本の伝統と西洋の音楽を融合させた武満徹は、生前から国際的に高い評価を受けていました。
彼の初期の作品の一つであるこのピアノ曲は、前衛的な音楽活動を展開していた若き日の探究心と独自の作曲スタイルが反映されています。
西洋クラシック音楽と日本の音楽性を組み合わせた音楽は、静ひつでありながら奥深いな響きをたたえており、武満さんならではの世界観を創り上げています。
独学で音楽を学んだ彼の才能と感性が、余すことなく注ぎ込まれた本作は、現代音楽になじみのない方にこそ、耳を傾けていただきたい作品です。
遊び 第1巻より「無窮動」Kurtág György

ハンガリーの作曲家、クルターグ・ジェルジュさんは、20世紀後半から21世紀初頭にかけて最も尊敬される作曲家のひとりです。
彼の音楽は緻密かつ繊細なテクスチャーと厳密な形式感、深い表現力で知られています。
1973年から書き始められたピアノ曲集『遊び』は、子供たちがピアノと自由に遊ぶ姿から着想を得た教育的演奏作品。
即興的な音楽実践や民族音楽、グレゴリオ聖歌の知識を活用し、演奏者自身が喜びのために音楽を創造することを促しています。
ピアノを学び始めた子供から大人まで、自由な発想で音楽を探求したいすべての方にオススメの作品集です。
ピアノのためのソナチネ尾高尚忠

日本を代表する作曲家として知られる尾高尚忠さん。
彼はウィーンでピアノや音楽理論、作曲を学び、卒業後は指揮者としてウィーン交響楽団やベルリン・フィルハーモニー管弦楽団といった名門楽団で活躍。
帰国後、NHK交響楽団の前身である新交響楽団でクラシック作品とともに自作の管弦楽曲を演奏し、指揮者、作曲家としてデビューして以降、オーケストラ作品や室内楽作品、ピアノ独奏曲などの創作活動を精力的に展開しました。
『ピアノのためのソナチネ』は、ドイツロマン主義と日本音楽の要素を融合させた作風に定評のある彼独自の世界観を存分に味わえる作品として、現代音楽、特に日本で生まれた現代作品に興味のある方にオススメの1曲です。
3つのピアノ曲 Op.11Arnold Schönberg

アルノルト・シェーンベルクさんは、20世紀初頭の革新的な作曲家のひとりです。
彼の『3つのピアノ曲 Op.11』は、調性を完全に放棄し、斬新な音楽表現を追求した作品です。
この曲の特徴である楽想の絶え間ない変化や急激なダイナミクスの変化は、20世紀音楽の発展への重要な一歩を示しています。
この曲集は、音楽大学の教材としても用いられるなど、後の無調、十二音技法などの先駆けとなった意義深い作品です。
彼の先駆的な試みは、柔軟な発想力と創造性に富むリスナーにとって魅力的な体験となるでしょう。