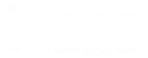【現代曲】ピアノの不思議な響きに惹かれるクラシック作品を厳選!
クラシックの現代曲といえば「複雑すぎる響き」「目を疑う超絶技巧」「理解不能……」このようなイメージをお持ちの方も多いはず。
確かに、クラシック音楽が行き着いた「現代における最終形態」ともいえる現代曲には、解釈の難しい作品も数多く存在しますが、作曲家の意図や作曲の背景を知ることで、曲の魅力が見えてくることもあります。
今回は、そんな難解と思われがちな現代曲の中から、ピアノ独奏のために作曲された作品をご紹介します。
現代曲に挑戦してみたい方や、ぜひチェックしてくださいね!
- 【中級レベル】華やかな旋律が印象的なピアノの名曲を厳選!
- 【スクリャービンのピアノ曲】現代音楽の先駆者が遺した名曲を厳選
- 【上級者向け】聴き映え重視!ピアノ発表会で弾きたいクラシック音楽
- 【和風のピアノ曲】日本らしさが心地よいおすすめ作品をピックアップ
- 【印象派】色彩豊かなピアノの名曲を厳選~ドビュッシー・ラヴェル~
- 【中級者向け】挑戦!ピアノ発表会で聴き映えするおすすめの名曲
- 【フランクのピアノ曲】近代音楽の父による珠玉の名作を厳選
- 【本日のピアノ】繊細な音色で紡がれる珠玉の名曲・人気曲
- 【上級者向け】ピアノ発表会で挑戦すべきクラシックの名曲を厳選
- 【名作クラシック】涙が出るほど美しい珠玉の名曲を一挙紹介
- 【ピアノ発表会向け】簡単なのにかっこいいクラシック作品
- 【難易度低め】ラフマニノフのピアノ曲|挑戦しやすい作品を厳選!
- ピアノで弾けたらかっこいい!魅力抜群の名曲たちをピックアップ
【現代曲】ピアノの不思議な響きに惹かれるクラシック作品を厳選!(21〜30)
クライスレリアーナ Op.16 第7曲Robert Schumann

非常に情熱的で劇的な表現が特徴的なこの曲。
急速なテンポとハ短調の調性が融合し、聴く者の心をつかみます。
約2分30秒の短い演奏時間ながら、ロベルト・シューマンの内面的な葛藤や情熱が凝縮されています。
激しいアクセントを持つアルペッジョの繰り返しが緊張感を高め、中間部のフガートとの対比が印象的です。
1838年に作曲された本作は、シューマンがクララ・ヴィークとの結婚に反対され苦悩していた時期の作品。
ロマン派音楽の特徴である感情表現の豊かさが存分に発揮されており、ピアノ演奏の技術と表現力が試される1曲です。
クラシック音楽の深い感動を味わいたい方におすすめの名曲です。
ラ・カンパネラFranz Liszt

鐘の音を模した繊細な旋律が印象的で、高音域での跳躍や装飾音が美しく響き渡ります。
1851年に改訂されたピアノ曲は、ロマン派音楽の真髄を感じさせる情熱的な表現力と、技巧的な演奏が特徴です。
フランツ・リストは、1831年にパガニーニの演奏に感銘を受け、ヴァイオリン協奏曲の主題をピアノ用に編曲。
映画やテレビ番組のBGMとしても度々使用され、多くの人々の心を魅了してきました。
本作は、静かな環境で集中して勉強したい方にオススメです。
鐘の音のような透明感のある音色は、心を落ち着かせながらも適度な緊張感を保ってくれるでしょう。
【現代曲】ピアノの不思議な響きに惹かれるクラシック作品を厳選!(31〜40)
8つの演奏会用練習曲 Op.40 第1曲「プレリュード」Nikolai Kapustin

ウクライナ出身のロシアの作曲家ニコライ・カープスチンさんによる明るくエネルギッシュな曲調が特徴のこの曲。
リズミカルで、ジャズのスウィング感とクラシックの精密さが見事に融合していて、聴いていて思わず体が動きだしてしまいそうです。
ピアノ1台でまるでジャズコンボが演奏しているような錯覚を覚えるかもしれません。
演奏者にとっては高度なテクニックが必要で、挑戦しがいのある1曲。
しかし、聴く側にとっては軽快で楽しい曲なんです。
クラシックとジャズ、両方のジャンルが好きな方にぜひ聴いてほしい1曲ですね。
前奏曲集第1集「沈める寺」Claude Debussy

神秘的な霧の中から浮かび上がる壮大な大聖堂を描いた印象的なピアノ曲です。
フランス・ブルターニュ地方に伝わる「イースの伝説」をモチーフに、1910年に作曲されました。
深い静寂から始まり、遠くから鐘の音が響き、荘厳な聖歌が聞こえてくるような幻想的な情景が、豊かな音色で表現されています。
本作の魅力は、優しい響きの中にも力強さを併せ持つ和音の重なりと、自然な流れを感じさせる音の移ろいにあります。
音楽を通して絵画のような世界を描くクロード・ドビュッシーならではの作品で、和音の響きを大切にしながら、ゆったりとしたテンポで演奏できる曲です。
物語性豊かな音楽に触れてみたい方や、音の重なりの美しさを味わいたい方におすすめです。
スペイン組曲 第1集 作品47『アストゥリアス』Isaac Albéniz

スペイン各地の風景や文化を音楽で描写した、情熱的で印象的なピアノ組曲『スペイン組曲 第1集 作品47』から、魅力的な楽曲をご紹介します。
神秘的な雰囲気を持つ中間部と、力強いリズム主題が織りなすコントラストが見事な本作は、ギター的な奏法をピアノで表現する独特の技法が用いられています。
1886年に作曲された本作は、映画やテレビ番組、CMなどでも使用されており、多くの人々の心を捉えてきました。
ピアノ技術を持ち合わせた方や、表現力が豊かな演奏を目指す方におすすめです。
スペインの民族音楽の要素を取り入れた味わい深い曲調は、発表会で聴衆を魅了することでしょう。
子供の領分 第4曲「雪は踊っている」Claude Debussy

窓辺で静かに降り積もる雪を見つめる子供たちの純粋な眼差しをイメージした作品です。
16分音符の連続する音型によって、舞い落ちる雪片の様子を緻密に描写しています。
両手で交互に奏でるパッセージは、まるで空から無数に舞い落ちる雪の結晶のよう。
1908年に当時3歳だった愛娘のために作られた本作は、子供の想像力が豊かな世界観を大切に表現しています。
スタッカートとレガートの対比や、繊細なペダルワークによって、降り積もる雪の静寂さと、その中に秘められた生命感を感じ取れます。
クラシック音楽に親しみたい方や、日常から離れて心静かなひとときを過ごしたい方におすすめの一曲です。
春の祭典Igor Stravinsky

春の到来を祝う異教の儀式を描いたこの作品は、20世紀の音楽に革命をもたらしました。
複雑なリズムと不協和音の大胆な使用が特徴で、原始的で力強い音楽が展開されます。
オーケストラでは冒頭のファゴットの独奏は、楽器の高音域を使用し、独特の緊張感を生み出しています。
1913年5月の初演時には観客の間で大きな騒動を引き起こしましたが、オーケストラ版とは別に作曲者であるイーゴリ・ストラヴィンスキー2台ピアノ版も存在し、本人編曲であることから複調の仕組みや和声構造などの各楽曲の構造が非常に明確になって、現在では重要なピアノ曲のレパートリーとしても広く演奏されています。
クラシック音楽の常識を覆す革新性に興味がある方におすすめです。