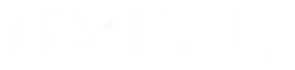アイドルの神曲から作詞の作法を解く
楽曲の選定にはコンペという方法があります。
コンペはコンペティションの略、競争の意味。
たくさんの候補の中からめぼしい1曲を、または数曲を選びます。
コンペに落ちた楽曲の行方は……。
次のコンペに挑む体力のある楽曲は輝ける場所を探して再びコンペに向かいます。
敗れ去りどこにも使えない楽曲は楽曲からただのくずへと帰ります。
昔からコンペに関しては賛否両論あります。
故寺山修二は「本当に起こらなかったことも歴史の一部分だ」と話しています。
たくさんのコンペを通らなかった楽曲はその音色をどこで奏でているのでしょうか。
今回は必然、偶然問わず、世に出ることのできた2曲の神曲から作詞の作法を解いてゆきたいです。
お手本神曲まなみのりさ「vポラリスAb」
作詞はtestuhikoさんです。
サビありき
「回る回る 回る回る 回る回る 回る回る」
良くも悪くもこのサビがなければ、世の中に出なかった楽曲なのではないかと思わせる、そんな大きなサビです。
何でもない歌詞ですが、リズムに乗ったその空間的あしらいは特筆すべきものです。
歌詞は文字だけでなくどこか感情の母体みたいなものを持っていることが大切です。
このサビは一瞬で演者とファンをつなげ、両者をその場でリズム良くクルクルと回らせます。
この一体感がこの楽曲を神曲へと押し上げました。
初めてこの楽曲を聴いた時「この先この楽曲以上のものを作り上げることができるのかな?」と思ったことを覚えています。
それくらい衝撃的でした。
一番練り上げられた部分がサビです。
分かりやすいサビの楽曲はまず耳に残ります。
結果的に人の心に残り、そして売れると思います。
ですから歌詞をサビから書き出すのもひとつの手だと思います。
私は多くの場合に、とびっきりかわいいサビのフレーズから書き始めます。
クリスタルキングの「大都会」や西城秀樹の「ヤングマン」(「ヤングマン」はヴィレッジ・ピープルの「Y.M.C.A.」のカバーですが)、昭和の大ヒット曲にはこのまずサビありきの楽曲が多いです。
例えば美空ひばりの「川の流れのように」を歌ってみて、と人から言われれば、多くの人は「あーあー川の流れのようにー」とサビを歌うものです。
Tubeの「シーズン・イン・ザ・サン」を歌ってみてと言われれば「Stop the season in the sun~」と景気良くサビを歌うものです。
サビにはそれだけの力があります。
では、逆に「サビありき」の楽曲でないものの例を挙げるとすればどんな曲になるでしょうか。
私は山下達郎の「クリスマス・イブ」をパッと思い浮かべました。
「雨は夜更け過ぎに 雪へと変わるだろう」
この出だし(Aメロ)が「クリスマスイブ」そのものだと言っても過言ではないです。
これはこれで作家冥利に尽きるレアな事象だと思います。
AメロBメロの概念
「えいこらえいこらほい 時間の河を もひとつえいこらほい 眠りにつくまで」
Bメロと区切って良いのでしょうか。
突然拍子の変わるやや違和感あるメロディーが挟まれます。
この歌詞が、
「何をやっても駄目と 決めることで逃げた だけど今度は掴む 君がいなくたって」
と王道の「逃げちゃだめだ系」の応援ソングの歌詞の続きなのですから、「えいこらえいこらほい」の歌詞の登場はとても不思議な感じがします。
楽曲内でストレスのない戦いが起こっています。
楽曲制作は、自分1人で作詞作曲をしていなければ曲が先に決まることが多い世界ですので、これら楽曲に厚みを出す部分は作曲家さんの心意気でもあります。
細部にわたる印象をいくつも積み重ねて音は作られていることを再確認できます。
QUEENの代表曲「ボヘミアン・ラプソディ」のように、Aメロ、Bメロの気遣いがどこかへ吹っ飛んでしまった重層的な楽曲は聴いていて楽しいです。
きっと楽曲を制作したフレディ・マーキュリーには凡人が考えるようなAメロやサビの概念などなかったのでしょう。
彼もまた独特な体性感覚の持ち主のひとりだったのでしょう。
アイドルの楽曲「vポラリスAb」にはそこまでの重苦しさはないにしろ、一種の遊びのようなこのBメロパートがあるだけで、その後のCメロ、サビがぐっと盛り上がります。
ももいろクローバーの「ミライボウル」もAメロBメロサビがめくるめく変化を続ける楽曲で、そこには全く違う曲のパートがホッチキスでつなげられたような不思議さがあります。
残念なことに、作曲家がつくるメロディーと違って、歌詞は突然テイストがガラッと変わって曲が続く……ことは少ないです。
ほぼないと思います。
ただ、今までなかっただけで、ボカロやDTMなど、これだけ自由に楽曲作りができる時代なのですから、はじめはヘビメタのノリだったのにサビは演歌だった、みたいな楽曲が生まれてもおかしくはないと思います。
どこまでもアイドルを追う歌詞
「はしゃいでいるふりして 君にだけ話した 夢をまた今から 追いかけてみるよ」
創作フレンチのレストランに行くといろいろと珍しい料理は出るものの、最後には「普通のフレンチが食べたい……」「オーソドックスなフランボワーズソースで食べたい……」となるのは人の常でしょう。
アイドルの楽曲でも、私だけかもしれませんが、普通に明るく前向きな、でもどこか切ない思いを抱いた女の子が主人公である、そんな楽曲の歌詞が一番落ち着きます。
上記の歌詞に登場するのはしゃいでいるふりをしている女の子も意中の男の子にだけ自分の夢を話す、それだけでいい、誠にいいシチュエーションです。
ほかには何もいらないです。
「夢をまた今から~」の部分もこの楽曲の物語性の中で際立ったセリフにも読めます。
「誰も知らない無数の星 今夜も消えるよ 忘れないキラキラ 思い出はひらひら」
簡単に書いているように見えて丹念に作り上げられた言い回しです。
名もなき星が生まれては消える、それは好きだと思う気持ちがどこかで生まれ、そしてどこかで消えてゆく。
切ない思いを星に託し、時にため息をつきながらも常に肯定的に生きようとする少女像です。
無意識に対比されたキラキラとひらひらもメロディから冒険することなく耳に聞こえが良いです。
この楽曲はどこまでもどこまでもアイドルを追う歌詞の連続です。
私はアイドルが歌いそうな歌詞しか書かないです。
器用貧乏と呼ばれてもいい、そのくらいの些細なプライドがあってもいいと思います。
平成の世が終わり新しい未来がもうすぐやってきます。
特化は新時代のキーワードかもしれません。
℃-ute「Danceでバコーン!」
作詞はつんく♂さんです。
歌わせたい曲、歌いたい曲
音楽をあまり聴かない普通の人でも知っている人気のあるプロデューサーと言えば、AKB48グループを指揮している秋元康さんと、ハロープロジェクトの楽曲に多く関わっているつんく♂さんです。
2人の違いは何かと問われれば、私なら「秋元さんはアイドルに歌わせたい楽曲を作る、対してつくん♂さんは自分が歌いたい楽曲を作る」でしょうか。
秋元さんが作るどこまでも元気で可憐な楽曲は、アイドルが歌ってこそ輝くものばかりです。
つんく♂さんが作る楽曲はシャ乱Qが歌ってもそのまま通用するような、どこかセクシャルポイントを含んだ楽曲ばかりで、まさに自分が歌いたい曲を書いていると思わせるのです。
お2人とも多種多様な歌詞を書きますので、当然ひとつの特定したラインを見つけて無理に比べることはできませんが、最大公約数的なところを拾い、その女の子像をあえて例えるなら、
- 秋元さん……純粋な白さ、男の子が直視する女子
- つんく♂さん……どこかセクシーな要素を含む、男の子がチラ見する女子
にもなるでしょうか。
その片鱗がお2人の歌詞に見え隠れします。
もうひとつ書き足すとするなら秋元さんの「Everyday、カチューシャ」はまずファンを盛り上げようとして書かれた感じがします。
「Danceでバコーン!」はまず演者である℃-uteを盛り上げようとして書かれた感じがします。
どうでしょうか。
現実、夜の匂い
大ヒットした楽曲でもシャ乱Qの歌はどこかしら夜の匂いがしました。
夜の匂いがするから大ヒットしたのかもしれません。
夜の匂いとはここでは少なくとも現実のことです。
ホストの笑顔のうさん臭さと言いましょうか、成り切れない水商売女性の心のせめぎ合いとでも言いましょうか、状態を表す言葉が見つからない現実、それがつんく♂楽曲の味なのかなと思います。
「もちろん玉の輿 そりゃ乗りたい 毎日が勝負パンツ」
パンツは意外とアイドルの楽曲に登場するキーワードです。
NMB48 「純情U-19」
「大人にはなれるでしょう いつの日か だからもう少しだけ 鉄のパンツ」
でんぱ組.inc「さくらあっぱれーしょん」
「カッコつけても パンツパンツパンツはみ出てる」
脱がないことを前提の鉄のパンツ、見せないこと前提のはみ出たパンツに比べると、見せること、脱ぐこと大前提の勝負パンツなのですから、いやらしさを競えばつくん♂さんの歌詞が一番になります。
これを現役トップアイドルに歌わせ、さらに強引に組み込んだ感は少しもないのだから、痛快極まりないのです。
一人称は女性である「私」ぽいのですが、その目線は男性寄りです。
かわいさにたくましさと猥雑をミックスさせたつんく♂さんの歌詞にはいつもハラハラドキドキさせられます。
「お腹が減って来たわ 帰りにうどんでも食べてくわ」
ときめきや切なさを歌いあげるアイドルの楽曲が多い中、つんく♂さんの歌詞には生々しい現実が度々登場します。
上記の歌詞に登場する「うどん」、普通アイドルなら「クレープ」を食べるでしょう。
アイドルは虚構、誰もリアルなんか求めていないのに歌詞に「うどん」が出てくる、受け手は頭をガツンとやられた思いです。
現実をリンクさせた歌詞と言えば、森高千里さんの初期楽曲は彼女の私小説(のような歌詞)にそのままメロディーを乗せたものでした。
「今度私どこか連れていってくださいよ」も「この街」も歌詞全編彼女の思いだけでした。
これらの歌詞が和製ユーロビートに刻まれて小気味良いテンポを奏でていました。
微量の毒のよう、現実を喚起させる言葉を混ぜるのは有効な作詞手段のひとつなのかもしれません。
二重サビ
1回目のサビが始まります。
「ダンスでバコーン なんか全部忘れたい!
ダンスでバコーン 涙が止まらないよ!」
ここでファンは100%のヒートアップです。
歌詞から観察すると曲名にもなっている「ダンスでバコーン!」と盛り上がる訳です。
ダンスでバコーンと盛り上がっているのに涙が止まらない、女性特有の割り切れない心の空白感が表現されています。
このサビの時点でマックスの盛り上がりが、2回目のサビ
「こんなにすごく切ないの どうしてかわかんない
今まで溜めたストレスと 今夜でおさらばさ!」
が、さらに盛り上げます。
二重サビとでも名付けたいです。
こんな楽曲は今までなかったと思います。
サビの次にもっと盛り上がるサビ的なメロディが続くなんて。
ライブ映像では演者はさることながらファンの様子も目にするのですが、個々で盛り上がるファンたちにアイドルファンの原風景を重ねて見ることができます。
その場所で笑顔になっているファンには疑似恋愛も偏愛もありません。
楽曲と一体になっている昭和アイドルの親衛隊の「変な爽やかさ(やり切った感)」がそこにはあります。
「自分で作詞作曲両方する人はいいなあ、自分でメロを作れるのだから」と作詞家の仲間内でよく聞く言葉です。
しかし、作詞作曲する人の作詞によく見られる特有の余裕っぷりは、よく聴けば面白くもなんともない言い回しがあったりもします。
うまくは言えませんが、音譜が言葉を迎えに行った歌詞につまらなさを感じます。
メロがある、音譜の長短がある、この言葉を充てたいのに文字数が合わない……などのもがきがあって輝く歌詞もあるはずです。
そんなもがきを楽しむことができれば今日からあなたも本物の作詞家だと思います。