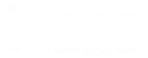【印象派】色彩豊かなピアノの名曲を厳選~ドビュッシー・ラヴェル~
19世紀後半にフランス・パリで起きた芸術運動「印象派」。
見たものを忠実に再現する写実主義がよしとされていた時代から、より自由な表現方法を求める時代への変化は、クラシック音楽史にも多大な影響を与えました。
そして、この印象派を代表する作曲家として後世に名を残したのが、クロード・ドビュッシーとモーリス・ラヴェル。
今回は、この2人の偉大な作曲家と、印象派の影響を受けたとされている19世紀の作曲家をピックアップし、光や色彩感を重要視した印象派らしさを感じさせる名曲をご紹介していきます!
- 【難易度低め】聴いた印象ほど難しくない!?ドビュッシーのピアノ曲
- 【難易度低め】ラヴェルのピアノ曲|難易度低め&さらっと弾ける作品を厳選!
- 【上級者向け】聴き映え重視!ピアノ発表会で弾きたいクラシック音楽
- 【イベールのピアノ曲】20世紀フランスの作曲家が手掛けた珠玉の名作
- 美しすぎるクラシックピアノの名曲。心洗われる繊細な音色の集い
- 【現代曲】ピアノの不思議な響きに惹かれるクラシック作品を厳選!
- 【プーランクのピアノ曲】エスプリの作曲家が手掛けた名曲を厳選
- 【中級レベル】華やかな旋律が印象的なピアノの名曲を厳選!
- 【セヴラックのピアノ曲】ドビュッシーが認めた天才作曲家による名作
- 【シャブリエのピアノ曲】フランス音楽のエスプリが手掛けた珠玉の名曲
- 名作が勢ぞろい|春を感じさせるピアノ曲
- 【フランクのピアノ曲】近代音楽の父による珠玉の名作を厳選
- 【ムソルグスキーのピアノ曲】組曲「展覧会の絵」の作者による珠玉の名作
【印象派】色彩豊かなピアノの名曲を厳選~ドビュッシー・ラヴェル~(11〜20)
物語 第8曲「水晶の籠」Jacques Ibert

フランスの作曲家ジャック・イベールは、新古典主義スタイルの音楽で知られ、ウィットに富んだ才気あふれる作品を多く残しています。
1919年にローマ賞を受賞したことを機に、彼の音楽家としての地位は不動のものとなりました。
この頃に書かれたピアノ曲集『物語』は、地中海やアジアの港を巡る旅から着想を得た色彩豊かな作品です。
『物語』の中でも特に人気が高い第8曲『水晶の籠』は、透明で壊れやすい美しさを感じさせるタイトル通り、繊細で幻想的な響きが魅力。
私たちの想像力をかきたて、心の奥底に閉じ込めていた大切な思い出を優しく解き放ってくれるような1曲です。
音楽を通して旅をする感覚を味わえる本作は、ピアノが奏でる多彩な表情を堪能したい方にぜひオススメしたい作品です。
組曲『鏡』 第4曲-道化師の朝の歌Maurice Ravel

芸術家グループ「アパッシュ」の仲間たちに捧げられた組曲『Miroirs』。
その第4曲は、スペインの朝を舞台に、道化師の姿が目に浮かぶような変化に富んだ作品です。
ギターの響きを思わせる乾いたリズムと情熱的な旋律が交差し、道化師の陽気さと、その裏に隠された哀愁を見事に描き出しています。
この楽曲は後に管弦楽にも編曲され、1919年にロンドンで上演されたバレエで使われたそうです。
難易度としては決して易しくはありませんが、技巧的なパッセージの中に歌心があふれる瞬間がちりばめられています。
表情が豊かなスペイン音楽の世界に浸りたい方や、技巧を通して表現の幅を広げたい方にぴったりです。
激しい部分と物悲しい中間部の対比を際立たせ、物語を語るように演奏してみましょう。
組曲『鏡』 第5曲-鐘の谷Maurice Ravel

1905年に作曲された組曲『Miroirs』の最後を飾る作品は、モーリス・ラヴェルがパリの街に鳴り響く教会の鐘の音から着想を得たとされる、幻想的な1曲です。
1906年1月に行われた初演でも、その独創的な世界観が高く評価されました。
この楽曲は、重厚な低音で表現される鐘の響きと、きらめくような高音の繊細な音色が溶け合い、聴く人を夢のなかのような瞑想的な空間へと誘います。
ペダルを巧みに使った色彩が豊かな表現や、情景を思い浮かべながら音色をコントロールする感覚を磨きたい方にぴったりの作品です。
空間に音が溶けていくようなイメージを大切に演奏してみましょう。
高雅で感傷的なワルツ 第1ワルツ,Modéré(モデラート) ト長調Maurice Ravel

伝統的なワルツに、モーリス・ラヴェルらしい近代的な響きを融合させた組曲『Valses nobles et sentimentales』。
その幕開けを飾る第1曲は、優雅でありながらどこか物憂げな、不思議な気持ちにさせられる1曲です。
この楽曲は、1911年5月の初演で作曲者名を伏せて演奏され、その斬新さで聴衆を驚かせました。
華やかな舞踏会で踊りながらも、ふと心によぎる秘めた想い…そんな情景が目に浮かぶようです。
バレエ『Adélaïde, ou le langage des fleurs』としても知られています。
本作は、これまでのワルツのイメージを覆すような、リズムやハーモニーの面白さを感じたい方にぴったり!
華やかさの奥に潜む憂いを表現できるよう、角のないやわらかい音で演奏しましょう。
高雅で感傷的なワルツ 第2ワルツ,Assez lent(十分に遅く)ト短調Maurice Ravel

心の奥深くを覗き込むような、内省的な雰囲気が魅力の作品で、モーリス・ラヴェルが手掛けた組曲『Valses nobles et sentimentales』に含まれています。
本作は1911年に、作曲者を伏せたままプライベートな演奏会で披露されたという逸話があります。
ゆったりと流れる時間の中に、感傷的でありながらも高貴な旋律が浮かび上がり、聴く人の心に静かに寄り添うかのようです。
伝統的なワルツのリズムに隠された、少々意外な響きが、言葉にならない複雑な感情を表現しているみたいですね。
繊細な音色の変化や、息の長いフレージングを学びたい方にぴったりな一曲。
神秘的な雰囲気を壊さないよう、一つ一つの音に想いを込めて、呼吸するように演奏するのがポイントです!
高雅で感傷的なワルツ 第5ワルツ,Presque lent ホ長調Maurice Ravel

組曲『Valses nobles et sentimentales』に含まれる、ひときわ内省的な一曲です。
1911年5月に匿名の新作発表会で初演された際、多くの批評家が作者をモーリス・ラヴェルだと見抜いたという逸話も残っています。
この楽曲には「親密な感情にて」と記されており、心の内側でささやかれる対話のような、とてもプライベートな雰囲気に満ちています。
寄せては返す波のようなメロディは、ため息のようでもあり、秘めた想いのようでもあり、聴く人の心に静かに寄り添います。
繊細なタッチや表現力を深めたい方にぴったりです。
感傷的で美しい世界観を大切に、角のないやわらかい音で丁寧に奏でましょう。
【印象派】色彩豊かなピアノの名曲を厳選~ドビュッシー・ラヴェル~(21〜30)
メヌエット嬰ハ短調Maurice Ravel

親しい作曲仲間への練習課題として1904年頃に書かれたとされる、わずか1分ほどの短い作品です。
古典的なメヌエットの形式の中に、ラヴェルらしい洗練された響きと、どこか内省的な雰囲気が漂います。
華やかさよりも、抑制された気品を感じさせるこの楽曲は、胸の内に秘めた繊細な感情をそのまま音にしたかのような、物憂げで美しい1曲。
本作は、ラヴェルの持つ独特の美意識に気軽に触れてみたいという方にぴったりです。
無駄な装飾を排した簡潔な構成だからこそ、一つ一つの音を丁寧に、そして優雅な舞踏のステップをイメージしながら演奏するのがポイント。
淡い雰囲気のなかで、心の機微を表現してみましょう。