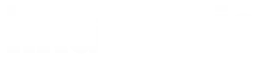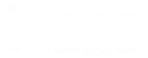【和風のピアノ曲】日本らしさが心地よいおすすめ作品をピックアップ
ピアノはヨーロッパで生まれた楽器。
そして、クラシック音楽は西洋で発展した音楽スタイル。
クラシック作品を中心に練習していると、どうしてもヨーロッパのエッセンスが盛り込まれた曲に偏りがちで、ピアノを弾きながら「和」を感じることは少ないかもしれませんね。
そこで本記事では「日本らしさを感じられる和風の作品をピアノで弾いてみたい!」という方に向けて、和風のピアノ曲をたっぷりご紹介します。
「和風」といっても、ヨーロッパの作曲家が日本の浮世絵に魅せられて作曲した作品から童謡を題材にした変奏曲まで、曲のルーツや形式はさまざま。
ぜひ、それぞれの作品の「日本らしさ」を聴き比べたり、作曲家によって異なる「和風」の解釈を楽しんだりしながらお聴きください!
- 【中級レベル】華やかな旋律が印象的なピアノの名曲を厳選!
- 【山田耕作のピアノ曲】日本の童謡唱歌の名作曲家が遺したピアノ作品たち
- 【印象派の音楽】日本の心を感じるクラシック作品をピックアップ
- 【三善晃のピアノ曲】現代日本音楽の巨匠が手掛けた珠玉の作品を厳選
- 【現代曲】ピアノの不思議な響きに惹かれるクラシック作品を厳選!
- 美しすぎるクラシックピアノの名曲。心洗われる繊細な音色の集い
- 【ピアノ曲】子供でも弾きやすい!簡単なクラシック作品を一挙紹介
- 【大人向け】ピアノ発表会にオススメ!聴き映えする名曲を厳選
- 【日本】和を感じられる邦楽・和風テイストなJ-POPまとめ
- 名作が勢ぞろい|春を感じさせるピアノ曲
- 【ピアノ】暑い夏に聴きたいピアノ曲!爽やかなクラシック作品を厳選
- 【ピアノ×J-POP】弾けたらかっこいい最新曲・アニソンを厳選
- 【印象派】色彩豊かなピアノの名曲を厳選~ドビュッシー・ラヴェル~
【和風のピアノ曲】日本らしさが心地よいおすすめ作品をピックアップ(11〜20)
君が代変奏曲成田為三

日本の作曲家、成田為三さんが1943年に作曲したピアノ曲『君が代変奏曲』。
14の変奏から成るこの楽曲は、国歌『君が代』のメロディをテーマに、さまざまな速度や感情を巧みに表現しています。
この曲には作曲当時の時代背景が色濃く反映されており、戦時下において純粋な音楽美を追求するという成田さんの音楽家としての信念が感じられます。
西洋の作曲技法をしっかりと習得し『君が代』という日本の素材を題材としたこの曲は、成田さんの音楽的才能と芸術への情熱を如実に表した作品といえるでしょう。
真夜中の火祭り平吉毅州

炎が燃え盛る情景を思わせる熱烈な日本人作曲家、平吉毅州さんによるピアノ独奏曲です。
ダイナミックで激しい響きと、緻密なアーティキュレーションが見事に調和し、夜空に舞い上がる火の粒を表現しています。
独特の変拍子が生み出す躍動感と、スペイン舞踊を思わせるリズムパターンが、聴く人の心を高揚させます。
2024年度PTNAピアノコンペティションの課題曲に選定されており、ピアノ学習者の技術向上に役立つ作品としても評価が高まっています。
短調の響きながらも暗さを感じさせない力強さがあり、暑い夏の夜に聴くことで心が躍るような清涼感が得られる一曲です。
お菓子の世界 第14曲 「鬼あられ」湯山昭

きらきらと硬質なピアノの響きが印象的なアルバム『お菓子の世界』に収録された小品です。
1973年に制作されたこの楽曲は、1分25秒という短い時間の中に、和と洋の要素を見事に融合させた独創的な世界を描き出しています。
イ短調の4分の4拍子で始まり、不協和音とスタッカートを巧みに操ることで、硬くて跳ねるような音の表現を実現。
3声のパートや複雑なリズム、テーマの変奏など、演奏の難しさと魅力を兼ね備えています。
発表会やコンクールで演奏されることも多く、表現力を試される作品として愛されています。
プログラムの締めくくりに効果的な一曲として、クラシック音楽の新しい魅力を求める方におすすめです。
「こどものピアノ曲」より 土人のおどり中田喜直

1分間の短いながらも迫力が溢れるこの楽曲は、アルバム『こどものピアノ曲』に収録された17曲の中でも異彩を放っています。
イ短調を基調とした力強いリズムパターンが、独特の緊張感と躍動感を生み出しています。
本作の魅力は、日本の伝統的な五音音階を用いながらも、民族音楽的な活力を持つ印象的な旋律にあります。
Pitinaピアノステップの課題曲としても採用され、基礎5のレベルで親しまれている楽曲です。
手の交差を伴う演奏技法は、観客に強い印象を与え、発表会やコンクールでの演奏に最適です。
聴衆を魅了する表現力と、奏者の技術を引き出す工夫がちりばめられた、見事な小品となっています。
風の即興曲中田喜直

アルバム『こどものゆめ』に収録された一曲は、まるで風が吹き抜けていくような爽やかな旋律が印象的です。
軽やかで流れるような自由なメロディが心地よく、グリッサンドの技法を取り入れた仕上がりは発表会でも魅力的な要素となっています。
本作は、流麗なフレーズと繊細なタッチが溶け合い、ピアノならではの表現力を存分に引き出した1分20秒の小品。
2011年のピティナ・ピアノコンペティションでC級の課題曲に選ばれた本作は、音楽の楽しさを感じながら技術を磨きたい方におすすめの一曲です。
手の大きさを考慮した自然な運指で、誰もが楽しく演奏できる工夫が施されています。
ナイト・オブ・ナイツビートまりお

疾走感があふれる高速メロディーと緻密な構成が織りなす、東洋的な要素を取り入れたダンスミュージックです。
軽快なビートとエネルギッシュなフレーズの組み合わせは目が離せない展開を生み出し、聴く人を魅了する独特の世界観を作り上げています。
本作は、インストゥルメンタル楽曲なのにもかかわらず、音の一つひとつが物語を語りかけてくるような、不思議な魅力を持ち合わせています。
2008年5月の発表以来、音楽ゲームやピアノアレンジなど多彩な形で展開され、その人気は衰えることを知りません。
華やかな演奏技巧を存分に活かせる楽曲のため、ピアノ発表会で聴衆を魅了したい方におすすめです。
【和風のピアノ曲】日本らしさが心地よいおすすめ作品をピックアップ(21〜30)
春がきて、桜が咲いて中田喜直

日本の四季を音楽で描いた組曲『日本の四季』の第1曲。
春の訪れと桜の開花を祝う喜びが表現されています。
ピアノ連弾の形式で、2人の奏者が協力して春の情景を鮮やかに描写。
日本の春を象徴する複数の旋律が巧みに織り交ぜられ、桜の花びらが舞い散る様子や春の穏やかな空気感を感じさせる美しい旋律が特徴的です。
日本の伝統的な旋律と現代音楽の要素が融合した叙情的な作品で、日本の春を感じたい方におすすめです。