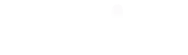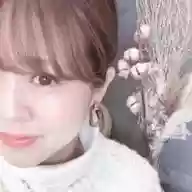【保育】3月を楽しもう!行事に関する遊びや自然遊びのアイデア集
3月はぽかぽか暖かく過ごしやすい日が増え、子供も大人も陽気な気分になりますよね。
今回はそんな3月にオススメの、春の訪れを感じる遊びのアイデアを紹介します!
3月におこなわれるひなまつりや卒園式など、行事に関係するものを中心に、屋内や屋外で楽しめる遊びを幅広くそろえました。
3月ならではの生き物や草花への関心が深まる遊びもたくさん紹介しているので、子供たちと一緒に春の訪れを感じながら、楽しい時間を過ごしてくださいね。
- 【保育】ひな祭りや桜など、3月にオススメ製作あそび
- 【保育】春のたのしい遊び。自然・運動・製作のアイデア
- 【年長】3月ってどんな季節?行事や自然物を折り紙で作ってみよう!
- 【子供会】簡単で楽しい室内ゲーム。盛り上がるパーティーゲーム
- 【年中】行事や自然物など、3月に作りたいオススメの折り紙アイデア集
- 【保育】4月におすすめの室内遊び・レクリエーションゲーム
- 小学1年生から6年生まで楽しめる遊びアイデア【室内&野外】
- 【2月】保育で盛り上がる!室内遊び&運動遊びのアイデア集
- 保育園、幼稚園向けのレクリエーション。たのしい子どもの遊び
- 【少人数の室内遊び】盛り上がるレクリエーション
- 【保育園・幼稚園】作った後に遊べる製作
- 【保育】3月の壁面飾りのアイデア
- 【小学校】すぐ遊べる!低学年にぴったりの室内レクリエーション
【保育】3月を楽しもう!行事に関する遊びや自然遊びのアイデア集(21〜30)
ひな祭りクイズ

「ひな祭り」がどういうものかを知れるクイズ大会を開いてみるのはいかがでしょうか。
シンプルかつ王道かつ盛り上がる!まず「クイズ」というだけでお子さんたちは食いついてくれるはずです!
ご紹介しているような動画やネット検索で出てくる問題が載っているサイトを活用したり、Wikipediaなどの情報を参考にオリジナルクイズを作ったり、発想次第でいろんな楽しみ方が!
難易度を低めに設定したければ、○×形式にするのがいいかもしれませんね。
ひな祭り工作

3月の行事で真っ先に思い浮かぶのがひな祭り!
童謡『うれしいひなまつり』を歌ったり、ひなあられを食べたり、男の子女の子わけへだてなく楽しいイベントですよね。
ということで、ひな祭りにちなんだ工作にぜひチャレンジ!
ぜひひな人形、ぼんぼりやひしもちなどひな飾りを作ってみてください。
動画サイトで調べてもらうと作り方がたくさん出てきますし、印刷して使う素材画像のダウンロードリンクが載せられている場合も。
自分たちだけのオリジナル飾りを考えるのも楽しいですよ!
【保育】3月を楽しもう!行事に関する遊びや自然遊びのアイデア集(31〜40)
ひな祭り手遊び歌

ひな祭りを楽しむアイデアはいくつかありますよね。
その中に手遊び歌を組み込んでみるのはどうでしょう。
歌って遊んで、春の暖かさをその身で体感!
『うれしいひなまつり』『けっこんしきをあげました』など、動画サイトで調べてもらうと振り付けが見られる童謡がいくつかありますのでぜひチェックしてみてください。
お子さんとのスキンシップとして、親子でのおうち時間で楽しむのも当然あり!
女の子も男の子も一緒になってやってみましょう!
卒園児へのプレゼント制作

卒園児に向けて在園児でプレゼントを渡す、その卒園プレゼントを制作として取り入れてみてはどうでしょうか。
制作で楽しめて、そしてもらう側の卒園児にも思い出に残る、そして実用的なプレゼントを作ってみましょう。
ダンボールや空き箱を使って写真立てを作って園での思い出の写真を入れたり、牛乳パックやペットボトルを使ってえんぴつ立て、小学校に行っても使えるしおりなどが実用性も高くオススメです。
卒園児たちへの思いを込めて、すてきなプレゼントを作ってくださいね。
お花見

地域差はありますが3月の中旬以降に楽しめるのがお花見。
桜がほころんでいる様子は眺めるだけでほっこり、春が感じられますよね。
お散歩がてら桜並木に寄ってみたり、園内に桜の木があるならその下でおやつを食べたり。
晴れた日にやると本当に気持ちいいんですよね!
また、暖かくなってくると桜以外の花も咲き始めます。
そういう草花を探すお花見、というのもありなんじゃないでしょうか。
4月が待ち遠しくなるイベントアイデアだと思います!
おわりに
3月のイベントにオススメのレクリエーションを中心にたくさんご紹介しましたが、ピンと来るものはあったでしょうか。
暖かくなったら外に出て、春ならではの自然の変化を子供たちにたくさん感じていってほしいですね。
年度末でもある3月、進級に向けて期待がふくらむように友達や先生、異年齢児と楽しい時間を共有する機会を増やしていきましょう。
みんなで素敵な思い出をたくさん作ってくださいね。