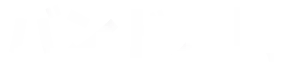未来はそんなに悪くないよ!音楽シーンの過去・現在・未来を考える 2/3
第一回に続き今回も「CD売上の減少」を、今度は社会的現象の視点から振り返ってみたいと思います。
1982年の誕生からソフト・ハード面一体となり一気に普及したCDは、成熟期と言える1990年代に黄金時代を迎えます。
ミリオンセラーの量産
今ミリオンセラーと言えば、ほぼAKB48一色。
しかも数々のバージョン違いや握手権と言った戦略で一人のファンが何枚も買うと言う状況、「のべ」を排除したユニークユーザという点で言うと実質ミリオンは皆無と言えるかも知れません。
しかし、CD売上全盛期にはミリオンセラーが年間20本以上も生まれる、今から考えると信じられないような状況がありました。
以下は1990年~2013年までの邦楽ミリオンセラーシングルの数と代表曲の一例です。
| 年 | 数 | 代表曲 |
|---|---|---|
| 1990 | 3 | B.B.クィーンズ「おどるぽんぽこりん」、米米CLUB「浪漫飛行」、KAN「愛は勝つ」 |
| 1991 | 8 | 小田和正「OH! Yeah!/ラヴ・ストーリーは突然に」、CHAGE&ASKA「SAY YES」、槇原敬之「どんなときも。」 |
| 1992 | 18 | 稲垣潤一「クリスマスキャロルの頃には」、米米CLUB「君がいるだけで」、中山美穂&WANDS「世界中の誰よりもきっと」 |
| 1993 | 16 | THE 虎舞竜「ロード」、ZARD「負けないで」、広瀬香美「ロマンスの神様」 |
| 1994 | 20 | 篠原涼子 with t.komuro「恋しさと せつなさと 心強さと」、松任谷由実「春よ、来い」、Mr.Children「Tomorrow never knows」 |
| 1995 | 32 | H jungle with T「WOW WAR TONIGHT」、桑田佳祐/Mr.Children「奇跡の地球」、DREAMS COME TRUE「LOVE LOVE LOVE/嵐が来る」 |
| 1996 | 24 | スピッツ「チェリー」、久保田利伸「LA・LA・LA LOVE SONG」、globe「DEPARTURES」 |
| 1997 | 17 | 安室奈美恵「CAN YOU CELEBRATE?」、globe「Can’t Stop Fallin’ in Love」、Kinki Kids「硝子の少年」 |
| 1998 | 20 | Every Littele Thing「Time goes by」、kiroro「長い間」、BLACK BISCUITS「タイミング」 |
| 1999 | 11 | 坂本龍一「energy flow(『ウラBTTB』)」、速水けんたろう/茂森あゆみ/ひまわりキッズ「だんご3兄弟」、モーニング娘。 「LOVEマシーン」 |
| 2000 | 14 | サザンオールスターズ「TSUNAMI」、慎吾ママ(香取慎吾)「慎吾ママのおはロック」、福山雅治「桜坂」 |
| 2001 | 5 | 宇多田ヒカル「Can You Keep A Secret?」、桑田佳祐「波乗りジョニー」、CHEMISTRY「PIECES OF A DREAM」 |
| 2002 | 1 | 浜崎あゆみ「H」 |
| 2003 | 2 | 宇多田ヒカル「COLORS」、SMAP「世界に一つだけの花」 |
| 2004 | 3 | ORANGE RANGE「花」、福山雅治「虹/ひまわり/それがすべてさ」、森山直太郎「さくら(独唱)」 |
| 2005 | 1 | 修二と彰「青春アミーゴ」 |
| 2006 | 1 | KAT-TUN「Real Face」 |
| 2007 | 1 | 秋川雅史「千の風になって」 |
| 2008 | なし | |
| 2009 | なし | |
| 2010 | 1 | AKB48「Beginner」 |
| 2011 | 5 | AKB48「フライングゲット」(他、4作ともAKB48の楽曲) |
| 2012 | 5 | AKB48「真夏のSounds good!」(他、4作ともAKB48の楽曲) |
| 2013 | 5 | AKB48「さよならクロール」(他、4作ともAKB48の楽曲) |
もちろん1990年までにもミリオンセラーはあったようですが(例:「およげ!
たいやきくん」、寺尾聰「ルビーの指輪」、ピンクレディー「サウスポー」等)、これまでのミリオンセラー作品中約65%が1990年代に集中しています。
| 年 | 数 |
|---|---|
| 1960年代 | 8 |
| 1970年代 | 25 |
| 1980年代 | 11 |
| 1990年代 | 169 |
| 2000年代 | 28 |
| 2010年代 | 16 |
ドラマ主題歌とのタイアップ
バブル絶頂期の1980年代末~1990年にかけ、横文字カタカナの職業名を持ち都会でスタイリッシュに過ごす男女を描いた「トレンディードラマ」と呼ばれるイケイケ(死語)の一ジャンルがありました。
その流れから生まれたのか分かりませんが、まだバブルの香りは残りつつも「憧れ」ではなく「不器用でリアルな葛藤」を描いた『東京ラブストーリー』が登場。
まだ「月9」という言葉はなかったようですが、「月曜夜9時の街からOLが消えた」との話を聞いたことがあるように、絶大な支持を得たドラマでした。
その主題歌が小田和正「ラヴ・ストーリーは突然に」、ここからヒットシングルとドラマ主題歌タイアップという黄金の蜜月関係が始まります。
それまでももちろんドラマ主題歌とのタイアップで売れた作品はあったようですが、CDというメディアが再生ソフトの頂点に立ち、その販売数・タイアップの破壊力はそれまでとは一線を画していました。
『東京ラブストーリー』と「ラヴ・ストーリーは突然に」小田和正
『101回目のプロポーズ』と「SAY YES」CHAGE & ASKA
『愛という名のもとに』と「悲しみは雪のように」浜田省吾
『ホームワーク』と「クリスマスキャロルの頃には」稲垣潤一
etc.
ドラマは30%超えも含む好視聴率を連発し、その主題歌はそれに呼応するかのようにミリオンを連発。
1990年代のヒットソングの多くはドラマ主題歌とのタイアップであり(ミリオン超えも惜しくも未満も)、CD売上に大きく貢献したのは紛れもない事実でしょう。
では、なぜドラマはヒットし、蜜月関係はかくもリンクしたのでしょうか。
これは私の想像でしかありませんが。
ドラマの作品数は今とそれほど大差なく、クオリティは少なくとも映像技術に関しては現在の方が高いでしょう。
シナリオや脚本はもしかしたら当時の方がより落とし込まれていたのかも知れません。
が、作品の優劣=視聴率ではないだろうと想像します。
1990年代当時はインターネットも携帯電話もない時代、まだ「テレビを視聴する」文化がありました。
バブルが弾け、外で接待・遊ぶ機会よりも家でテレビを見る時間も増えたのではないでしょうか。
そこに「憧れ」よりも「共感」を生むリアリティあるドラマがあり、ドラマの内容とリンクした主題歌(当時はドラマの内容をもとに曲を書いてもらっていたとのこと)が視聴者の心を掴み、その曲が好きなことはもちろんカラオケネタとしてもCDを買う。
レコード会社サイドとしても、高い広告宣伝費を雑誌やCM等に払うより、タイアップを取ることの方が費用対効果が高かった、そんな循環があったのではないかと思います。
参考:ドラマ主題歌CD売上枚数ランキング | 年代流行
http://nendai-ryuukou.com/article/023.html
イカ天:三宅裕司のいかすバンド天国
同じくテレビ関係では、バンドマンにとって「イカ天」は関係性の高い番組であり、放送当時のCD売上を考える上でも重要な番組ではないでしょうか。
1989年2月11日~1990年12月29日まで、約2年という短い放送期間ながら、勝ち抜きバンドコンテストであるこの番組から、Blanky Jet CityやFLYING KIDS、BEGIN、JITTERIN’ JINNらを輩出しました。
実は私は直接番組を見たことはありませんでしたが、バンドをやっている仲間連中では知らない者はいない程の名物番組でした。
数々のビッグネームを輩出したことはもちろん、こういった形式の音楽番組が作れるくらいに、当時はバンドブームでありバンド人口は多かったのでしょう。
歴史的には「第二次バンドブーム」と言われるようで、BOφWYやレベッカ、ハウンドドッグ等の台頭により喚起され、この「イカ天」がブームに火をつけたとされています。
当時のバンド人口がどれ程だったのか、客観的に明示できる資料がないので分からないのですが、
・恐らくバンドをやっていたであろうボリュームゾーン:18歳~24歳を中心とした年齢層でバンド人口率がどの程度か高まった。
・バンドマンはそうでない人よりCDを多く買うウォンツもニーズもある。
・当時バンドマンに必要な知識・技術等が得られるのは雑誌や教則本、VHSビデオ、そして何よりCDだった。
・18歳~24歳頃は可処分所得が多く好奇心・学習意欲も高い、また他にお金を費やす対象も今より少なかった。
等の理由から、第二次バンドブーム期前後のCD売上を、(僅かなのかも知れませんが)バンドマンが底上げしていた可能性を指摘します。
人口動態
単純に、年齢・年代別人口数というものも、CD売上には大きく関わってくるでしょう。
私自身を振り返っても、CDを一番多く購入していた時期は20歳前後であり、購入した枚数を年齢毎にカウントすればおそらくそこをピークに山なりのグラフになると思うのです。
そして、それは多くの人に当てはまる傾向ではないかと思います。
その理由としては、20歳前後が
・音楽に対する興味が高い≒まだ知らない音楽や聴きたい音楽が沢山ある。
・可処分所得が多い。
バイトや仕事である程度収入があり、使い道も比較的自由。
・値段が高過ぎる訳ではない。
・趣味の一つや日常生活の一部として少なからず音楽は聴く。
からです。
これは京都市の人口構成なので若干全国的な傾向と違いますが(京都は大学が多いので18-22歳あたりが増えますが、全国的には年齢毎に減少しているでしょう)、例えば1991年に18-24歳頃であった現41歳~47歳は、現在の18~24歳に比べ30%程人口は多くなっています。
もちろん他の年代の方もCDを買いますし、「年代別人口減少=CD売上減少」と一概に合致はしないでしょうが、ボリュームゾーンは当時より縮小しておりその傾向は今後も続くのは確実かと思います。
インターネットと携帯・スマホの普及
1990年代との比較で言うと、大きく変わった点がインターネットと携帯電話(近年ではスマホ)による情報革命です。
仕事においても日常生活においても、ネット&携帯はもはや必須の存在となりました。
インターネットの普及により、
・ファイル共有による音楽データの違法ダウンロード
・YouTube等動画サイト閲覧による視聴の代替、もしくは音源データ化
等が、CD売上の減少に関わる悪影響としてたびたび指摘されます。
「全く同一もしくは劣化コピーの流布と原本流布との相関関係」については、MDの登場やレンタルCDという業務形態においてと同様、「デジタルデータ」であるCDが根本的に生まれ持つ問題です。
業界からは、その関係については売上を妨げる悪としてやり玉に上がることが殆どだと思いますが、一方で単純に悪ではなくむしろCD売上を補完する・音楽ファンの裾野を広げるといった指摘・研究もあります。
参考1:音楽 CD 売上減少の要因についての考察 | 愛知工業大学
http://aitech.ac.jp/lib/kiyou/41B/B22.pdf
参考2:CDレンタルがCD売り上げに与える影響(docファイル)
http://www.geocities.jp/gindama_mos/mitasai.doc
CD(及びダウンロードも)が常に抱えてきたこの問題は、「複製権を買う」から「アクセス権を買う」ストリーミング・サブスクリプションによって解決するのかも知れませんね。
そして、携帯電話の普及は、「着うた」ダウンロード販売にはかなり寄与したようですが、ここ最近のスマホシフトによりその販売量は減っているようです。
「(携帯の)通信費が高くて、CDに回すお金がないのでは?」という話も聞きますし、実際よく通話される方は万単位で支払っているとも聞きます。
通信費の他にも、ソーシャルゲームやLINEのスタンプ等、1990年代には存在せず今の若い方を魅了する有料コンテンツは沢山あり、音楽CDはその競合相手に苦戦しているところはあるのでしょう。
世界的情勢とガラパゴス化する日本
世界的なトレンドとしては完全にストリーミング・シフト。
市場規模としては2013年は前年比3.9%減の約150億ドル、世界2位の音楽市場である日本の停滞が指摘されています。
世界2位ながら、CDを含むパッケージ販売が占める割合が80%という高い数値を示す特殊な国が日本です。
「世界的にもCDは売れない、日本でもCDは売れない、だけど日本ではCD売上比率が高い」全体的にはストリーミングの方向にシフトはしつつ、CDも併存する形で残っていくのかも知れません。
しかし、売上高も販売数も、全体に占める比率も、全て下がっていくことはもはや間違いないと思われます。
「音楽もアートワークも含めたトータルパッケージ」としてのCD作品、私もそのど真ん中の世代ですので、その衰退には郷愁を感じずにはいられません。
しかし、「失われた20年」と言われる日本経済よりも長く30年以上に亘りその主役であり続けたCDは、十分その役目を果たし次代にバトンタッチする時期なのでしょう。
そしてバンドマンの夢は
2回にわたりCD売上の変遷について見てきましたが、「CDが売れなくなった」というより「1990年代に異様な程売れていた」のであり、嘆くことではなくある種身の丈にあってきた現在と捉えることができるのではないでしょうか。
「CDバブル」とも言えるその時代に築き上げられたスキームやエコシステムは、やはり現在には通用せずそれも身の丈にあった環境に再構築しなければなりません。
かつては「CD売上に支えられていたので、ライブ・コンサート事業では赤字を出しても全く問題がなかった」という時代もあったそうです。
時代は変わりました。
しかし、悲観することではなくこれはチャンスだとも思うのです。
実際、様々な方法で今の時代を切り開くアーティスト活動や支援活動も動き始めています。
「レコード会社からCDを出してメジャーする」バンドマンにとって確かにそれは夢でした。
その構図は崩壊したとはとまでは言わずとも、かつてのように単一の価値観ではなくそのロードマップも狭き道になっています。
しかし、「夢」は「CDを出すこと」ではなく「自分達の音楽をより多くの人に知ってもらい共感してもらうこと(プロを目指すならさらにそれをマネタイズすること)」のはずです。
CDはそのための手段の一つであり、誰にでも分かりやすいポップ・アイコンだったのだと思います。
だからと言って嘆くのではなく、「こんなやり方もある」「こんなアイデアはどうか」バンドマンそれぞれがベンチャーのように色んなアプローチが出来る、そしてYouTubeやSNS、ハイレゾ配信やアナログレコード、路上ライブやカフェライブ、クラウドファンディング等、デジタルでもフィジカルでも、オンラインでもオフラインでもやれることはアイデアの数だけあります。
大手レコード会社からのトップダウンではなく、バンドマンそれぞれからのボトムアップ、今の時代をそう肯定的に捉えたいと思います♪