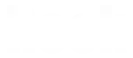【90年代ヴィジュアル系】名古屋系の代表的なバンドたち
ヴィジュアル系の中でも、とりわけアンダーグラウンドな世界観で熱狂的なファンも多い「名古屋系」と呼ばれるサブジャンル、およびシーンの総称をご存じでしょうか。
起源は諸説あるのですが、1990年代初頭に活動を開始した黒夢とSilver-Roseが2大巨頭とされ、まだヴィジュアル系という言葉もなかった時代において、名古屋のインディーズ・シーンで活躍したバンドたちがいつしか「名古屋系」と呼ばれるようになったのです。
本稿では、そんな名古屋系と呼ばれた90年代のバンドたちを紹介しています。
ヴィジュアル系を掘り下げたい方はもちろん、日本のインディーズ音楽の歴史を語る上でも欠かせない名古屋系の存在をこの機会にぜひ知ってください。
- 1990年代ビジュアル系の扉を開くヒット曲&名曲集
- 90年代のビジュアル系バンドのデビュー曲
- ヴィジュアル系の名曲。V系ロックを代表する定番の人気曲
- 【ネオ・ビジュアル系】2000年代のV系バンドの人気曲まとめ
- 【闇の美学】ゴシックロックのすすめ~代表的なバンド紹介
- 【BUCK-TICKの名曲】圧倒的な存在感を放つ伝説のバンドの人気曲
- 再結成求ム。惜しまれつつ解散した伝説バンド
- 長崎県出身のバンド・アーティスト・歌手
- 【平成レトロ】90年代を代表する邦楽ヒット曲。おすすめのJ-POP名曲
- DIR EN GREY(ディル・アン・グレイ)の名曲・人気曲
- 80年代のビジュアル系バンドのデビュー曲
- 【90年代音楽】渋谷系の名曲。おすすめの人気曲
- 黒夢の人気曲ランキング【2026】
【90年代ヴィジュアル系】名古屋系の代表的なバンドたち(11〜20)
Heart to Heartsus4

黒夢の清春さん、Of-Jの間宮馨さんが在籍していたことで知られているSUS4。
音楽史的に見れば、ある意味90年代名古屋系の始まりの始まりなバンド、と言えるかもしれません。
TWITTERでSilverーRoseのボーカリストであるYOWMAYさんが「名古屋系の本当の元祖はSus4の間宮氏」といった意味の発言をしていることを思うと、当事者としてはそのような認識を持っているのだなと興味深いですよね。
1989年から1990年辺りまでの短い活動期間の中で残された音源としては配布を含むデモテープを残すのみ、当時の音を聴く限りでは初期のBUCK-TICKのようなビートロック的な音を鳴らしていたようで、間宮さんのギタリストとしての才能や一聴してそれと分かる清春さんのボーカルはこの時点で個性を確立しているのは驚きですね。
もちろん音源入手は困難を極めるというのが実情ですが、名古屋系を深掘りしていくのであれば知識としてだけでも存在は知っておくべきバンドでしょう。
CHAOSDIE-ZW3E

DIE-ZW3Eというバンド名を初見で正確に読める方は、恐らくいらっしゃらないですよね。
DIE-ZW3Eと書いて「ディザイ」と読ませる彼らもまた、90年代名古屋系を深掘りしていく中で重要な存在です。
名古屋系のつながりという意味では、名古屋系最初期に活動していたMANICUREのメンバーが参加しており、メジャー・デビュー直後のROUAGEにベーシストとして参加していたギタリストのYUKIさん、黒夢の臣さんやOF-JのMASATOSHIさんが在籍していたGERACEEのベーシストであるTOMOKIさんといった面々が集ったバンドなのですね。
さらに言えば、SOPHIAのベーシストとして名を馳せる黒柳能生さんも一時期在籍しておりました。
そんなディザイというバンドの音楽性は、初期のミニアルバム『Di・es I・rae』にはカラーの違うツインのギターを駆使したサウンドや性急なビートに90年代ヴィジュアル系らしい要素は感じられるものの、名古屋系特有のダークネスとはまた違った魅力を持っていることはすぐに理解できるでしょう。
ボーカリスト、結城敬志さんによる張りのある力強い歌声で歌われる歌詞に描かれるのは、若者の持つ葛藤やナイーブな心象風景といった趣で、ヴィジュアル系にありがちなデカダンな闇とは一線を画す世界観が特徴的です。
1994年にリリースされたフル・アルバム『SIDE-B』は名古屋系ヴィジュアル系はもちろんLUNA SEA辺りからの影響も顕著に感じさせつつ、彼ら独自の音楽性が見事に花開いた名盤となっていますから、中古ショップなどで見かけたら確実に入手しておきましょう!
DarlingCROW-SIS

今も現役で活動している90年代名古屋系のプレイヤーたちは多く存在していますが、YouTubeの公式チャンネルを持ちバラエティ番組のような企画をこなしているCROW-SISはかなり珍しいバンドかもしれません。
1993年に名古屋で結成されたCROW-SISは、ROUAGEのローディーも経験しており当時のシーンにおいて重要な位置を占めていた事務所「Noir」に所属していたのですから、まさに純度120%の名古屋系バンドなのですね。
当時の彼らが残した音源としては配布デモテープが数本、オムニバスCDへの参加、2000枚限定で1996年に発売された唯一のCD作品『CLOSE』のみ。
興味を持たれた方であれば、比較的入手しやすい『CLOSE』を探していただくのが一番でしょう。
残念ながら演奏能力や歌唱力に難があるのは事実ではありますが、今回紹介している『Darling』などいかにもヴィジュアル系の王道をいくマイナー調のメロディアスな楽曲など、名古屋系およびヴィジュアル系マニアであれば心をくすぐられる楽曲の存在はぜひチェックしてもらいたいですね。
孤独の中で愛した君WITH SEXY

名古屋系のバンドではないのですが、九州出身の実力派ヴィジュアル系バンドとして知られていたVasallaに参加したメンバーが多く関わっていたのがWITH SEXYです。
SilverーRoseのメンバーであり、ROUAGEを脱退した後のベーシストのKAIKIさん、SyndromeやDのSINさんといった面々も参加しており、在籍していたメンバーを知るだけでもヴィジュアル系のファミリーツリーを眺めているような気にさえなってしまいそうですね。
立ち位置的にはLAPUTAやROUAGEよりやや下の世代であり、1996年には5カ月連続のシングル発売など精力的な活動をしていた彼らが唯一残したアルバム『Couleurs』は1997年に発表されています。
前述したVasallaでもコンビを組むRINNEさんと戒依さんがツイン・ギターとして活躍、KAIKIさんが作曲した楽曲も含まれた作品であり、彼らの集大成のような作品と言えましょう。
空間系のエフェクターを駆使したメロディアスなギター、性急なビート、メロディアスなボーカルは名古屋系のダークネスよりもどちらかと言えば白系に寄ったもので、ポップで聴きやすいですね。
強烈な個性や世界観という意味では弱いものの、黒夢やLAPUTA的な名古屋系とはまた違ったサウンドとして楽しんでみてはいかがでしょうか。
Night’s雫…
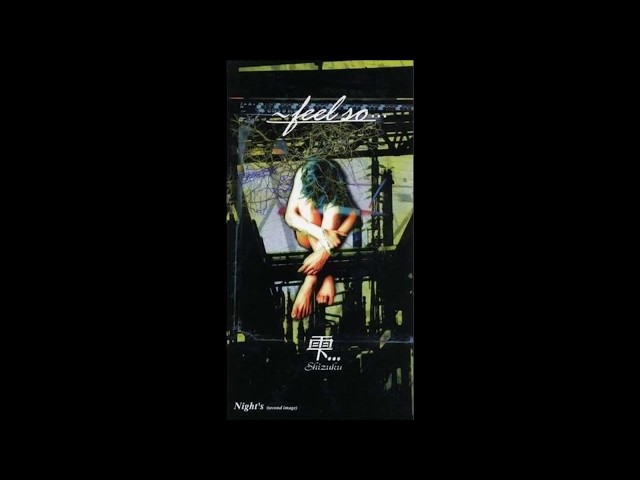
雫…は名古屋系らしいサウンドを継承しながらも後に「反戦」というテーマを押し出したヴィジュアル系という枠内では非常に珍しいタイプのバンドです。
KIZ-ETUというバンドで活動していたメンバーと、ROUAGEのRAYZIさんが参加していたSILU:ET!のメンバーを中心として1994年に結成、1999年の解散までの約5年程度の活動期間ではありましたが、メジャー流通も含めていくつかの作品を残した彼らの音楽性は、90年代ヴィジュアル系および名古屋系の奥深い魅力を表していると言えそうですね。
DIE-ZW3E辺りもそうですが、必ずしも耽美的であったりデカダンスな闇の要素だけが名古屋系というわけではない、ということです。
そんな雫…に興味を持たれた方であれば、まず手にしていただきたいのが1997年にリリースされたメジャー流通のフル・アルバム『夢を忘れた遺伝子』です。
あのLADIES ROOMのNAOさんがプロデュースを務め、線の細いヴィジュアル系とはまた違った男らしく骨太でアグレッシブなバンド・アンサンブルは水準以上のレベルで、社会的なメッセージを含んだ歌詞が作り出す世界観は今聴いても独特なものがありますね。
難を言えばボーカルの音域の狭さや、ある意味ヴィジュアル系らしい良くも悪くも微妙に盛り上がりきらないメロディ展開などに厳しさを感じてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
全体的にはメロディアスな作風ですし、名古屋系を掘り下げて間もないという若い方は早い段階で彼らの音楽に触れてみるのも悪くない選択と言えそうですね。
インディーズ時代の名盤『月が闇に翳るとき・・・』などもオススメです!
Fin(夜を越えて…)TI+DEE

かなりマニアックなバンドではありますが、TI+DEEは90年代の名古屋系バンドとしてかなり早い段階から活動していたバンドです。
Of-JやCLAUDIAなどの活動で知られる京野さん、Merry Go RoundのMAXXXさんがベーシストとしてそれぞれ在籍、後のDIE-ZW3EやSilver-Roseのメンバーがいたことで知られるMANICUREのボーカリストのAMOURさんがドラマーという、まさに名古屋系の歴史が詰まった存在なのですね。
彼らもまた、多くの音源を残すこともなく解散してしまったバンドではありますが、1994年にリリースされた唯一の7曲入りアルバム『Fin.』を聴けば、王道の名古屋系とはまた違ったサウンドを模索していたことが理解できるはず。
ヘビーメタルを基調としながらもクラシック音楽への傾倒が感じ取れるギター・フレーズや音階、荘厳なシンセやピアノを導入してほんのりシアトリカルな雰囲気もあり、メロディはJ-POPというか歌謡曲的、病的かつ猟奇的な名古屋系とは一線を画す耽美さを目指していたであろう音世界で実に興味深いですね。
同年にMALICE MIZERがデビュー・ミニアルバム『memoire』をリリースしていることを踏まえると、偶然ながら同時代的な音のつながりを発見できるのもおもしろいですよ。
残念ながら毎回のことですがCDは廃盤で入手困難、名古屋系をとにかく知り尽くしたいという方はオークションや中古ショップなどを定期的にチェックしてみることをオススメします!
おわりに
名古屋系、と一括りにされているバンドにはそれぞれの魅力があり、鳴らしているサウンド自体必ずしも同一の方向性ではないことが今回の記事をご覧頂いた方は理解できたのではないでしょうか。
とはいえ、多くの名古屋系とされるバンドに共通している点は、やはり独自の「闇」やアンダーグラウンドな雰囲気です。
メジャーの音楽シーンに対する反抗精神は、後続のバンドたちに大いなる影響を及ぼしたのです。