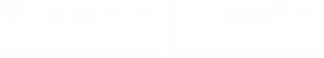ノイズミュージックの名盤。~インダストリアルからジャパノイズまで
通常の音楽的な楽曲構成や音作りを無視したような手法で、時には純粋な楽器ではなく金属物や自然界に流れる音のサンプリング、その他ありとあらゆる方法を駆使したアーティストたちの自由な発想で生まれる「ノイズ・ミュージック」は、言葉通り聴く人を不快にするほど非音楽的なものです。
本稿では、ノイズ・ミュージックを語る上では欠かせない「インダストリアル・ミュージック」と呼ばれるジャンルの代表的なバンドの名盤を中心として、世界的に「ジャパノイズ」として高い評価を受ける日本のアーティストたちの作品も紹介していきます。
雑音の中にしか得られない特別な感覚を、ぜひこの機会に味わってみてください。
- ダークサイケの名曲|暗く怪しいサイケの世界へ…
- 気持ちが悪い音楽。邦楽の名曲
- 【混沌の電子音楽】ドリルンベースの名曲まとめ
- 日本発!テクノポップの名曲・オススメの人気曲
- アーティスト名でよく見る「a.k.a.」の意味って?
- 【2026】美しきエレクトロニカ~オススメの名曲・人気曲
- アートコアとは?|アートコアの名曲や定番曲を紹介!
- 【印象派の音楽】日本の心を感じるクラシック作品をピックアップ
- ダンサーが選ぶ、20代にオススメのダンスミュージック。人気の曲集
- ミニマルテクノとは?心地よい反復が生む音楽の魅力を解説します
- 攻撃的ダンスミュージック。ハードコアテクノの名曲
- 【ノレる】リズムのいい邦楽。楽しくなる曲
- 【本日のジャズ】今日聴きたい!往年の名曲や現代ジャズをピックアップ
ノイズミュージックの名盤。~インダストリアルからジャパノイズまで(1〜10)
NeuridrinaEsplendor Geométrico

スペインを代表するインダストリアル・ミュージック・グループのエスプレンドー・ジオメトリコは1980年に結成され、特徴的なグループ名はイタリアの未来派詩人F. T. マリネッティによるエッセイ『幾何学的および機械的かがやきと数的感受性』から引用されたものです。
荒々しいハーシュノイズとインダストリアル特有のマシン・ビートを用いたサウンドを特徴として、2020年代の今もバリバリの現役として活動している彼らはノイズ・ミュージックのみならず、先鋭的な電子音楽家たちにも多大なる影響を与えているのですね。
今回紹介しているのは、近年は入手困難だった作品が次々とリイシューされ、再評価も進んでいる彼らが1981年にリリースした『Eg -1』です。
オリジナル版はカセット・テープとしてリリースされ、2021年にはリリース40周年を記念したレコードとしてリイシューされています。
凶暴なノイズと反復するミニマルかつ冷徹なマシン・ビートはインダストリアルの基本形であり、テクノ・ミュージックの原型とも言えそうな要素を兼ね備えている点も見逃せませんね。
イギリスのインダストリアル・ミュージックとはまた違った形で展開する独自のノイズが、イタリアで生まれていたという歴史的事実を知る上でも必聴と言える1枚です!
Spread The VirusCabaret Voltaire

芸術や文学などに詳しい方であれば、キャバレー・ヴォルテールというグループ名だけで彼らが普通の音楽グループではないことに気付くはず。
1973年にイギリスはシェフィールドで結成されたキャバレー・ヴォルテールは、いわゆるダダイスムの発祥の地とされるスイスのキャバレーの名前からそのグループ名を拝借したインダストリアル~エレクトリック・ミュージックのグループ。
カットアップの手法などを駆使して実験的なインダストリアル・サウンドを鳴らしていた彼らは、後にエレクトリック・ダンス・ミュージックへとサウンドをシフトしますが、1981年にリリースされたサード・アルバム『Red Mecca』は、初期の実験精神とわかりやすい音楽としてのフォーマットが見事なバランスで成立した作品として名高い傑作です。
トリオ編成だった頃の最後の作品でもあり、初期のキャリアにおける1つの集大成と言えるかもしれませんね。
チープなドラム・マシーンによるエレクトロ・ビート、ミニマルなギターやシンセ、エフェクトが施されたボーカルが呪術的な音世界を作り上げており、ノイズも計算された形で音の装飾として使われている印象です。
スロッビング・グリッスルと並ぶインダストリアル・ミュージックの立役者であり、良い意味で「商業音楽」としてのインダストリアル・ミュージックを作り上げた彼らの功績を知りたければ、ぜひ本作を聴いていただきたいですね。
The Honour of SilenceDeath In June

おそらく、暴力的なノイズや電子音といったノイズ・ミュージックの基本的なイメージを持って本作『Nada!』を聴いた方であれば、一般的な音楽の構成とゴシックな雰囲気も漂うメロディを持った曲を前にして思わず拍子抜けしてしまうかもしれませんね。
デス・イン・ジューンはCrisisというポストパンク・バンドで活動していたメンバーが1981年に結成したグループで、彼らのサウンドはいわゆる「ネオフォーク」と呼ばれています。
とはいえフォーキー一辺倒というわけではなく、電子音によるコラージュ・ノイズなどさまざまな要素をブレンドさせ、欧州古代神話や第三帝国をモチーフとしたエクスペリメンタルな音世界はまさに孤高の一言。
1985年にリリースされた通算3枚目となるアルバム『Nada!』は、政治的な理由で分裂してしまったグループを中心人物のダグラス・ピアーズさんが再始動させた仕切り直しの1枚であり、傑作として名高い作品です。
「無」と名付けられたタイトル通り、どこまでも虚無的で深い闇の底へと落ちてしまいそうなサウンドを聴けば、ノイズ~インダストリアル・ミュージックの世界にはこのような音楽も存在しているのだ、と理解できることでしょう。
ネオフォーク、ポストパンク、ネオサイケやダークウェーブといったジャンルに興味がある方も、ぜひ一度は彼らの音楽を体験してみてください。
ノイズミュージックの名盤。~インダストリアルからジャパノイズまで(11〜20)
Lion Of Kandahar (Extended Re-Mix)Muslimgauze

ムスリムガーゼ、という不思議な語感を持ったアーティストネームは、イギリス人音楽家のブリン・ジョーンズさんによるソロユニットです。
1982年の活動開始以来、1999年に37歳の若さでこの世を去るまでにジョーンズさんが発表したアルバムや楽曲は膨大なもので、公式のディスコグラフィを眺めるだけでも圧倒されてしまいますね。
ご本人が望んだものではないというのは皮肉ではありますが、亡くなってからも多くのリミックス版などがリリーされ続けていることから、後続のアーティストたちに与えた影響の大きさも分かるというものでしょう。
今回取り上げている『Iran』は1988年に発表された作品で、ムスリムガーゼ名義としては初のCDとしても有名なアルバムです。
インダストリアル的な要素は控えめとなっており、タイトル通りエスニックな要素をたっぷりと含んだ独自のブレイクビーツはノイズ~アバンギャルド・ミュージックに興味を持たれている方々はもちろん、テクノやワールド・ミュージックを愛聴している音楽好きにも楽しめるはず。
ムスリムガーゼといえばその政治的なメッセージや思想も欠かせない要素ではありますが、まずは電子音楽と中東音楽をミックスさせたプリミティブなサウンドのおもしろさを味わってから、楽曲の背景にあるアーティストの意思を知るというのも決して悪い選択肢ではないでしょう。
Ultra Cockerハナタラシ

ノイズ、ひいてはジャパノイズの著名アーティストたちの名前はインパクトの強いものが多い印象ですが、後にボアダムスのフロントマンとして世界的な知名度を得る山塚アイさんの音楽家としての第一歩、ハナタラシもまた日本人であれば一発で覚えてしまうバンド名ですね。
ハナタラシは1983年に山塚アイさんを中心として結成されたハードコアパンク~ノイズバンドであり、その悪名高いライブ・パフォーマンスも含めて、80年代地下音楽シーンの伝説として永遠にその名を残すこととなりました。
日本の老舗インディーズ・レーベル、アルケミーレコードから1985年にリリースされたセルフタイトルのファースト・アルバムは、ライブにおけるプリミティブな破壊衝動と混沌がそのまま音として記録されてしまったが如き作品。
遠慮なく襲い掛かるノイズの嵐、お経のようなボーカル、ある意味極限までハードコアでパンクなサウンドは純然たるインダストリアル・ミュージックとはまた違った形の、行き場のない怒りと暴力性と破壊衝動だけで構成されたノイズの塊を味わえる……と表現できるかもしれません。
ボアダムスの音を気に入った方がいきなりこの音に手を出すのは厳しいと思われますから、注意が必要です!
Senzuri Championザ・ゲロゲリゲゲゲ

日常生活において絶対に口にできないタイトルが素晴らしい、ジャパノイズの鬼才による1987年リリース名盤!
1985年より活動を開始した山之内純太郎さんによるソロ・プロジェクト、ザ・ゲロゲリゲゲゲの記念すべきデビュー・アルバムです。
インパクトの強すぎるユニット名に負けない音と活動を続ける山之内さんですが、何と高校時代にあのメルツバウで知られる秋田昌美さんにデモ・テープを送ってデビューを飾る、という経歴を持っています。
ノイズ・ミュージックの世界は若くして活動を開始する早熟なアーティストが多いイメージですが、山之内さんもその中の1人だったということでしょう。
デビュー・ライブで早稲田大学の講堂に穴を開けるという、文字通りエクストリームな存在のザ・ゲロゲリゲゲゲですから当然音も普通ではありません。
こちらの『Senzuri Champion』はどこまでもパンクかつハードコア、やりたい放題のノイズと奇声大会!
オリジナル版は廃盤となっており、2012年には全未発表バージョンの再編集を施した改訂版がリリースされました。
余談ですが、彼らの音楽性はあまりにも幅広く、ノイズというのは1つの側面でしかないのですね。
彼らに興味を持ってしまった方は、ぜひ他の作品もチェックしてその都度驚かされてください!
Endless SummerFennesz

あの坂本龍一さんとのコラボレーション作品なども手掛け、2000年代以降の電子音楽~音響~エレクトロニカといったジャンルにおける異才、クリスチャン・フェネスさん。
Fennesz名義での活動が特に有名なフェネスさんといえば、やはり2000年に発表された大傑作アルバム『Endless Summer』の存在は欠かせませんね。
タイトルから想起されるようなノスタルジックな景色が目に浮かぶような、あまりにも美しいフォーキーなエレクトロニカは多くのアーティストたちに影響を与え、2000年代に盛り上がりを見せた美メロ重視のエレクトロニカ、フォークトロニカの先陣を切ったエポックメイキング的な作品としてまさに永遠となった1枚です。
同時に、単にメロディが美しいエレクトロニカというだけではなく、本作は実験的かつ先鋭的な電子音楽の名盤を多くリリースしているオーストリアの名門レーベル、Megoからリリースされた代物であり、ちりばめられたグリッチ・ノイズなどの要素も多く含まれることから、レコード・ショップなどでノイズ~アバンギャルドのコーナーに置かれている場合もあるのです。
広義の意味でのノイズ・ミュージックの発展形として、本作のようなアルバムが存在していることも、ぜひ知っていただきたいところです。