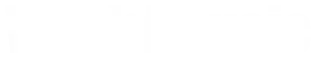ポルカの名曲。おすすめの人気曲
素朴で親しみやすいメロディと、速いテンポで思わず体を動かしたくなってしまうようなチェコ民謡の「ポルカ」という音楽ジャンルを皆さまはご存じでしょうか。
ジャンルの名前を知らずとも、実際にポルカの有名な曲を聴けばピンとくる方も多いはず。
日本では子供向けに『みんなのうた』で紹介されたこともありますし、変わったところで言えば、2000年代にフラッシュ・アニメーションや初音ミクが歌唱したことによって有名になったポルカの曲もあるのですよ。
本稿はそんな楽しい「ポルカ」の名曲たちをまとめた記事となっていますから、ぜひお子さまと一緒にお楽しみくださいね!
- 【クラシック】ワルツの名曲。おすすめの人気曲
- 【アイルランド民謡】意外と身近な民族音楽の名曲・定番曲
- ケルト音楽の名曲。おすすめのアイリッシュ音楽
- 誰でも知ってる洋楽。どこかで聴いたことがある名曲まとめ
- 【タンゴ】タンゴの名曲。おすすめの人気曲
- 【懐かしのコレクション】オールディーズの名曲。おすすめの人気曲
- 【讃美歌】有名な賛美歌・聖歌。おすすめの讃美歌・聖歌
- 【全部オシャレ!】フランスのポピュラーな音楽
- 有名なドイツ民謡|日本のアノ曲がドイツ民謡だった!?
- カフェミュージックにも!ミュゼットの魅力を味わう名曲紹介
- ファドの名曲。おすすめの人気曲
- おすすめのラテンミュージック|ハイセンスな名曲を紹介
- 【洋楽】女性アーティストのアップテンポで可愛い曲
ポルカの名曲。おすすめの人気曲(11〜20)
トリッチ・トラッチ・ポルカ

運動会でよく使われるポルカの名曲で1度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
トラッチとはドイツ語でうわさを意味し、トリッチ・トラッチと並べることで音遊び感覚になり、街角のうわさやおしゃべりを表現しているそうです。
当時、トリッチ・トラッチという有名人のうわさを掲載した現在でいう週刊誌のような雑誌があったとか。
軽快でゴージャスな音とリズムが特徴的ですよね!
運動会の選曲にはもちろん、初めてポルカを聴く人にもオススメの楽曲です。
鍛冶屋のポルカ

ヨーゼフ・シュトラウスが作曲したフランス風ポルカ。
板金などで加工する加熱した金属をのせる鉄製の作業台である金床を楽器として使っているのも面白いですよね!
金庫メーカーの舞踏会と花火大会用に作曲を依頼されたヨーゼフが、金庫を製造した鍛冶職人たちを称賛するため、金床を使用したポルカを手がけたそうです。
この曲は小学生の鑑賞共通教材として採用されているので、聴いたことがある人もいるかもしれません。
金床のチーンという音色がなんともいえずユーモラスで曲のアクセントと言えますね!
はたけのポルカ

保育園や幼稚園などでも人気の『はたけのポルカ』。
ポーランド民謡を原曲としていますが詳細は不明だそうです。
幼児のリズム表現としての遊びに最適な楽曲。
畑にたくさんの作物を植えていくのですが、せっかく植えた野菜をひつじやこぶたやにわとりに食べられてしまいます!
その後ひつじやこぶたは捕獲されますが、何もおとがめなく畑で一緒にポルカを踊ってしまうというなんとも平和なひとときを描いている楽曲です。
小さいお子さんでも楽しく聴けますね!
ホップ・スコッチ・ポルカ

ホップ・スコッチとは英語圏の子供たちに人気の伝統的な遊びのこと。
地面にマス目を書き、片足飛びで遊ぶゲームだそうです。
日本へも明治以降に伝わっており、昭和40年代頃まで石けりとして大人気になりました!
ゲーム要素はなくなりましたがけんけんぱは今でも子供たちの間で行われていますよね。
そんなホップ・スコッチをイメージしたポルカはレトロな雰囲気でポコポコした効果音が楽しい1曲!
お子さんと一緒にけんけんぱをして遊びながら聴いてもいいですね。
シャンペン・ポルカ

ヨハン・シュトラウス2世が作曲したポルカで『シャンパン・ポルカ』とも呼ばれています。
彼は毎年夏の時期にロシアの首都であるサンクトペテルブルクに演奏旅行に出かけていたそうで、この曲はその旅行中に短期間で作曲されたそうです。
短期間とは思えないこだわった構成とユーモラスな味わいのある楽曲ですよね!
曲中にはシャンペンを開ける音が入る演出も印象的です。
演奏されることが少ない楽曲だそうですが、聴覚的にも面白味のある楽曲なので、お子さんと聴いても盛り上がれそう!
オススメのポルカです。
ピチカート・ポルカ

ヨハン・シュトラウス2世とヨーゼフ・シュトラウスの兄弟で手がけた合作ポルカ。
兄弟2人でロシア旅行に出かけた際にピアノの連弾をしたことがきっかけで誕生した楽曲だそうです。
タイトル通り弦楽器のピチカート=弦を指ではじく演奏技法のみで構成されていて、ユーモラスな雰囲気あふれるポルカです。
大人である兄弟が子どものような遊び心で作った名曲をぜひ聴いてみませんか。
お子さんも大人も一緒に子どもに戻って楽しめるポルカです!
ポルカの名曲。おすすめの人気曲(21〜30)
ビア樽ポルカ

「ビア樽ポルカ(Beer Barrel Polka)」は、チェコの作曲家、ヤロミール・ヴェイヴォダ(Jaromír Vejvoda)の作品として知られています。
英語歌詞の出版を機に「ビア樽ポルカ」として広まったそうです。
晴海客船ターミナルでの東京消防庁音楽隊の演奏です。