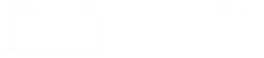Jean-Philippe Rameauの人気曲ランキング【2025】
機能和声法と調性を初めて体系的に理論化した音楽理論家として知られるフランスの作曲家、ジャン=フィリップ・ラモーさん。
クレルモン大聖堂、ディジョン、リヨンなどでオルガニストを務めた経歴を持ちますが、元々は法学を学んでいたことでも知られています。
フランス王室作曲家の称号を獲得するという経歴からも、その多才さや活躍ぶりが分かりますよね。
今回は、そんなジャン=フィリップ・ラモーさんの人気曲ランキングをご紹介します!
- François Couperinの人気曲ランキング【2025】
- ジャン=フィリップ・ラモーの名曲。人気のクラシック音楽
- 【名作クラシック】涙が出るほど美しい珠玉の名曲を一挙紹介
- Olivier Messiaenの人気曲ランキング【2025】
- 【フランソワ・クープラン】クラヴサンを愛した作曲家の名曲、人気曲を紹介
- Jacques Ibertの人気曲ランキング【2025】
- Francis Poulencの人気曲ランキング【2025】
- Gabriel Fauréの人気曲ランキング【2025】
- Georg Friedrich Händelの人気曲ランキング【2025】
- César Franckの人気曲ランキング【2025】
Jean-Philippe Rameauの人気曲ランキング【2025】(41〜45)
新クラヴサン組曲集 第1番(第4組曲)第5曲「小さなファンファーレ」Jean-Philippe Rameau41位

フランスのバロック音楽を代表する作曲家ジャン=フィリップ・ラモー。
彼は幼少期から音楽教育を受け、オペラやクラヴサンのための作品を数多く遺しました。
『新クラヴサン組曲集 第1番』の第5曲は、『小さなファンファーレ』という愛らしいタイトルが付けられた1曲。
ファンファーレを思わせる音型から始まりつつも、すぐに優しいフレーズへと移り変わるこの曲は、おしゃべり好きな女の子を表現しているともいわれています。
重厚な和音が続かず、荘重さよりも軽快さに満ちた本作は、ピアノ学習者がバロック音楽の入り口として取り組むのにピッタリの1曲といえるでしょう。
新クラヴサン組曲集 第1番(第4組曲)第7曲「ガヴォットと6つの変奏」Jean-Philippe Rameau42位

フランスのバロック時代に活躍した作曲家ジャン=フィリップ・ラモーは、クラヴサンのための数多くの作品を遺したことで知られています。
『ガヴォットと6つの変奏』は、そんな彼の代表的な作品集『新クラヴサン組曲集 第1番』に収められた1曲。
ガヴォットのリズムに基づいた主題と6つの変奏で構成される本作は、繊細かつ精巧な装飾音符が施された旋律が特徴的で、各変奏ごとに異なる情感や技術が要求されるのも魅力です。
バロック音楽に興味のある方や、クラヴサンやピアノの演奏技術を磨きたい方にぜひオススメしたい作品です。
新クラヴサン組曲集 第2番(第5組曲)第5曲「雌鶏」Jean-Philippe Rameau43位

フランスのバロック時代を代表する作曲家ジャン=フィリップ・ラモーは、クラヴサンのための作品で名高い作曲家で、40歳を過ぎてから発表した音楽理論書『音楽調和論』は、音楽界に大きな影響力を与えました。
そんな彼が手掛けた『新クラヴサン組曲集 第2番』に収録されているキュートなタイトルでおなじみの『雌鶏』は、は雌鶏の鳴き声や動きを音で巧みに表現したユーモアあふれる1曲。
バロック音楽の演奏法を学びたい方や、動物や自然に関する作品に興味のある方にオススメです。
新クラヴサン組曲集 第2番(第5組曲)第7曲「未開人」Jean-Philippe Rameau44位

バロック音楽の巨匠ジャン=フィリップ・ラモーが遺したクラヴサンのための作品のなかでも、現代のピアニストに愛されているのが『新クラヴサン組曲集 第2番』に含まれる1曲『未開人』。
この曲には当時のヨーロッパで興味を持たれていた異国情緒が反映され、ときに荒々しく原始的な感覚を音楽的に表現しています。
リズミックな特徴が顕著なこの曲は、バロック音楽の特徴を示しつつ、ラモーの音楽的探求心や社会的・文化的な動向が色濃く反映されている点が魅力的です。
新クラヴサン組曲集 第2番(第5組曲)第9曲「エジプトの女」Jean-Philippe Rameau45位

バロックの巨匠ジャン=フィリップ・ラモーの鍵盤楽器のための楽曲は、当時のフランス音楽界において重要な位置を占めていたと伝えられており、その作曲技法や音楽的想像力は現代のピアニストにも大きな影響を与えています。
『新クラヴサン組曲集 第2番』に収められた『エジプトの女』は、エキゾチックな題材を扱った当時としては珍しい作品で、複雑な和声構造やリズムの活気など、ラモーの革新的なアプローチが随所に感じられます。
バロック音楽への造詣を深めたい方や、鍵盤楽器の表現力を追求したい方にぜひオススメしたい1曲です。