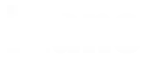【初級~中級向け】ピアノで弾くシューベルトのおすすめ曲
31年という短い生涯の中で膨大な作品を残し、初期ロマン派の代表的な作曲家であるフランツ・シューベルト。
『野ばら』や『魔王』といった教科書に載っているような歌曲、『4つの即興曲』や『楽興の時』といったピアノ曲、交響曲第7番『未完成』などさまざまな分野で音楽史に残る名曲を生み出したことはここで語るまでもないですよね。
こちらの記事ではシューベルトの数ある名曲の中でも、比較的ピアノを弾く上で難易度が低めの楽曲をピアノ曲はもちろんピアノアレンジで弾ける歌曲なども含めてまとめています。
有名なソナタなどは難しくて手が出せない、という初心者から中級者のピアニストの皆さま、まずはここからシューベルトの世界に触れてみてください!
- 【中級レベル】ピアノで弾けるかっこいい曲【発表会にもおすすめ】
- 【初級~中級】難易度が低めなショパンの作品。おすすめのショパンの作品
- 【ピアノ名曲】難しそうで意外と簡単!?発表会にもオススメの作品を厳選
- 【難易度低め】今すぐ弾ける!シューマンのピアノ作品を一挙に紹介
- 【中級レベル】華やかな旋律が印象的なピアノの名曲を厳選!
- ブラームスのピアノ曲|難易度低め&挑戦しやすい作品を厳選!
- 【大人向け】ピアノ発表会にオススメ!聴き映えする名曲を厳選
- 【中級者向け】挑戦!ピアノ発表会で聴き映えするおすすめの名曲
- 【小学生向け】ピアノ発表会で聴き映えする華やかな名曲たち
- 【難易度低め】易しく弾けるメンデルスゾーンのピアノ曲。おすすめのピアノ曲
- 【ベートーヴェン】ピアノで簡単に弾ける珠玉の名曲をピックアップ
- 【難易度低め】聴いた印象ほど難しくない!?ドビュッシーのピアノ曲
- 【初級編】発表会で弾きたいおすすめのピアノ曲まとめ
【初級~中級向け】ピアノで弾くシューベルトのおすすめ曲(1〜10)
即興曲集 第3番 変ロ長調 ,D935,Op.142Franz Schubert

19世紀初期のオーストリアを代表するフランツ・シューベルトの作品をご紹介します。
1827年に作曲されたこの曲は、主題と5つの変奏から構成される変奏曲形式で書かれています。
同じくシューベルト自らの作品の劇付随音楽からの引用を含む親しみやすい旋律が特徴的です。
各変奏では、付点リズムや装飾音、三連符などさまざまな技法が用いられ、ウィーン古典派の技巧とロマン派の叙情性が見事に融合しています。
シューベルトの作曲したピアノ曲の中では最も評価が高く、聴く機会も多いのがこの即興曲です。
ピアノを学び始めた方から中級者の方まで、シューベルトの世界に触れたい方におすすめの1曲です。
日本では東京電力のCMなどでも使用されているので、弾きながらこの曲だ!
と思う方もいらっしゃるかもしれませんね。
『12のワルツ、17のレントラーと9つのエコセーズ D145 Op.18』より「ワルツ 第6番」Franz Schubert

フランツ・シューベルトの作品の中でも、ピアノ初級者が挑戦しやすい作品とされている『12のワルツ、17のレントラーと9つのエコセーズ D145 Op.18より ワルツ第6番』。
終始ゆったりとしたワルツのリズムのまま、短調と長調が交互に変化しつつ、再び穏やかな長調に落ち着きます。
左手の伴奏が跳躍しているため、ペダルを上手に使ってなめらかに仕上げることが大切です!
「ペダル使いにまだ慣れてない」という方は、左手とペダルで練習してから、右手のメロディーを加えてみてくださいね!
4つの即興曲 D935 Op.142 第2番Franz Schubert

シューベルトのピアノ曲と言えば、こちらの『4つの即興曲 D935 Op.142』を思い浮かべる方も多いのではないのでしょうか。
ジャズのようにむしろ即興こそが本質的な音楽と比べて、クラシック音楽は譜面通りに弾くというイメージがありますし知らない方にとっては意外だと感じられるかもしれませんね。
タイトル通り型にとらわれない、晩年のシューベルトの自由な発想で作曲されましたが、実質的な「ピアノソナタ」と見なされて現代では4曲を1つの作品として演奏されるケースが多いそうです。
技術的な面で言えば中級の上、もしくは上級のレベルの技術が必要とされる中で、唯一「第2番」は他の3作品と比べると難易度が低めで、とにかくシューベルトの即興曲を弾いてみたいという方であれば、まずはこちらから挑戦してみるのがいいかもしれません。
メヌエット風の楽曲で4分の3拍子のリズムをしっかりと感じつつ、中間部の軽やかな三連符のアルペジオも優美に弾きこなせるように繰り返し練習してみましょう!
【初級~中級向け】ピアノで弾くシューベルトのおすすめ曲(11〜20)
野ばらFranz Schubert

『野ばら』は、ドイツの詩人ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテの詩に、フランツ・シューベルトが曲をつけて歌曲にした作品。
日本でもよく知られており、学校のチャイムや電車の発車メロディーに使用されています。
「わらべは見たり」で始まる日本語の歌詞で歌ったことのある方も、多いのではないでしょうか?
もとの歌曲がとてもシンプルなメロディーのため、ピアノでも演奏しやすい作品です。
野に咲く野ばらのかわいらしさをイメージしながら、やさしく弾いていきましょう。
スケルツォ 変ロ長調 D.593Franz Schubert

シューベルトが軽やかなワルツのリズムが心地良い『2つのスケルツォ』を作曲したのは1817年のこと。
彼の人生の中では、創作という意味ではそれほど特筆すべき年ではないとされており、本作も出版されたのはシューベルトが亡くなってからずっと後の1871年なのですね。
本稿で紹介しているのは第1曲で、踊るような右手のアルペジオが特徴的ながら高度な演奏技術を要求されるわけではなく、ある程度ピアノに慣れてきた初心者の方であっても十分弾いていただける楽曲と言えるでしょう。
「アルバムの綴り」 D.844 ト長調Franz Schubert

シューベルトは気の置けない友人たちの前でピアノを演奏して、その中からさまざまな舞曲などが生まれたという話は今回の記事でも何度か説明していますが、そういった集まりは「シューベルティアーデ」と呼ばれていたそうです。
こちらの『「アルバムの綴り」D.844 ト長調』は「シューベルティアーデ」時期の最後の方、シューベルトの作品が世間に認められた頃の1825年頃に作曲された作品。
1分半にも満たない短い曲なのですが、静謐な雰囲気で軽やかなアルペジオも登場しませんし、地味に感じるかもしれません。
しかし、こういう曲の雰囲気を引き出せればピアニストの表現力も向上すると言えましょう。
シューベルトの子守歌Franz Schubert

世界でもっとも有名な子守歌といっても過言ではない、フランツ・シューベルト作曲の『シューベルトの子守歌』。
穏やかで心地よいメロディーが眠気を誘う、とてもシンプルで美しい作品です。
「母の手の中でお眠りなさい」と語りかける歌詞とピッタリ合う、やさしく素朴な歌詞が印象的ですよね。
子守歌を演奏するときは、とにかく音の美しさが大切!
ピアノで弾く際も、丸みのある音でやさしく弾くことに意識を向け、心を落ち着かせて演奏しましょう。