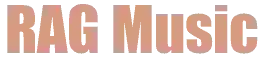街中を彩るデコレーションにキラキラのイルミネーション……思わずワクワクしていますクリスマスですが、もともとはイエス・キリストの降誕を祝う神聖な日。
ヨーロッパではミサに参加し、家族でゆっくり過ごすのが一般的だそうです。
そんなクリスマスには、古くからたくさんの曲が作られてきました。
そもそもクラシック音楽の始まりは教会音楽だったことを思えば、どの曲もふさわしいと言えるのかもしれませんが、今回はとくにおすすめの曲を集めました。
華やかなパーティ向けではありませんが、厳かなヨーロッパの聖夜に思いをはせてみるのもステキだと思いませんか?
- 【名作クラシック】涙が出るほど美しい珠玉の名曲を一挙紹介
- 【高齢者向け】心に響くクリスマスソング。定番ソングや童謡など人気曲まとめ
- クリスマスに聴きたいディズニーソング。ホリデーシーズンを彩る名曲集
- 子供に聴いてほしい!オススメのクリスマスソング&童謡
- 【2026】サンタクロースの歌。クリスマスに聴きたいサンタの名曲まとめ
- クリスマスの投稿にオススメ!インスタのリールに使える曲
- YouTubeショートで人気のクリスマスソングを一挙紹介!
- 【クリスマスのラブソング】聖なる夜に聴きたい恋愛ソング
- 【80代のこころに響く】クリスマスソングの名曲集
- 【90代高齢者向け】オススメのクリスマスソング。懐かしい唱歌や讃美歌、定番ソングまで
- 【バイオリン】時代を越えて愛され続けるクラシックの名曲・人気曲を厳選
- 【クリスマスのうた】こどもと歌いたいクリスマスソング
- 【クリスマスソング】インスタのストーリーにオススメの曲
【クリスマス】クリスマスに聴きたいクラシック音楽。おすすめの神聖なるクリスマスソング(1〜10)
もろびとこぞりてLowell Mason

クリスマスの賛美歌の代表曲として世界中で愛されている作品。
日本では1923年に讃美歌の歌集に収録され、以来100年以上にわたって教会や合唱の定番として、さらにはクリスマスソングとしても親しまれてきました。
冒頭の音型がヘンデルのオラトリオ『メサイア』と共通しており、明朗で躍動感あふれる旋律がキリストの降臨を祝う喜びを力強く表現しています。
クリスマスの夜を神聖な雰囲気のなかで過ごしたいとき、耳を傾けてみてはかがでしょうか。
We Wish You a Merry Christmas

イギリス西部の伝統的なクリスマスキャロルとして16世紀から17世紀に生まれたとされる本作。
裕福な家庭を訪ねてお菓子やごちそうをねだる歌い歩きの習慣から生まれました。
合唱曲集への収録やさまざまなアーティストによるカバーが行われ、今では世界中で親しまれています。
明るく軽快なメロディと歌いやすい反復構造が魅力で、クリスマスの祝祭気分を盛り上げてくれますよ。
家族や友人と一緒に歌ったり、クリスマスパーティーのBGM として流すのもオススメです。
讃美歌第312番「いつくしみ深き」Charles C. Converse

友なるイエスへの信頼を歌う歌として、世界中で愛されてきた作品です。
祈りのなかですべてを神にゆだねる安らぎと、いつくしみ深い友としてのキリストの存在が、シンプルながら心に響く調べとともに表現されています。
賛美歌集に収録され、礼拝や結婚式など静かな祈りの場で長く歌い継がれてきました。
日本では王道のクリスマスソングとしても親しまれていますね。
華やかなパーティだけでなく、静寂のなか神聖な聖夜の意味を見つめ直したいときにも最適な1曲です。
讃美歌第115番「ああベツレヘムよ」Lewis Redner

心を落ち着かせてくれる、美しい聖夜の歌。
聖地ベツレヘムの町が静かに眠る夜、暗い路地に永遠の光が差す情景を描いた歌詞は、まさに救い主の誕生という希望を静ひつに伝えています。
子供たちのために書かれた平易な旋律ですが、深い祈りと感謝が込められた本作は、ひぎやかなパーティーよりも、静かにしっとりと過ごす聖夜にピッタリ。
ろうそくの火をともし、気心知れた人々と穏やかに過ごすクリスマスの夜に聴いてみてはいかがでしょうか。
くるみ割り人形「トレパーク」Pyotr Tchaikovsky

チャイコフスキーのバレエ音楽『くるみ割り人形』から、ロシアの民族舞踊を題材にした躍動感あふれる楽曲です。
1892年12月にサンクトペテルブルクで初演されたバレエの第二幕で演奏されるこの曲は、急速なテンポと跳躍するようなリズムが印象的で、コサックダンスを思わせる活気に満ちています。
ディズニー映画『ファンタジア』やゲーム音楽にも引用されるなど、クラシックの枠を超えて親しまれてきました。
お菓子の国のにぎやかな情景を描いた明るさが、楽しいホリデー気分を盛り上げてくれますよ。
Agnus DeiSamuel Barber

静ひつな祈りの音楽として知られるサミュエル・バーバーさんの合唱作品は、クリスマスの神聖な雰囲気を味わうのにふさわしい1曲です。
もともとは弦楽のための器楽作品として1936年に作曲され、1938年に弦楽合奏版として世に出ましたが、1967年に作曲家自身の手によって混声四部合唱へと編曲されました。
ラテン語の典礼文が静かに歌われる本作は、ピアニッシモの穏やかな響きから始まり、波のように広がる旋律が祈りの言葉を運んでいきます。
クライマックスでは全声部がフォルテシモで高揚し、やがて静寂へと戻る構成は、まさに神への祈りそのもの。
家族と静かに過ごすクリスマスを心に描きながら聴くのがオススメです。
Rocking Carol

チェコに伝わる子守歌を起源としたクリスマスキャロルです。
揺りかごで幼子イエスをやさしくゆらす情景が描かれ、母性的ないつくしみにあふれた歌詞が魅力的。
教会や合唱団のレパートリーとして長く歌い継がれています。
1960年代にはジュリー・アンドリュースさんが録音したことで再び注目を集めました。
穏やかで温かな旋律は、静かな聖夜を過ごしたい方や、合唱でクリスマスを祝いたい方にピッタリ。
厳かな雰囲気を演出してくれる1曲です。