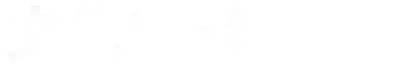文化祭で脱出ゲームをしたい!リアル脱出ゲームの作り方とコツ
文化祭の出し物として「リアル脱出ゲームを作りたい」と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
鍵のかかった部屋から脱出することを目指してさまざな謎解きをしていくゲームで、もともとはパソコンゲームから始まりました。
最近では実際に自分たちが閉じ込められて脱出するという、リアル脱出ゲームが話題になっています。
文化祭の出し物としてこれを実現できれば大きな話題になることまちがいなしですが、どうやって作るのかわからない方が多いはず。
そこでこの記事では、脱出ゲームの作り方や完成度を上げるコツを紹介していきますね!
- 【文化祭・学園祭】謎解きゲームの作り方やコツ
- 【文化祭・学園祭の出し物に】迷路のオススメのアイデア・トラップ
- 【文化祭・学園祭】教室でできる珍しい出し物
- 【文化祭】ジェットコースターを作ろう!
- 【文化祭】お化け屋敷に取り入れたい仕掛けのアイデア
- 【小学生】お宝発見!手作りで楽しむ謎解き宝探しのアイデア集
- 【文化祭】出し物の人気ネタランキング
- 映える!文化祭を彩る内装の装飾アイデア
- 【文化祭】手作りコーヒーカップのアイデア
- 【高校生向け】文化祭でオススメの出し物まとめ
- テーマパーク顔負け!文化祭・学園祭にオススメのアトラクション
- 高校の文化祭でインスタ映えするアイデア。喜ばれるフォトスポット
- 【火を使わない】調理なしで提供できる文化祭の模擬店メニュー
問題の作り方とコツ(1〜10)
問題作りは「答え×法則」
問題は既存の謎解き問題集などを参考にしてもいいですが、せっかく文化祭で脱出ゲームを作るのであれば、問題も自分たちで考えたいですよね。
そんなときに役に立つ謎解き問題の考え方のコツが、「答えとそこにたどり着くための法則を考える」というもの。
たとえば、答えが「梅」、法則は「カタカナを漢字に変換する」であれば、「菅原道真が愛したサイヒは?」という問題が出来上がります。
これは「サイヒ」を漢字に変換して「花」となるため、答えの「梅」が導き出されます。
このように、答えにしたい言葉と問題を解く法則の2つの視点で考えるとさまざまな問題が作れるでしょう。
謎解きのバリエーション(1〜10)
問題の作り方のコツをお伝えした後には、実際に使える解答の法則や問題形式など、謎解きのバリエーションを紹介していきますね。
さまざまな形式の問題やアイデアを取り入れることで、ゲーム全体のマンネリ化を防ぎ、最後までプレイヤーに楽しんでもらえるようになるはずです。
変換問題
問題を解くためのもっともメジャーな法則の一つは、「問題の作り方とコツ」の見出しでも紹介した変換系でしょう。
漢字をカタカナに変換したり、数字やアルファベットをほかの読み方にしたり、イラストから別の言葉を連想させたりなど、お題から何か別のものに変換するものはよく見かけますよね。
日頃からアンテナを張り巡らせておくことで、「〇〇は△△とも読めるぞ」など変換できる言葉に気付けるようになるかもしれません。
日頃からそうしたアイデアを集めておけば、より凝った変換が思いつくかもしれませんね。
例を使った問題
これも謎解き問題でよく見かけるもので、「12は赤、56は那覇、では876は?」といったように、先に例をいくつか出したあとにそこから法則を見つけ出して答えるというものです。
このタイプの問題を解くためには、よく観察していろいろな仮説を試すことが必要になります。
プレイヤーはついつい没頭して問題に取り組んでくれるはず。
このタイプの問題を作るには、謎解きクイズの問題集などを参考にしてみるといいでしょう。
ちなみに例に挙げた問題はガラケーの文字入力方法にちなんでいて、1はあ行、2はか行を意味しています。
そのため「876」は「ヤマハ」となります。
ジグソーパズル
脱出ゲームで解いてもらう謎解き問題はクイズだけではありません。
実際に手を動かして完成させるジグソーパズルを使うのもオススメのアイデアです。
そこでオススメしたいのが、パズルを完成させると次の謎解きの手がかりが出てくる、という仕掛け。
準備としては、絵柄が書かれていない真っ白なジグソーパズルを完成させ、そこに次の謎解きの手がかりを書いておきましょう。
あとは脱出ゲームの本番でプレイヤーにそのパズルを解いてもらいます。
慣れ親しんだジグソーパズルパズルを使ったアイデアですが、手軽に謎解き感が演出できるのでぜひ取り入れてみてくださいね。
クロスワード
クロスワードもジグソーパズルと同じく、脱出ゲームの問題のマンネリ化を防ぐためにオススメのアイデアです。
クロスワードを完成させて出てくる言葉が、次の段階に進むための手がかりだったり、重要なアイテムが入った箱の鍵のパスワードになっているなど、工夫次第でさまざまな展開にアレンジできるのもオススメの理由です。
あまり複雑なものにすると時間がかかりすぎてしまうので、短時間で解けるようにしておくといいでしょう。
ゲームの完成度を上げるために(1〜10)
ここまでストーリー作りのコツ、問題の作り方や謎解きのバリエーションなどを紹介しました。
これらを踏まえて脱出ゲーム作りをすれば、きっとじっくり取り組めるゲームができたはずです。
そこで、最後に出来上がったゲームの完成度をさらに上げるコツを紹介していきますね。
ぜひこれから紹介するコツを取り入れてゲームをさらに磨き上げてください。
デモプレイしてもらう
脱出ゲームが一通り出来上がったら必ずやってもらいたいのが、テストプレイです。
ゲーム制作に関わっていない複数の人に何度か試しにプレイしてもらい、全体の難易度が適切かどうか、時間はどれくらいかかるのか、もっとおもしろくなる改善点はないかなど、さまざまな意見を聞いて改善していきましょう!
テストプレイに時間をかけられない、テストプレイする人員が不足しているなど、十分にテストプレイができない場合もあるかもしれませんが、不測の事態が起きないように最低でも1度はおこなうようにしましょう。
謎解きや脱出ゲームを実際に解いてみる
この記事では、主にストーリーと問題の作り方のコツに焦点を当てて紹介してきましたが、それでも「なかなかいいアイデアが思い浮かばない」という方も少なくないと思います。
そんな方は、ぜひいくつかの脱出ゲームをプレイしてみたり、謎解きクイズを解いてみたりしてください。
実際にご自身でそういった体験をすることで参考になるアイデアに出会えたり、謎解きクイズの考え方がわかるようになったりするはず!
「困ったときは自分がプレイヤーになってみる」というのを心のどこかに留めておいてください。
ゲームで使いたいアイテムアイデア(1〜10)
最後に脱出ゲーム内で使いたい小道具のアイデアを紹介します。
脱出の鍵となる仕掛けやキーアイテムの隠し場所などのアイデアにお役立てください。