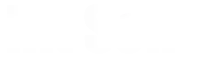昭和初期の春の歌。春を感じる歌謡曲や唱歌まとめ
あなたは「春」と聞いて、どんな歌を思い浮かべますか?
戦前から戦後にかけての昭和初期には、季節の移ろいを繊細に描いた流行歌や唱歌、童謡が数多く生まれました。
本特集では、そんな時代の春にまつわる歌謡曲や唱歌をたっぷりとお届けします。
リンク先の音源動画資料には当時のオリジナル音源を選んでいる曲もありますから、レトロな響きとともに当時の春の空気を味わってみてください。
懐かしいメロディーを口ずさみながら、穏やかな春のひとときをお楽しみいただければ幸いです。
- 【昭和に生まれた春の歌】時代を彩った歌謡曲&今も歌い継がれる名曲を厳選
- 【高齢者向け】口ずさみたくなる春の歌。懐かしい名曲で季節を感じよう
- 【高齢者向け】4月に歌いたい春の名曲。懐かしい童謡や歌謡曲で心ほぐれるひととき
- 【高齢者向け】90代の方にオススメの春の歌。昭和の春曲まとめ
- 春に歌いたい童謡。子供と一緒に歌いたくなる名曲集
- 【春の歌】うららかな春に聴きたい定番ソング・最新ヒット曲集
- 【春うた】4月に聴きたい名曲。四月を彩る定番曲
- 春に聴きたい感動ソング。春の名曲、人気曲
- 【2026】じっくり聴きたい演歌の春歌。日本の春を感じる演歌の名曲まとめ
- 春うたメドレー。春に聴きたい名曲ベスト
- 昭和歌謡の名曲まとめ。時代を超えて愛される楽曲を一挙に紹介
- 【春うた】3月に聴きたい仲春の名曲。春ソング
- 【2026】聴くだけで思い出にタイムスリップ!50代におすすめの春ソング
昭和初期の春の歌。春を感じる歌謡曲や唱歌まとめ(1〜10)
祇園小唄NEW!作詞:長田幹彦 / 作曲:佐々紅華

京都の風情ある花街を舞台に、四季折々の情景と舞妓の恋心を情緒たっぷりに描いたのがこの楽曲です。
昭和5年に公開された映画『祇園小唄絵日傘』の主題歌として制作された本作は、長田幹彦さんが作詞を、佐々紅華さんが作曲を担当しており、藤本二三吉さんの艶やかな歌声とともに大ヒットしました。
歌詞には春の「東山」や「おぼろ月」といった美しい言葉が並び、「だらりの帯」というフレーズが印象的な一節は、聴く人の心に京都の風景を鮮やかに映し出します。
実は日本舞踊の演目としても親しまれており、単なる流行歌を超えて花街のお座敷芸としても長く愛され続けているのですね。
あたたかな陽気の中で古都の春を感じたいときや、しっとりとした和の雰囲気に浸りたいときにおすすめしたい名曲です。
街は春風NEW!中野忠晴

春の風が街を吹き抜ける、そんなモダンで軽やかな光景が目に浮かぶような一曲です。
この歌は、1938年5月に発売されたレコードのB面曲として世に出ました。
歌唱を担当したのは、和製ポップスの先駆者とも言える中野忠晴さん。
作曲にはアメリカの著名なアーヴィング・ベルリンの名前があり、編曲を仁木他喜雄さんが手掛けるという、当時の洋楽ジャズを日本の流行歌へ見事に落とし込んだ作品ですね。
実は明確な映画主題歌などの記録は残っていないのですが、その洗練されたメロディはまるで銀幕の世界のようです。
軽快なリズムと中野さんのあざやかな歌声が、新しい季節の訪れに胸を躍らせる人々の心に寄り添います。
お洒落をして街へ出かけたくなる、そんなウキウキとした春の日に聴いてみたいですね。
小夜吹く春風NEW!小夜福子

昭和16年4月、宝塚歌劇団月組の舞踊公演に合わせて発売された本作は、当時の月組組長であり男役スターとして人気を誇った小夜福子さんが歌唱を担当した楽曲です。
作詞と演出を岡田恵吉さんが、作曲を岩河内正幸さんが務め、宝塚管弦楽団の演奏をバックに春の夜の風情を歌い上げる構成は、劇場の空気をそのまま閉じ込めたような華やかさがありますよね。
ちなみに本作は同公演の主題歌として制作されており、レコードのB面には『大やまとの歌』がカップリングされているのも特徴です。
舞台の記憶を蘇らせる記念品として、また家庭で春を楽しむ音楽として親しまれた背景がうかがえます。
小夜福子さんの気品ある歌声に耳を傾け、レトロな春のひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。
昭和初期の春の歌。春を感じる歌謡曲や唱歌まとめ(11〜20)
春風春雨NEW!山口淑子

こきゅうの音色がかもし出す異国情緒と、切ない歌声が印象的な昭和のバラードです。
歌唱を担当したのは、国際的スターとして活躍した山口淑子さん。
1952年、昭和27年公開の映画『上海の女』の挿入歌である本作には、じつは日本語と中国語の2つのバージョンが存在しているのですね。
日本語詞は岩谷時子さん、中国語詞は金人さん、作曲は中民さんが担当しました。
愛する人に抱きしめられたいと願う想いが、春の夜の湿った空気感を描き出しているのです。
映画で歌われた中国語版は、当時香港でSP盤として発売された経緯があり、女優としての山口さんの魅力を象徴する作品と言えるでしょう。
しっとりとした春の雨の夜、静かにもの思いにふけりたい時に聴いてみてほしい1曲ですよね。
梅に春風NEW!新橋喜代三

春の訪れを告げる花として、梅の花を思い浮かべる方もきっと多いのではないでしょうか?
本稿で紹介している『梅に春風』は、1935年1月に発売された流行歌で、昭和初期の空気を色濃く残す1曲です。
歌唱を担当したのは、民謡や小唄で人気を博し、のちに作曲家の中山晋平さんの妻となったことでも知られる新橋喜代三さん。
作詞を時雨音羽さん、作曲を田村しげるさんが手がけた本作は、梅と春風という日本の美しい情景を、新橋喜代三さんの粋な歌声で表現しています。
当時の花柳界やお座敷文化を思わせる軽やかなメロディーは、穏やかな春の日にのんびりと聴きたくなるような魅力がありますよね。
戦前の流行歌ならではのレトロな響きが、懐かしい気分にさせてくれることでしょう。
チューリップNEW!童謡

春の訪れとともに花壇を彩るあの花、誰もが一度は口ずさんだことがある童謡ではないでしょうか。
赤や白、黄色といった鮮やかな色が並んで咲く様子を描き、どの花もそれぞれに美しいと肯定する歌詞は、シンプルながらも深い優しさに満ちていますよね。
実は本作、1932年7月に発行された『絵本唱歌 夏の巻』が初出なのですが、当時は作詞者名が伏せられており、のちに裁判を経て近藤宮子さんが作者として認められたという歴史があるのです。
1933年にはレコード化もされ、以来長きにわたり入園式や春の行事などで親しまれてきました。
小さなお子さんが初めて歌う一曲としてもぴったりですし、懐かしいメロディに耳を傾けて、穏やかな春の陽気を感じてみるのもすてきですね。
江戸は春風NEW!高田浩吉

春風に吹かれて江戸の町を歩くような、そんな粋で軽やかな気分にさせてくれるのが本作ですよね。
昭和29年5月に発売された高田浩吉さんの楽曲であり、松竹映画『黒門町伝七捕物帖』の主題歌としても知られている1曲です。
野村俊夫さんが作詞、万城目正さんが作曲を手掛けた本作ですが、オーケストラの伴奏に三味線の音色が重なることで、時代劇ならではの和洋折衷な魅力が見事に表現されているのが特徴的ですよね。
映画の中で高田さんが演じる伝七の颯爽とした姿が目に浮かぶようで、聴いているだけで胸が踊るという方も多いのではないでしょうか。
春の陽気を感じながら、古き良き江戸の情緒に浸りたい時にはぴったりの名曲です。
ぜひ一度、その独特な世界観を味わってみてほしいですね。