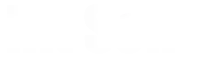昭和初期の春の歌。春を感じる歌謡曲や唱歌まとめ
あなたは「春」と聞いて、どんな歌を思い浮かべますか?
戦前から戦後にかけての昭和初期には、季節の移ろいを繊細に描いた流行歌や唱歌、童謡が数多く生まれました。
本特集では、そんな時代の春にまつわる歌謡曲や唱歌をたっぷりとお届けします。
リンク先の音源動画資料には当時のオリジナル音源を選んでいる曲もありますから、レトロな響きとともに当時の春の空気を味わってみてください。
懐かしいメロディーを口ずさみながら、穏やかな春のひとときをお楽しみいただければ幸いです。
- 【昭和に生まれた春の歌】時代を彩った歌謡曲&今も歌い継がれる名曲を厳選
- 【高齢者向け】口ずさみたくなる春の歌。懐かしい名曲で季節を感じよう
- 【高齢者向け】4月に歌いたい春の名曲。懐かしい童謡や歌謡曲で心ほぐれるひととき
- 【高齢者向け】90代の方にオススメの春の歌。昭和の春曲まとめ
- 春に歌いたい童謡。子供と一緒に歌いたくなる名曲集
- 【春の歌】うららかな春に聴きたい定番ソング・最新ヒット曲集
- 【春うた】4月に聴きたい名曲。四月を彩る定番曲
- 春に聴きたい感動ソング。春の名曲、人気曲
- 【2026】じっくり聴きたい演歌の春歌。日本の春を感じる演歌の名曲まとめ
- 春うたメドレー。春に聴きたい名曲ベスト
- 昭和歌謡の名曲まとめ。時代を超えて愛される楽曲を一挙に紹介
- 【春うた】3月に聴きたい仲春の名曲。春ソング
- 【2026】聴くだけで思い出にタイムスリップ!50代におすすめの春ソング
昭和初期の春の歌。春を感じる歌謡曲や唱歌まとめ(11〜20)
東京の花売り娘岡晴夫

青い柳の芽吹く東京の辻に咲く、一輪の希望を描いた昭和21年の名曲。
岡晴夫さんの温かみのある歌声で紡がれるメロディは、戦後の混乱期にあった人々の心を優しく包み込みました。
柔らかな物腰で花を売る少女の姿を通じて、焦土から立ち上がろうとする東京の姿が浮かび上がります。
佐々詩生さんの詞と上原げんとさんの曲が見事に調和し、寂しさの中にも確かな希望が感じられる珠玉の一曲となっています。
本作は春の訪れとともに新たな一歩を踏み出そうとする人々の心情を、優美に描き出した珠玉の一曲です。
春の陽気とともに心温まるひとときを過ごしたい方にオススメしたい、心に染み入る名曲です。
リンゴの唄並木路子

戦後の日本に希望の光を灯した名曲を、並木路子さんの澄んだ歌声でつづった傑作です。
青い空を見上げながら、無垢な心で愛をうたう優しさに満ちた楽曲は、当時の人々の心に深く響きました。
モノラルの音質で刻まれた音の記憶は、昭和初期の空気感を鮮やかに伝えています。
本作は1945年10月公開の映画『そよかぜ』の主題歌として世に送り出され、翌年1月にレコード化されました。
作詞のサトウハチローさんと作曲の万城目正さんが紡ぎ出した温かなメロディーは、戦後の復興期を生きる人々の心の支えとなりました。
春の訪れを感じながら、懐かしい思い出とともに聴いていただきたい一曲です。
十九の春神楽坂浮子

沖縄民謡として知られる同名の楽曲も存在しますが、本稿で紹介する『十九の春』は昭和31年に「最後の芸者歌手」と呼ばれた神楽坂浮子さんの歌唱で大ヒットした楽曲です。
神楽坂さんにとっては歌手としての出世作でもあり、この曲のヒットがきっかけで一気にスターダムへとのし上がり、女優としても活躍することとなるのですね。
歌詞の内容としては、タイトルにもあるように十九歳の女性が主人公で、おそらく気持ちを言い出せないまま失恋してしまった切ない乙女心を情緒たっぷりに描いています。
何かが始まるだけではなく、何かが終わるのも春の特徴ということを思い出させてくれますね。
早春賦唱歌

春の訪れを待ちわびる心情を描いた楽曲として、吉丸一昌さんと中田章さんにより1913年に制作された本作は、暖かな季節への期待と早春の寒さが見事に表現されています。
ウグイスの歌声や解けゆく氷、芽吹き始めたアシなど、繊細な情景描写により春の息吹を感じられますね。
高齢者の方にもなじみ深い本作は、懐かしい思い出を振り返りながら楽しく歌えるレクリエーションにピッタリですよ。
春の唄月村光子

1937年、昭和12年に発表された『春の唄』は、戦前にラジオを使って国民に向けた健全な歌の普及活動として放送された歌「国民歌謡」の一つとして大ヒットした、昭和初期の代表的な春の曲です。
歌唱を担当したのは、当時は東京音楽学校の教師であり、歌手としてレコードの吹込みを行っていた渡辺光子さん。
『春の唄』を発表した時点では結婚後という背景もあって月村光子名義となっていますが、渡辺さんは多くの芸名を使い分けていた女性歌手としても知られているのですね。
そんな渡辺さんの華やかな歌唱と春の訪れを迎えて楽しそうな町の人々を描いた歌詞が、いつの時代にも何となく浮かれてしまう春という季節の変わらぬ雰囲気を伝えてくれるのです。
花唱歌

春の情景を優しく描いた唱歌の名曲です。
満開の桜や春風に舞う花びらが目に浮かぶような、美しい楽曲。
歌詞には、咲き誇る花々の姿を通して、春の訪れを喜ぶ気持ちが表現されています。
高齢者の方にもなじみ深い曲なので、一緒に口ずさんでみるのはいかがでしょうか。
懐かしい思い出がよみがえり、心が温かくなるはずです。
春の散歩のお供にもぴったり。
季節の移ろいを感じながら、ゆったりと歩くのもすてきですね。
昭和初期の春の歌。春を感じる歌謡曲や唱歌まとめ(21〜30)
憎や春風NEW!藤本二三吉

春の風に吹かれて、ふと誰かを想う……そんな経験はありませんか?
この曲『憎や春風』は、タイトルにある「憎や」という言葉が、憎しみではなく「憎いねえ」「粋だねえ」といった江戸っ子の洒落た感情を表しているのが素敵ですよね。
昭和6年4月にビクターの新譜として発売された本作は、作詞を伊藤深水さん、作曲を斉藤佳三さんが担当しており、当時の「ジャズ流行唄」としてモダンな魅力を放っています。
歌うのは「鶯芸者」として名を馳せた藤本二三吉さんで、その端唄仕込みの美しい節回しと都会的な情緒が融合し、聴く人の心を昭和初期のモダンな春へと誘ってくれます。
春の陽気に誘われて、少しレトロな気分でお酒を嗜みたい時や、粋な大人の恋心に触れたい時にぴったりの1曲ですね。