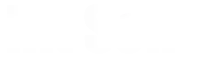昭和初期の春の歌。春を感じる歌謡曲や唱歌まとめ
あなたは「春」と聞いて、どんな歌を思い浮かべますか?
戦前から戦後にかけての昭和初期には、季節の移ろいを繊細に描いた流行歌や唱歌、童謡が数多く生まれました。
本特集では、そんな時代の春にまつわる歌謡曲や唱歌をたっぷりとお届けします。
リンク先の音源動画資料には当時のオリジナル音源を選んでいる曲もありますから、レトロな響きとともに当時の春の空気を味わってみてください。
懐かしいメロディーを口ずさみながら、穏やかな春のひとときをお楽しみいただければ幸いです。
- 【昭和に生まれた春の歌】時代を彩った歌謡曲&今も歌い継がれる名曲を厳選
- 【高齢者向け】口ずさみたくなる春の歌。懐かしい名曲で季節を感じよう
- 【高齢者向け】4月に歌いたい春の名曲。懐かしい童謡や歌謡曲で心ほぐれるひととき
- 【高齢者向け】90代の方にオススメの春の歌。昭和の春曲まとめ
- 春に歌いたい童謡。子供と一緒に歌いたくなる名曲集
- 【春の歌】うららかな春に聴きたい定番ソング・最新ヒット曲集
- 【春うた】4月に聴きたい名曲。四月を彩る定番曲
- 春に聴きたい感動ソング。春の名曲、人気曲
- 【2026】じっくり聴きたい演歌の春歌。日本の春を感じる演歌の名曲まとめ
- 春うたメドレー。春に聴きたい名曲ベスト
- 昭和歌謡の名曲まとめ。時代を超えて愛される楽曲を一挙に紹介
- 【春うた】3月に聴きたい仲春の名曲。春ソング
- 【2026】聴くだけで思い出にタイムスリップ!50代におすすめの春ソング
昭和初期の春の歌。春を感じる歌謡曲や唱歌まとめ(41〜50)
みかんの花咲く丘川田正子

戦後から1年が過ぎた昭和24年の8月25日に発表され、戦後に発表された童謡としては最もヒットした曲と言われるほどの人気を誇るのが『みかんの花咲く丘』です。
みかんと言えば冬の果物というイメージですが、みかんの花が開花する時期は5月ということで、みかんの花に着目したこちらの『みかんの花咲く丘』は、まさに春の童謡なのですね。
音楽雑誌『ミュージック・ライフ』編集長の加藤省吾さんが作詞を務め、作曲は海沼實さんが担当。
歌唱を担ったのは、童謡歌手として絶大的な人気を誇った当時12歳の川田正子さんです。
川田さんが出演するラジオ向けの曲として誕生したのですが、何と楽曲が完成したのは放送が行われる前日だったというのですからすごいですよね。
加藤さんの出身地でもある静岡県には複数の歌碑も存在していますから、この曲のバックグラウンドを深く知りたい方はぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。
微笑がえしキャンディーズ

大切な人との別れを前にした女性の切ない思いを、爽やかな春風のような旋律に乗せて歌い上げたキャンディーズの至高の1曲です。
1978年2月のリリース後、オリコンチャートで1位を獲得し、累計100万枚を超える売り上げを記録しました。
引越しのシーンを通してカップルの別れを描いており、これまでの思い出を振り返る主人公の姿には笑顔の裏に隠された複雑な感情が映し出されています。
春の時期に大切な人との別れを経験した方に聴いていただきたい1曲です。
湖畔の乙女菊池章子

6歳で琵琶の免許皆伝となり、1939年に歌手としてのデビューを果たしたシンガー、菊池章子さん。
1942年11月15日にリリースされたシングル曲『湖畔の乙女』は、映画『湖畔の別れ』の主題歌として大ヒットとなりました。
透明感のある伸びやかなハイトーンボイスと叙情的なメロディーは、古き良き日本の音楽を感じさせられるのではないでしょうか。
日本語の美しさが詰まったリリックにも注目して聴いてほしい、エモーショナルなナンバーです。
アコーデオンの春中野忠晴

中野忠晴さんの『アコーデオンの春』は、昭和初期の歌謡曲の伝統を感じさせる素晴らしい選曲です。
2021年7月28日に発売されたアルバム『音故知新 昭和の名歌手 中野忠晴』にも収録されている本作。
海外の軽音楽風の旋律が特徴で、その牧歌的な雰囲気は、多くの春の日々を通り抜けてきたような趣深さを持っています。
やわらかな春の日差しの下、新しい季節の訪れを感じながらお楽しみいただきたいですね。
春まだ浅く有島通男

26歳の若さで亡くなった明治時代を代表する歌人であり詩人、石川啄木の短編小説『雲は天才である』に登場する歌が使われたこちらの『春まだ浅く』は、昭和11年に公開された映画『情熱の詩人啄木 ふるさと篇』の主題歌として誕生した楽曲です。
作曲は日本を代表する国民的作曲家の古賀政男が務め、歌唱は有馬通男さんによるもの。
実は過去に古賀さんが手掛けた寮歌をアレンジしたものということで、そういった原曲の雰囲気が残っているのも特徴ですね。
春が来た

童謡『春が来た』は、日本の四季の美しさを感じさせる名曲ですね。
山や里、野に春が訪れる様子を、シンプルで親しみやすいメロディと歌詞で表現しています。
花が咲き、鳥が鳴く春の情景が目に浮かぶようです。
明治時代に作られたこの曲は、100年以上にわたり日本の音楽教育や文化行事で親しまれてきました。
春の訪れを喜ぶ気持ちが込められた歌詞は、長い冬を乗り越えた喜びを感じさせてくれます。
懐かしい思い出とともに、春の訪れを感じたいときにぴったりの曲ではないでしょうか。
春よいずこ二葉あき子、藤山一郎

作詞と作曲を西條八十さんと古賀政男さんがそれぞれ務め、二葉あき子と藤山一郎が歌唱を担当という昭和の流行歌におけるゴールデンコンビが昭和15年に発表した楽曲が『春はいずこ』です。
同名の映画が同じく昭和15年に公開されており、その主題歌でもあるというのは当時の流行歌によくあるパターンですよね。
ちなみに作詞と作曲、歌手全員が共通している『なつかしの歌声』という楽曲も同映画の主題歌であり、実はこちらの『春よいずこ』は『なつかしの歌声』のレコードのB面曲として発表されています。
歌詞の内容としてはどちらも映画の内容に沿った感傷的なものという共通点はあるのですが、アップテンポなリズムで明るい曲調の『なつかしの歌声』と比べて『春よいずこ』はメロディも曲調もセンチメンタルで物悲しいというのが特徴です。
興味のある方は、ぜひ2つの曲を聴き比べてみてほしいですね。