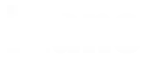【初級】ピアノ発表会にもオススメ!弾けたらかっこいいクラシックの作品
ピアノを弾けるようになりたい方にとって憧れとも言えるクラシックの作品は、ある程度ピアノが弾けるようになってからでないと無理……そんなふうにお考えの方、多いのではないでしょうか。
そんな方にオススメしたい、初心者向けの弾けたらかっこいいクラシック作品をピックアップしてみました!
華やかでダイナミックなピアノ曲はどうしても高度な技術を要求される場合も多いですが、今回紹介しているピアノ曲は初心者でも十分に手の届くレベルで、短いながらもかっこいいフレーズを楽しめる名曲ばかりです。
初心者向けにアレンジされた有名な曲もご紹介しているので、お子さまの発表会曲をお探しの方も、大人になってからピアノを始めた方も、ぜひチェックしてみてくださいね!
- 【小学生向け】ピアノ発表会で聴き映えする華やかな名曲たち
- 【ピアノ発表会向け】簡単なのにかっこいいクラシック作品
- 【初級者向け】やさしい&弾きやすい!ピアノ発表会で聴き映えする曲
- 【初級~中級】難易度が低めなショパンの作品。おすすめのショパンの作品
- 【ピアノ名曲】難しそうで意外と簡単!?発表会にもオススメの作品を厳選
- 【初級編】発表会で弾きたいおすすめのピアノ曲まとめ
- 【初級】大人のピアノ初心者におすすめ! 美しい&おしゃれなピアノ曲
- 【6歳児向け】ピアノ発表会で映えるおすすめ楽曲をピックアップ!
- 【ピアノ発表会】男の子におすすめ!かっこいい&聴き映えする人気曲を厳選
- 【中級レベル】ピアノで弾けるかっこいい曲【発表会にもおすすめ】
- 【クラシック音楽】全曲3分以内!短くてかっこいいピアノ曲まとめ
- 【ピアノ発表会】小学生・中学年におすすめのクラシックの曲を厳選
- 【ピアノ曲】子供でも弾きやすい!簡単なクラシック作品を一挙紹介
【初級】ピアノ発表会にもオススメ!弾けたらかっこいいクラシックの作品(71〜80)
バースデイ・マーチLouis Köhler

多くの子供向けピアノ楽譜に収録されている、初めての発表会にピッタリのかわいらしい作品!
ルイス・ケーラーの『バースデイ・マーチ』は、シンプルで覚えやすい曲ですが、和音のスタッカートやメロディのなめらかなレガートなど、ピアノを学ぶ上で重要な要素が詰まっています。
また、元気な部分とそっと弾く部分など、強弱の変化をたっぷりつけられるのもこの曲の魅力の一つ!
お誕生日のサプライズなどを想像しながら、表情豊かに演奏しましょう。
歓喜の歌Ludwig van Beethoven

年末になると多くの演奏会で取り上げられる、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの名曲『交響曲第9番 ニ短調 Op.125』。
『歓喜の歌』は、この作品の第4楽章で歌われる第一主題を指します。
オーケストラと合唱の演奏では、この上ない喜びを感じさせる華やかさや力強さが魅力的ですが、ピアノで演奏するとメロディラインがより際立ち、流れるような美しさも味わえます。
まずは、「ミミファソソファミレ」と順次進行になっている部分から練習し、メロディが弾けるようになったらベース音を入れて両手奏にもチャレンジしてみましょう!
子供のアルバム 第1集 「少年時代の画集」 第5曲 エチュードAram Khachaturian

リズミカルでスタッカートが効いた独特のメロディーが印象的な本作は、「4分の4拍子」のハ長調で書かれた軽快な一曲です。
右手のスタッカートと左手の半音階的な和音の動きが絶妙なバランスを保ち、わずか1分30秒という短い演奏時間の中に、豊かな表現と情景描写が詰め込まれています。
アルメニアの伝統音楽や舞踊のリズムが巧みに取り入れられており、生き生きとした躍動感があふれる演奏を楽しめます。
1926年に作曲されたこの作品は、リズムの正確さや両手のバランスを養うのに適しており、ピアノ発表会でも人気の高い曲として知られています。
ピアノの基礎的な技術を身につけた方で、表現力が豊かな演奏にチャレンジしたい方におすすめの一曲です。
ワルツ 第15番 Op.39-15「愛のワルツ」Johannes Brahms

15番のなかでも最も有名な作品『ワルツ 第15番 Op.39-15「愛のワルツ」』。
ピアノ発表会などでも頻繁に耳にする楽曲ですね。
そんなこの作品のポイントは、右も左も和音が多い点にあります。
この和音が少しだけ弾きづらいのですが、和音をつかむ練習だと思って取り組んでみるのもよいかもしれません。
とくに37小節目の右手が難しいので、左右を個別に練習することをオススメします!
ラッパ手のセレナードFritz Spindler

活き活きと響き渡るトランペットの音色が魅力的な楽曲です。
3拍子のセレナードでありながら、快活で軽やかな雰囲気に満ちています。
同音連打と軽快なリズムが織りなすメロディーは、明るく華やかな雰囲気を醸し出しており、聴く人の心を躍らせます。
演奏には指の独立性とリズム感が求められますが、技巧的な難しさを感じさせない親しみやすさがあります。
美しく響くスタッカートと、トランペットの音色を彷彿とさせる旋律は、発表会のレパートリーとして素晴らしい魅力を持っています。
優雅なセレナードの世界を表現したい方や、生き生きとした演奏で聴衆を魅了したい方におすすめの作品です。
ブルグミュラー25の練習曲 Op.100 第2番「狩り」Johann Burgmüller

軽やかな流れるような旋律と、「4分の2拍子」のリズミカルな伴奏が美しく調和した作品です。
本作では、イスラム美術の装飾模様をモチーフにした優雅な音の模様が織りなされており、躍動感のある行進曲風の曲調と相まって華やかな雰囲気を演出しています。
右手の16分音符による流麗な旋律と左手のスタッカートによる和音の組み合わせは、まるで光り輝く宝石のような輝きを放っています。
1851年にパリで出版されたこの曲は、やさしい技巧でありながら聴き映えのする魅力的な作品として長年愛され続けています。
皆様も、この華やかで優美な音の世界を堪能してみてはいかがでしょうか。
ソナチネ 第9番 第1楽章Muzio Clementi

明るく華やかで情熱的な響きが魅力のクラシック音楽をお探しの方に、ムーツィオ・クレメンティの軽快な一曲をご紹介します。
1797年に発表されたこの楽曲は、力強く活気に満ちたフレーズから始まり、軽やかなスケールパターンへと展開していきます。
アレグロ(速い)のテンポで奏でられる本作は、軽やかな指さばきとダイナミックな表現力を必要とする構成となっています。
調和のとれた美しい和音とスタッカート(跳ねるような音)の絶妙なバランスが、華やかさと優雅さを見事に演出しています。
メロディーが明快で親しみやすい本作は、ピアノの表現力を存分に味わいたい方や、華やかで生き生きとした楽曲をレパートリーに加えたい方におすすめの一曲です。