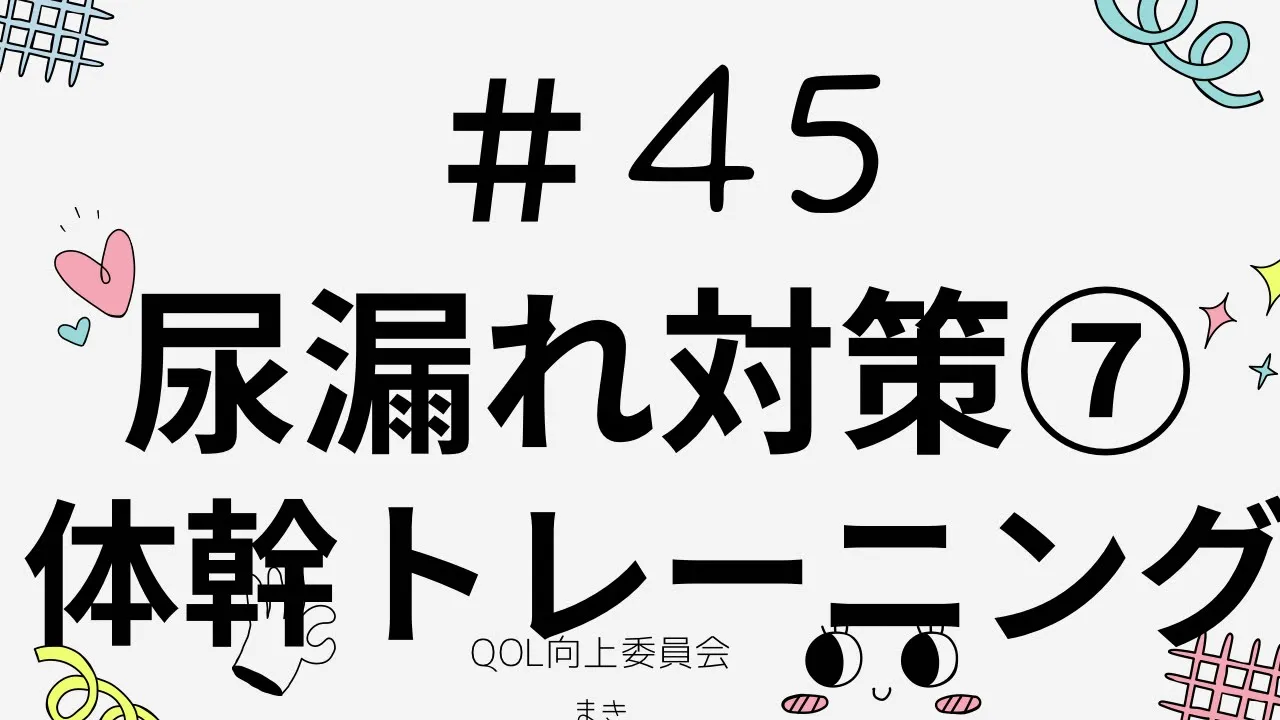【高齢者向け】インナーマッスル鍛え方。転倒予防
インナーマッスルは体の深い部分にある筋肉で、姿勢を支えたりバランスを保ったりする大切な役割を持っています。
特に高齢者の方にとって、インナーマッスルを鍛えることは転倒予防に効果的です。
無理なく続けられる簡単な運動を習慣にすることで、体幹が安定し、歩行もスムーズになりますよ。
今回は、高齢者の方でも安心してできるインナーマッスルの鍛え方を集めました。
毎日の生活に取り入れて、元気に動ける体を目指しましょう。
今日から始められる簡単なエクササイズで、転びにくい体づくりを始めてみましょう。
【高齢者向け】インナーマッスル鍛え方。転倒予防(1〜10)
体幹トレーニング

体幹は意識しないと鍛えるのが難しい部分で、この体幹の衰えが全身の筋力の低下にもつながります。
そんな体幹を意識したトレーニングで、腹横筋や骨盤底筋もあわせて鍛えていこうという内容です。
四つんばいの状態から右手と左足、もしくは左手と右足を伸ばした姿勢を作り、その体勢を維持すれば体幹が鍛えられていきます。
はじめは姿勢の維持が難しいかもしれませんが、まずは短い時間でも正しい姿勢を作ることを意識、徐々に慣らして時間をのばしていくのがポイントですよ。
座位バランス体操

バランス機能を鍛えるなんて高齢者の方にとってはハードルが高く感じる方もいるのではないでしょうか。
そんな方におすすめなのがこちらの座位バランス体操です。
座ってできるので運動が苦手な方でも安心ですよ。
座ってやる運動ですが、姿勢や座り方に気をつけるのがポイント。
骨盤をおこして背筋をしっかり伸ばしておこないましょう。
バランス機能はもちろん、血流が促進されるので心身のリフレッシュ効果もありますよ。
心の健康も意識して取り入れてくださいね。
足腰と体幹のトレーニング

バランスを強化する、体幹と足腰の筋トレをご紹介します。
高齢になると筋力や運動能力は衰え、転倒リスクが増します。
転ばない体をつくるためにはバランス能力の向上と筋力強化が重要ですよ。
立った状態で手足を動かしていきましょう。
立位が不安定な方は台につかまっておこなうか、いすに座った状態でおこなってくださいね。
さまざまな筋トレを紹介されていますので、取り入れやすいものから初めてください。
また高齢者施設のレクリエーションなど大人数でおこなう場合は、一人ひとりの体の状況や体力に合わせて、無理のない範囲でおこなうようにしましょう。
スロートレーニング立位体幹

体幹のスロートレーニングを取り入れて、認知症や寝たきり、転倒予防をしましょう。
立った状態でおじぎをしていきます。
お尻は動かさずそのままの状態で、背筋が丸くならないように注意しましょう。
激しく動くのではなくゆっくりな動作で、体幹に軽い負荷をかけていくことがポイントですよ。
ふらつき予防に、いすの背もたれや壁の前でおこなうようにしてくださいね。
体幹を鍛えることはふらつきを予防し、転倒リスクを軽減します。
また適度な運動は脳を活性化させ認知症予防にも効果的ですよ。
周りの環境を整えたうえで、ぜひチャレンジしてみてくださいね。
足じゃんけん手拍子体操

足でじゃんけんの形を順番に作っていき、その中に手拍子を入れることで順番を複雑にしていこうというゲームです。
じゃんけんの形をどの順番で作るのか、どこに手拍子を入れるのかを切り替えていくことで、脳トレの効果を加えていきます。
しばらくは同じ動きを繰り返して、慣れてきたタイミングで順番を変えていくと、順番にしっかりと意識が向けられますね。
動きだけだと混乱するという場合には、声に出しながら進めていくパターンもわかりやすいのでオススメですよ。
足上げ体操

椅子に座った状態でその前方に箱を配置、そこに足を交互に乗せていくことで、足を上に持ち上げる力を鍛えていこうという体操です。
座った状態で進めていくので、立った状態での踏み台昇降よりも楽に行えるのではないでしょうか。
使用する箱は椅子よりは低い程度の大きいものがオススメで、上に足を置いたときに股関節の動きも感じていきましょう。
体の横には手をおいて姿勢を維持、足の力だけでしっかりと持ち上げていくのが大切ですよ。
多裂筋のトレーニング

多裂筋とは、脊椎の周りに付いている小さな筋肉のことを指します。
多裂筋が弱ってくると背中が曲がったり反ったりしてしまい、それが原因で腰痛にもつながるんですね。
そこで腰痛の予防のために多裂筋のトレーニングが有効なんです。
やり方は膝をついて四つん這いになり、右手と左足を前後に伸ばす、次に左手と右足を前後に伸ばす、この動作を交互に繰り返しましょう。
慣れないうちはバランスが取れずにフラフラとしてしまうかもしれませんので、補助役の人についてもらうと安心ですね。
腰を反らさずにおこなうことがトレーニングを効果的におこなうために重要です。