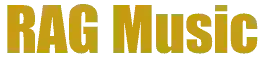祭りをテーマにした演歌の名曲。活気あふれる賑やかな曲
演歌の名曲の中には、祭りをテーマに描かれた楽曲がたくさんあるんですよね。
文字通り各地に実在するお祭りを歌ったご当地ソング的なものもあれば、祭りに男の生きざまを重ねて描いた楽曲もあります。
この記事では、そうした祭りをテーマにした演歌の名曲をたくさん紹介していきますね!
どの曲もお祭りの華やかさや賑やかさが込められた楽曲ばかり。
聴いている内に気持ちがどんどん盛り上がって元気が湧いてくることまちがいなしです。
祭りをテーマにした演歌の名曲。活気あふれる賑やかな曲(1〜10)
男の祭り唄福田こうへい

和太鼓の音が心地よく響き、まさにお祭りの活気をそのまま音にしたような、福田こうへいさんの1曲です。
歌詞に込められた、豊かな実りや大漁への祈り、そして自然への深い感謝の心が、福田さんの伸びやかな歌声に乗ってストレートに伝わってきます。
聴いていると、思わず「ソイヤ!」と声を出したくなるような、そんな力強さも魅力ではないでしょうか。
この楽曲は、2024年1月にCDシングル『庄内しぐれ酒/親友よ/男の祭り唄』として発売されました。
お祭り気分を味わいたい時はもちろん、何かを頑張る元気が欲しい時に聴けば、背中をぐっと押してくれるような心強さを感じられるはずです。
おんなの祭り市川由紀乃

演歌歌手である市川由紀乃さんのデビュー曲が『おんなの祭り』で、1993年にリリースされました。
佐賀県伊万里市で開催されている、女性だけでみこしを担ぐどっちゃん祭りの「女神輿」をモチーフにしたナンバーなんですよね。
みこしといえば男性のイメージがありますが、どっちゃん祭りの「女神輿」は迫力も活気もほかのみこしに負けないパワーを持っています。
『おんなの祭り』を聴いて興味を持たれた方は、ぜひ佐賀伊万里を訪れてみてください!
あばれ太鼓~無法一代入り~坂本冬美

魂を揺さぶる和太鼓の響きと、坂本冬美さんの力強い歌声が圧倒的な迫力で迫る一曲ですよね。
1987年3月に発売され、数々の新人賞を総なめにした彼女の輝かしいデビューを飾ったこの楽曲は、演歌史に残る名作と言えるでしょう。
歌詞では、人生の覚悟や、祇園の夏祭りといった日本の情景の中で、まるで魂が燃え上がるかのような男の生き様が描かれ、聴く者の心を熱くします。
本作は2008年9月にサブタイトルを加えて再録され、ライブでは欠かせない一曲として熱狂的に支持されています。
祭りの高揚感や、胸の奥からこみ上げるような情熱を感じたい時にぴったりの一曲ではないでしょうか。
祭りをテーマにした演歌の名曲。活気あふれる賑やかな曲(11〜20)
七夕おどり島倉千代子

島倉千代子さんの歌声に、仙台の七夕まつりの情景が鮮やかに浮かび上がるような一曲ですね!
本作は、日本の夏祭りの賑わいと華やかさを見事に描き出し、地元では盆踊りの定番としても愛されているのですね。
歌詞には、星空のもと浴衣姿で団扇を手に踊る楽しげな輪、青葉城や広瀬川の美しい風景、そして七夕のロマンが鮮やかに描かれています。
この楽曲は1962年7月、島倉さんが24歳の折に発売された作品なんですよ。
民謡調のメロディとフォークダンス風のリズムも、聴くだけで心が躍るようです!
古き良き日本の夏に浸りたい時や、お祭りの温かい雰囲気に包まれたい方にオススメですよ。
無法松の一生 (度胸千両入り)村田英雄

祭囃子が聞こえてくると、否が応でも心が躍り出すような気がしますよね。
そんな熱い魂を感じさせる村田英雄さんの代表作の一つは、まさに日本の夏、祭りの喧騒と高揚感を凝縮したような一曲と言えそうです。
主人公の型破りな生き様と、胸に秘めた一途な想いが、浪曲で鍛え上げられた力強い歌声を通じて、聴く者の魂を揺さぶります。
歌詞では、小倉祇園の夏祭りで打ち鳴らされる太鼓の音が、彼のどうにもならない恋心を断ち切り、前へ進もうとする決意を象徴しているかのようですよね。
1958年7月に世に出た本作は、同名の映画作品の情景をも彷彿とさせます。
祭りの夜にふと口ずさみたくなる、そんな男の生き様を描いた名曲なのですね。
男夢まつり神野美伽

夏祭りの熱気を力強く表現した演歌の名曲ですね。
みこしを担ぐ男たちの勇ましさや、祭りにかける情熱が歌われています。
胸のさらしやねじり鉢巻きといった祭りらしい表現も印象的です。
神野美伽さんの力強い歌声が、祭りの活気をより一層引き立てています。
本作は1991年3月に発売され、同年のアルバム『男夢まつり・神野美伽ベストヒット』にも収録されました。
祭りの季節はもちろん、元気がほしいときにもおすすめの1曲。
聴くだけで心が躍り、体が動き出すような、そんな魅力にあふれた楽曲です。
トリドリ夢見鳥 feat. DJ KOO丘みどり

丘みどりさんの『トリドリ夢見鳥 feat. DJ KOO』は、ダンスビートを基調とした華やかなお祭りソング。
DJ KOOさんとのセッションで生まれたこの曲は、日本盆踊り協会の公式タイアップソングにも選ばれました。
2024年12月25日発売の20周年記念アルバム『JOURNEY』に収録されています。
多彩な夢を追い求める鳥をモチーフにした歌詞は、明るく前向きなメッセージにあふれた内容。
夏のイベントや盆踊りで盛り上がるのにぴったりかもしれませんね。