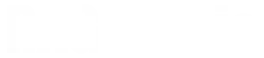【ハープの名曲】高貴で繊細な音色が際立つ名作を厳選
そよ風を連想させる透明感あふれる音色が魅力のハープ。
癒やしの音色もさることながら、弦をそっとなでるように演奏するハーピストの優雅な姿も印象的ですよね。
今回は、そんなハープのために作曲されたクラシックを中心に、その音色を存分に味わえる美しい名曲をご紹介します。
気持ちを落ち着かせたい夜や、爽やかな目覚めとともに1日をスタートさせたい朝、ハープの名曲を流しながら心穏やかに過ごしてみてはいかがでしょうか?
【ハープの名曲】高貴で繊細な音色が際立つ名作を厳選(21〜40)
ハープのためのソナタGermaine Tailleferre

20世紀フランスを代表する女性作曲家ジェルメーヌ・タイユフェールが手掛けた繊細な作品。
フランス六人組の一員として活躍した彼女の音楽は、透明感あふれるハーモニーが特徴です。
この曲では、ハープの優美な音色が織りなす柔らかな旋律が、聴く人の心を癒やしてくれることでしょう。
1892年生まれのタイユフェールは、2歳でピアノを始め、12歳でパリ音楽院に入学するなど、早くから才能を発揮。
ラヴェルからも指導を受けた彼女の音楽は、クラシック愛好家だけでなく、心地よい音楽をお探しの方にもおすすめです。
ハープ協奏曲 第6番 ヘ長調 Op.9Jean-Baptiste Krumpholz

クラシック時代を代表するハープ奏者であり作曲家でもあったジャン=バティスト・クランポルツ。
彼が残した『ハープ協奏曲 第6番 ヘ長調 Op.9』は、ハープの魅力を存分に引き出した傑作です。
エレガントで歌心あふれるメロディと技巧的なパッセージが絶妙に組み合わされた本作は、ハープ音楽の発展に大きく貢献しました。
1742年生まれのクランポルツは、52のソナタや6つの協奏曲など数多くの作品を残しています。
ハープの構造改良にも尽力した彼の功績は、今日のハープ音楽の基礎を築いたといえるでしょう。
癒やしを求める方にぴったりの一曲です。
ハープ協奏曲 イ長調 第3楽章Carl Ditters von Dittersdorf

ハープの魅惑的な音色を存分に堪能できる名曲が、カール・ディッタース・フォン・ディッタースドルフの手によって生み出されました。
18世紀後半に活躍したこの作曲家は、ハイドンやモーツァルトとも親交があり、多彩な音楽キャリアを歩んだことで知られています。
本作は、もともとチェンバロ協奏曲として1779年に作曲されたものをハープ用に編曲した作品。
軽快で愉快なムードを持つ第3楽章は、ハープの優雅で天使のような響きが際立ちます。
イタロ=オーストリアの旋律美を強調した繊細な音色は、リラックスしたい時や夢見るような気分の時にぴったり。
クラシック音楽の愛好家はもちろん、癒やしを求める全ての人におすすめの1曲です。
ハープ協奏曲イ長調 第2楽章Carl Ditters von Dittersdorf

カール・ディッタース・フォン・ディッタースドルフ作曲『ハープ協奏曲イ長調 第2楽章「ラルゲット」』。
もとはカール・ディッタースと称していましたが、33歳の時にマリア・テレジアから貴族に列せられたことによって、フォン・ディッタースドルフという家名が付け加えられました。
ハープとフルートのためのロンドレット第2番Nicolas-Charles Bochsa

19世紀フランスの作曲家ニコラ=シャルル・ボクサによる本作は、ハープとフルートの美しい調和が際立つ名曲です。
ロッシーニの有名なアリアをモチーフに、ボクサ独自の解釈で編曲された本作からは、彼の卓越した音楽センスが感じられます。
1813年に宮廷楽団のハープ奏者に任命されたボクサの経歴が、この作品の品格を高めています。
ハープの繊細な音色とフルートの澄んだ響きが織りなす優雅な旋律は、聴く人の心を穏やかにしてくれるでしょう。
静かな朝のひとときや、リラックスしたい夜に聴くのがおすすめです。