美しすぎるクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽
美しすぎるクラシックを一挙紹介!
クラシックには美しい曲がたくさんありますよね~。
今回は、その中でも特に美しい「美しすぎるクラシック」をピックアップしてみました!
長い歴史をこえて語り継がれる名曲たちがラインナップしていますよ!
美しいクラシックといえば、穏やかで爽やかものをイメージする方は多いと思いますが、ピアノだけではなく声楽やオーケストラで演奏される曲もピックアップしてみました。
それでは、ゆっくりとご覧ください!
美しすぎるクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽(1〜10)
練習曲作品10の3「別れの曲」Frederic Chopin

冒頭の旋律は特に有名で、誰もが一度は聴いたことがあるのではないでしょうか。
日本では「別れの曲」として有名ですが、これは1934年のショパンの生涯を描いたドイツ映画『別れの曲』でこの曲が使われていたために、こう呼ばれるようになりました。
この曲が作曲された頃、ショパンは故郷ポーランドを離れパリへと拠点を移しています。
パリでの成功を夢見る心情と田舎を懐かしむ心情が重なり合っていたであろう当時のショパンの心情が、温かくも時より激しい旋律によく表れています。
愛の悲しみNEW!Fritz Kreisler

古き良きウィーンの情緒をたっぷりと含んだ、哀愁と優美さが溶け合う名作『愛の悲しみ』。
オーストリア出身のバイオリンの巨匠、クライスラーさんが作曲したサロン音楽を代表する傑作です。
甘美な旋律のなかにほろ苦い感情が漂う本作は、1910年5月にクライスラーさん自身の演奏で録音が残されており、その歌うような音色は今も色あせません。
1923年にはジョージ・バランシンさんがバレエ音楽として採用するなど、演奏会だけでなく舞台芸術の世界でも愛されてきました。
ワルツの心地よいリズムと優雅な響きは、心を落ち着かせたい作業中や、勉強に集中したいときにピッタリといえるでしょう。
美しきロスマリンNEW!Fritz Kreisler

ウィーンの舞踏会を思わせる、軽やかで愛らしい旋律がとても印象的ですね。
オーストリア出身の名バイオリニスト、フリッツ・クライスラーさんが作曲した『美しきロスマリン』は、可憐な花を音楽で描いたようなバイオリンとピアノのための小品です。
ワルツのリズムに乗って跳ねるような音色は、聴く人の心を自然と明るくしてくれます。
本作は1910年に楽譜が出版され、1912年12月にはクライスラーさん自身による録音も行われました。
『愛の喜び』『愛の悲しみ』と並ぶ3部作のひとつですので、あわせて聴いてみるのもオススメです。
CMや映像作品のBGMとしてもよく使われていますから、作業の合間のリフレッシュや、穏やかな気分の勉強用BGMとしてぜひチェックしてみてください。
水の戯れJoseph-Maurice Ravel

水が変幻自在に色や表情を変える様子が描写されている1曲。
楽譜の冒頭には、アンリ・ド・レニエの詩「水の祭典」から引用した「水にくすぐられてほほ笑む河の神……」というテキストが添えられています。
曲名はリストの『エステ荘の噴水』に影響されていますが、ラヴェルは噴水そのものというよりも、光の加減とともに変化する水の色彩と音響を表現しようとしていたのでしょうね。
亡き王女のためのパヴァーヌMaurice Ravel

ピアノ作品の名作を聞かれると、多くの方は『亡き王女のためのパヴァーヌ』をイメージするのではないでしょうか?
本作は前衛的な音楽性で現代音楽に多大な影響をもたらした作曲家、モーリス・ラヴェルの名作です。
モーリス・ラヴェルは生前、この楽曲に対する評価を明言してこなかったのですが、晩年になってからはこの楽曲に対する特別な思いを述べています。
そういった背景を知ることで、より一層感動できるので、ぜひチェックしてみてください。
ソナチネ 2楽章Maurice Ravel

モーリス・ラヴェルといえば、『ボレロ』や『亡き王女のためのパヴァーヌ』で有名なフランスの作曲家です。
1903年に作曲された本作は、全3楽章からなるピアノ曲で、特に第2楽章が美しいと評判です。
優雅な舞踏のリズムと、ラヴェル独特の印象主義的な和声が織りなす音の世界は、まるで夢の中にいるような感覚を味わわせてくれます。
緻密な構造と豊かな表現力を持つ本作は、クラシック音楽ファンはもちろん、優雅な雰囲気に浸りたい人にもおすすめです。
ラヴェル自身も好んで演奏していたそうで、聴く人の心に深い感動を与える魅力にあふれています。
ヴォカリーズSergei Vasil’evich Rachmaninov
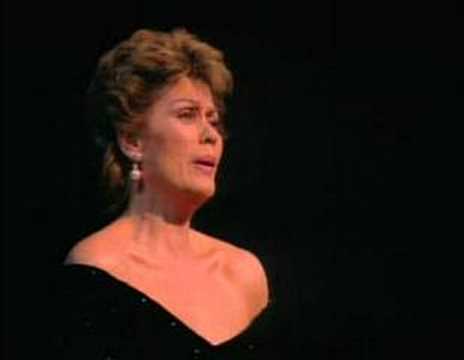
「ヴォカリーズ」は音楽用語で、一つ以上の母音を用いて歌う歌詞のない発声練習法のことを指します。
声楽において「あえいおう」という母音を使った発声練習は美しい歌声を出すうえで欠かせないもので、19世紀にはヴォカリーズの練習曲の楽譜も数多く出版されます。
そして、19世紀末あたりからヴォカリーズは単なる練習曲としてではなく芸術作品として扱われるようになりました。
この曲も歌詞のない歌曲でありながらも、その美しく切ない旋律が人々を魅了し続けています。



