切ないクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽
切ないクラシックを一挙紹介!
一口に切ないクラシックといっても、その曲調はさまざまです。
今回はピアノからヴァイオリン、小品や室内楽、協奏曲やオーケストラの曲など、さまざまなクラシックの切ない名曲をピックアップしてみました。
定番のものはもちろんのこと、クラシックを愛聴している方でもなかなか聞き覚えのない、マイナーな作品まで幅広くラインナップしています。
これからクラシックを知りたい方でも、既にクラシックにどっぷり浸かっている方でも楽しめる内容になっていますので、ぜひ最後までごゆっくりとご覧ください!
切ないクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽(1〜10)
交響曲第6番『悲愴』 第4楽章Pyotr Tchaikovsky

チャイコフスキーの最後の交響曲である『悲愴』。
「悲愴」という副題はチャイコフスキー自身によって付けられました。
終始、悲壮感が漂う雰囲気の曲ではありますが、その中にも激しさや美しさが見え隠れするのが特徴的です。
クライマックスの後に、重々しく静かに幕を閉じるのが印象的です。
この曲はチャイコフスキーの指揮により初演されていますが、その5日後にコレラを発症し亡くなりました。
彼の死後に追悼コンサートが開かれ、この曲はそこでも演奏されました。
亡き王女のためのパヴァーヌMaurice Ravel

こちらの曲はフランスの作曲家モーリス・ラヴェルが1899年にピアノの曲として作曲し、1910年に管弦楽の曲として彼自身が編曲した曲です。
タイトルだけを見ると亡くなった王女に贈る曲のように思えますが、実際は昔、スペインの宮廷で小さな王女が踊ったようなパヴァーヌを表現しています。
派手な曲ではありませんが、当時の宮廷での様子がイメージされるような、繊細でステキな曲ですよね。
ピアノのバージョンと管弦楽のバージョンを聴き比べるのも楽しいです。
ピアノソナタ 第8番 ハ短調 Op.13「悲愴」 第2楽章Ludwig van Beethoven
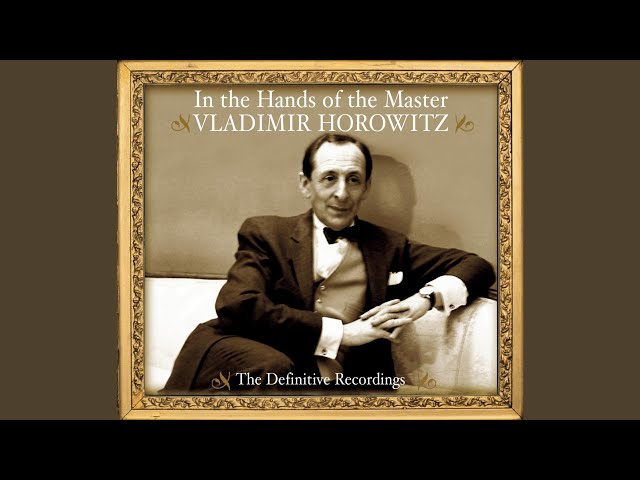
クラシック音楽の巨匠ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが若き日に作曲した作品です。
1799年に出版されたこの曲は、ベートーヴェンによる初期の作品では代表作として知られています。
青春の哀傷感を音楽で表現しようとした意欲作で、劇的な曲調と美しい旋律が特徴です。
第2楽章は特に人気が高く、穏やかで歌うような旋律が聴く者の心を揺さぶります。
ベートーヴェンの聴覚の衰えが始まった時期と重なりますが、その痛みや悲しみを乗り越えようとする強さも感じられます。
クラシック音楽に興味を持ち始めた方にもおすすめの一曲です。
シチリアーノGabriel Urbain Fauré

ガブリエル・フォーレは、19世紀後半に活躍したフランスの作曲家です。
当時フランスには、フランス独自の音楽を生みだそうという風潮がありました。
そこで作曲家達は、バロック時代の要素を作品に取り入れ新しい響きを生みだそうとしました。
この『シチリアーノ』もそのような時勢の中で生まれています。
「シチリアーノ」とは、17世紀から18世紀に流行した牧歌的で独特のリズムが特徴の音楽です。
バロック時代の音楽の特徴を生かすことで新しい響きを作り出し、魅惑的で幻想的な雰囲気に仕立て上げられたのがこの曲です。
旋律のようにJohannes Brahms

ロマン派音楽の巨匠、ヨハネス・ブラームスによる珠玉の歌曲をご紹介します。
1886年に発表された本作は、ピアノ伴奏と共に歌われる美しい旋律が特徴的です。
ブラームスは詩と音楽の調和を追求し、繊細な感情表現を重視しました。
イ長調で始まり、転調を通じて感情の変化を巧みに表現しています。
旋律が内面の感情や記憶をどのように引き起こすかを探る歌詞は、ブラームス晩年の内面世界を反映しています。
クラシック音楽の深い味わいを求める方におすすめの一曲です。
『エニグマ変奏曲』第9変奏「ニムロッド」Edward Elgar

「エニグマ」はギリシア語で、「なぞなぞ」「謎かけ」「謎解き」という意味で、作者のエルガーはこの変奏曲に2つのエニグマを込めたとしています。
「ニムロッド」は、楽譜出版社に勤める親しいドイツ人にエルガーが付けた愛称で、彼の人柄や、2人でベートーヴェンについて散策しながら論じた一夜を表したようです。
Morgen !Richard Strauss

クラシック音楽界の巨匠、リヒャルト・シュトラウスが贈る珠玉の歌曲。
1894年、妻ポーリーネへの結婚祝いとして作曲された本作は、愛と希望に満ちた明日への想いを優美に描き出します。
静謐な旋律と共に紡がれる詩は、二人の幸せな未来を見つめる温かさにあふれています。
シュトラウスの繊細な音楽表現が、詩の世界観を見事に昇華させる一曲です。
ロマン派の情感豊かな魅力が詰まった本作は、大切な人と共に聴きたい名曲として、多くの音楽ファンに愛され続けています。



