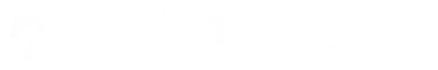学校では習わない!歴史に関する雑学&豆知識を一挙紹介
学校の授業で誰もが学んだ歴史。
苦手な人もいれば、今とは全く違う世界観にロマンを感じる人もいますよね。
学校で習うことの多くは歴史上の大きな出来事で、その周りにあるちょっとしたエピソードには触れないのが一般的です。
そこでこの記事では、学校の授業ではやらないような歴史に関する雑学&豆知識を紹介します。
あの偉人のびっくりエピソードや、歴史的な出来事の裏で起こっていた事件など、授業では知ることのできない歴史のおもしろい部分にフォーカスしました。
歴史好きな方もそうでない方も、ぜひチェックしてみてくださいね!
- いくつ解ける?歴史のおもしろい雑学クイズ
- 知りたくなかった?!気になる怖い雑学&豆知識
- 【勉強】知って楽しい!世界史の雑学クイズ集
- 学校にまつわる雑学クイズ。自慢したくなる豆知識まとめ
- 【歴史クイズ】知っておきたい歴史の一般問題
- 【小学生向け】小学校で習う日本の歴史クイズ
- 【一般向け】日常で即使える!役立つ驚きの雑学&豆知識
- 知って楽しい!宇宙の雑学まとめ【レク】
- 【難問】雑学クイズまとめ。難しくておもしろい3択問題
- おもしろい雑学のクイズ。新しい気づきに出あえる豆知識
- 【一般向け】思わず誰かに話したくなる!1月の雑学&豆知識特集
- 知ってると役立つ豆知識クイズ。学校や家で活躍する雑学【子供向け】
- 知っているようで意外に知らない?8月の雑学・豆知識クイズ!
学校では習わない!歴史に関する雑学&豆知識を一挙紹介(1〜10)
歴史上最も短い戦争はわずか40分で終結した
戦争といえば、数か月、数年と続くもの……とは限らなかった!?
歴史上最も短い戦争とされる「イギリス・ザンジバル戦争」は、わずか40分で終結したのだそうです!
1896年、イギリスと東アフリカの小国ザンジバル間で勃発したこの衝突は、イギリスの圧倒的な軍事力により瞬く間に終わりを迎えました。
学校では年表の流れを学ぶことは多いですが、こうしたトリビア的な話は歴史をより身近に、そして面白く感じさせてくれる良いきっかけになりますね。
江戸時代におならの身代わりをするお仕事があった
人前でおならをするのは恥ずかしい、しかし我慢するのは体に悪いという悩みは誰もが経験する苦しみです。
江戸時代にはそんなおならの悩みに寄りそう屁負比丘尼という職業が存在していました。
高貴な人の身の回りを世話しつつ、人前でうっかりおならをしてしまった高貴な人の身代わりとして、誰よりも素早く自分がおならをしたと宣言する人物です。
それが仕事になっていることで、当時の人にとってどれほどおならが恥ずかしいものだったのかが伝わってきますね。
日本の国旗が日の丸になったのは源平の合戦がきっかけ
日本の国旗といえば日の丸ですよね。
しかし、その由来を知っている人は少ないでしょう。
さかのぼること平安時代、源平合戦でのこと。
平氏は赤地に金色の丸の付いた旗を、源氏は白地に赤色の丸の付いた旗を掲げて戦いました。
そして源氏が勝つと、彼らは日本を統治した証として、日の丸の旗を持って各地を練り歩いたんです。
これが受け継がれ、現在も国旗として使われているんですよ。
もし平氏が勝っていたら、国旗のデザインは変わっていたでしょうね。
学校では習わない!歴史に関する雑学&豆知識を一挙紹介(11〜20)
ちょんまげは兜で頭が蒸れるから始まった
武士の髪形であるちょんまげ。
髪をそったり、結ったりと面倒くさそうですよね。
どうして手間暇をかけてあんな形にしたのかというと、兜をかぶった際に頭が蒸れてしまうからなんですよ。
その他の説には「冠の中に収めやすくするため」、「戦いの中でいつ死に直面しても、髪をそって出家できるように」という説があります。
どれも信ぴょう性がありますね。
ちなみに武士の中にはちょんまげにしていない人もおり、強制というわけではありませんでした。
徳川家康は健康オタクだった
江戸幕府を開いたことで有名な徳川家康は、実は戦国時代屈指の健康オタクとして知られています。
当時の平均寿命がおよそ30歳から40歳だったなか、家康は75歳という驚異的な長寿を全うしました。
その秘密は徹底した健康管理。
食事は麦飯や野菜中心で、動物性脂肪やぜいたくな料理を避け、少食を守っていたと言われます。
さらに薬草や漢方の知識にも通じ、自ら調合に関わるほどのこだわりよう。
天下をとっただけでなく、自身の体も冷静にコントロールしていた家康は、まさに戦国時代の健康マネジメントの達人です。
17世紀トルコではコーヒーを飲むことは死刑に値した
17世紀トルコでは公共の場でコーヒーを飲むことが厳しく禁止され、違反者には死刑を含む重い刑罰が科せられたことがあります。
トルコがまだオスマン帝国と呼ばれていたころの指導者ムラト4世はコーヒーを嫌っており、見せしめにコーヒーハウスを破壊したり、1杯飲めば40回の鞭打ち刑、2杯飲めば袋詰めにして海に捨てるという過激な処罰もしていたそうです。
人々は密かにコーヒーを飲んだり、カフェを開いたり、取り締まりは困難を極めて次第にコーヒー禁止は緩和されていったそうです。
現在トルココーヒーはユネスコの無形文化遺産に登録されトルコの重要な文化となっています。
ナイチンゲールが看護師として働いたのはわずか2年間
フローレンス・ナイチンゲールさんが看護師として活動した期間は、クリミア戦争中の約2年間だったと言われています。
彼女はクリミアの野戦病院に派遣され、荒れていた衛生面を徹底的に管理し、足りない薬などは自分でまかなったそうです。
しかし、過労により37歳の頃体調を崩してしまい、以降50年間はほとんど寝たきりで書籍の執筆など医療改革を訴えることに切り替えられた生活だったと言われています。
なりふり構わず24時間負傷した戦士たちの看護し献身的な活動から彼女を「クリミアの天使」と呼ばれるようになったそうです。