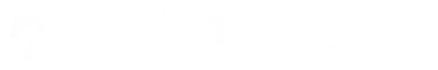学校では習わない!歴史に関する雑学&豆知識を一挙紹介
学校の授業で誰もが学んだ歴史。
苦手な人もいれば、今とは全く違う世界観にロマンを感じる人もいますよね。
学校で習うことの多くは歴史上の大きな出来事で、その周りにあるちょっとしたエピソードには触れないのが一般的です。
そこでこの記事では、学校の授業ではやらないような歴史に関する雑学&豆知識を紹介します。
あの偉人のびっくりエピソードや、歴史的な出来事の裏で起こっていた事件など、授業では知ることのできない歴史のおもしろい部分にフォーカスしました。
歴史好きな方もそうでない方も、ぜひチェックしてみてくださいね!
- いくつ解ける?歴史のおもしろい雑学クイズ
- 知りたくなかった?!気になる怖い雑学&豆知識
- 【勉強】知って楽しい!世界史の雑学クイズ集
- 学校にまつわる雑学クイズ。自慢したくなる豆知識まとめ
- 【歴史クイズ】知っておきたい歴史の一般問題
- 【小学生向け】小学校で習う日本の歴史クイズ
- 【一般向け】日常で即使える!役立つ驚きの雑学&豆知識
- 知って楽しい!宇宙の雑学まとめ【レク】
- 【難問】雑学クイズまとめ。難しくておもしろい3択問題
- おもしろい雑学のクイズ。新しい気づきに出あえる豆知識
- 【一般向け】思わず誰かに話したくなる!1月の雑学&豆知識特集
- 知ってると役立つ豆知識クイズ。学校や家で活躍する雑学【子供向け】
- 知っているようで意外に知らない?8月の雑学・豆知識クイズ!
学校では習わない!歴史に関する雑学&豆知識を一挙紹介(21〜30)
明智光秀は射撃がうまかった
明智光秀は戦国武将の1人で、織田信長を打ち取ったことで知られていますよね。
彼には少し意外な特技がありました。
1562年、朝倉義景は明光秀について「射撃の名手である」とのうわさを耳にし、腕前を見せてみよといいつけました。
すると光秀は100の的を設置し、離れた場所から百発百中で射抜いてみせたんです。
当時の火縄銃は現在の銃よりも性能が劣るので、彼の腕前は相当なものだったと推測できますね。
裏切り者として嫌われがちな光秀ですが、少しイメージが変わったのではないでしょうか。
産婆と飛脚は大名行列を横切ってOKだった
大名行列は知っていますよね?
大名が参勤交代などの際に、随員を引き連れて歩く行列のことです。
その長さは約4km以上にもなり、行く手を阻むのはタブーとされています。
しかし、特定の人物だけは、大名行列を横切ってもよいとされていました。
それは医者や産婆、飛脚など一刻を争うであろう人たちです。
ちなみに普通の人が大名行列を横切った場合は、切り殺してもよいというルールがあったそうです。
ただし、実際に切り殺されるのはまれだったと考えられています。
日本で初めてメガネをかけたのは徳川家康
日本で初めてメガネをかけたのは徳川家康ともいわれています。
当時はメガネではなく「目器」と呼ばれており、現在の耳にかける形ではなく、鼻にかけるタイプだったといわれています。
ちなみに日本で初めてメガネをかけたのは大内義隆であるとの説も有力視されています。
彼はフランシスコ・ザビエルから献上品としてメガネを渡され、ためしにかけてみたそうです。
ただし日常生活で愛用していたわけではないので「かけていた」とは言い難い気もしますね。
日本で初めてペンネームを使ったのは紫式部
文章を書いて広めるときに、本名とは異なるペンネームを名乗ることがありますよね。
そんなペンネームをはじめて使ったのは、『源氏物語』の作者としておなじみの紫式部だといわれています。
源氏物語に登場する紫の上と、父親の役職であった式部丞に由来するもので、作品への思い入れが感じられるペンネームですね。
平安時代の女性の、本名を夫にしか明かさないという風習の中で作品を残そうとした、紫式部の強い意志が名前から感じられます。
教科書などでよく見る聖徳太子の絵は聖徳太子ではない
聖徳太子といえば、十七条の憲法や冠位十二階の制定などの革新的な政治をした人物、その見た目といえば紙幣にもデザインされていた絵のイメージが強いですよね。
そんな聖徳太子は実在性が定かではなく、あの肖像画も別の人物のものではないかと言われています。
教科書に掲載された当初から誰の肖像画であるかははっきりとしておらず、天武天皇像ではないかなどさまざまな説が唱えられています。
どの時代に誰を描いたものなのか、それがわからなくなるほどに日本が長い歴史を歩んできたことを感じさせる内容ではないでしょうか。
ピラミッドという名前は「ピューラミス」というパンが由来
古代エジプトを象徴する建造物であるピラミッド、そこに眠っているものやどのように建てられたのかなど、謎が多い建物ですよね。
そんな神秘的なイメージが強いピラミッドですが、ピューラミスというパンの名称が由来だとされています。
ギリシャ語で三角形のパンをあらわした言葉で、身近なものの形に近いものから命名したことが伝わってきますね。
深い謎が込められたものが、シンプルな名称で呼ばれているという事実がおもしろいポイントですね。
縄文人は縄文土器でクッキーのようなものを作っていた
縄文時代といえば、時代の名前の由来にもなっている縄文土器や狩りなどに使われた石器が象徴ですよね。
鍋のような形をしたものから煮炊きをおこなっていたイメージが強いですが、それ以外にもさまざまな料理が作られていました。
木の実が食べられていたことや、道具をすり潰す用途で使っていたことから、クッキーのようなものも縄文時代の代表的な料理だといえるでしょう。
どんぐりなどの木の実を使っていたといわれていますが、獣肉も加えられていたという説があったりと、さまざまな形が推測されています。