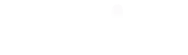【3歳児】1月にピッタリな冬&お正月製作!作って楽しむアイデア特集
1月の保育で子供たちと何を作ろうか、毎年悩んでいませんか?
お正月ならではのモチーフや冬の季節感を楽しみながら、3歳児さんが楽しめる製作を見つけるのは意外に難しいですよね。
そこでこちらでは、紙皿コマや鏡餅、ししまいなど、お正月にぴったりのアイデアから、もこもこひつじや雪だるまといった冬らしい製作まで、3歳児さんと一緒に楽しめるアイデアをご紹介します。
指スタンプやフィンガーペイント、折り紙など、手や指先を使った製作は子供たちの好奇心もくすぐりますよ。
作った後に遊べるものもあるので、ぜひ参考にしてみてくださいね!
子供たちの作ったものは作品として扱うため、文中では「制作」と表記しています。
- お正月遊びから冬の制作まで!1月の保育で楽しむレクリエーション特集
- 【3歳児】2月に作りたいオススメ製作のアイデア集
- 【1月】2歳児と楽しむ!冬やお正月を感じる製作のアイデア集
- 【1月の制作】子供向け!保育にいかせる楽しい手作りのアイデア集
- 【4歳児】1月の制作!冬やお正月をテーマに楽しむアイデア集
- 【3歳児】保育に使える冬の製作遊びや壁面製作のアイディア
- 保育で楽しむ!1月の寒い日に盛り上がる遊びのアイデア集
- 【保育園・幼稚園】お正月製作のアイデア特集!作った後にも楽しめる作品集
- 1月の楽しい制作!5歳児さんと作って遊べるアイデア集
- 1歳児さんと楽しむ!1月にオススメのモチーフの製作のアイデア集
- 【11月】3歳児と楽しむ!秋にオススメの製作遊びのアイディア
- 3歳児と作ろう!楽しい手作りおもちゃのアイディア
- 【保育】3歳児にオススメ!冬をテーマにした折り紙のアイデア
【3歳児】1月にピッタリな冬&お正月製作!作って楽しむアイデア特集(1〜10)
デカルコマニーのかわいい手袋
@hoikushisatomi 【技法を使った制作】デカルコマニー手袋#さとみ先生#保育士#子供が喜ぶ#製作#おうちモンテ#子どものいる暮らし
♬ オリジナル楽曲 – 【保育クリエイター】さとみ先生 – 【保育クリエイター】さとみ先生
みなさんはデカルコマニーをご存じでしょうか。
紙に塗った絵の具をはさんで押し当て、偶然できる模様を転写する技法です。
これを使って手袋の飾りを作ってみましょう。
まず、色画用紙を半分に折り、半分に好きに絵の具を置いていきます。
置いたらもう半分を押し付け、模様を転写します。
そうして作った紙を手袋の形に切りましょう。
綿などを使って手袋の入り口を飾るのも立体感が出てかわいいです。
台紙に貼りつけ、毛糸などを貼ってもいいですね。
手作り牛乳パック羽子板
@silk_haru3mama 牛乳パックで羽子板を作ってみたよ #お正月#工作#お正月工作#お正月製作#おうち遊び#ハンドメイド#羽子板
♬ Animal baby – 上野燿
お正月の遊びといえば羽根つき。
この羽子板を牛乳パックを使って作ってみましょう。
牛乳パックは開いて底の部分を取り除きます。
取り除いたら裏返し、二つに折りたたみます。
飲み口のところは折りたたむと羽子板によく似た形になります。
新聞紙の中に割りばしを入れ、新聞紙を折りたたむと羽子板の持ち手になるので、それを牛乳パックにセットしてテープでとめます。
とめたら上下と牛乳パックのつなぎ目もとめます外側にかわいい柄の折り紙を貼ってもいいですね。
毛糸を通して作るもこもこ雪だるま
ひも通しを楽しみながら、冬にぴったりの雪だるまを作ってみましょう。
このアイデアでは、白い画用紙から切り出した円形の枠にパンチで穴を空けて、そこに毛糸を通していきます。
すべての穴に毛糸が通せたら雪だるまの体の完成なので、少し小さめの丸いパーツを画用紙から切り出し、頭として接着しましょう。
マフラー、帽子、腕、顔のパーツを貼ればできあがりです!
毛糸は1本でカラフルな配色のものがあるので、それを使うと華やかに仕上がりますよ。
【3歳児】1月にピッタリな冬&お正月製作!作って楽しむアイデア特集(11〜20)
冬の保育に!折り紙のおでん

こんにゃく、大根、ちくわの3つを棒に刺した、おでんを折り紙で作ってみましょう。
まずは灰色の折り紙を2回折って小さい三角を作り、模様を描いてこんにゃくを作ります。
次に、黄色の折り紙をざぶとん折りして、さらに4つの角を内側に折って丸みを出したら、十字の切り込みを描いて大根に仕上げましょう。
ちくわは茶色い折り紙に模様を描いて、筒状に丸める事で表現できますよ。
串の折り紙を細長く折って、作った3つの具材を接着したらおでんの完成です!
スポンジスタンプで作る!楽しいおでん

スポンジスタンプで、おでんの具材の模様を作っていきます。
例えば、おでんのこんにゃくの場合、三角に切ったグレーの画用紙に粗い目のスポンジや、でっぱりを作ったスポンジをスタンプのように押すと、こんにゃくのつぶつぶが作れます。
同じ要領で、筋を入れたスポンジを使えば大根の筋、細かな切り込みを入れたスポンジを使えば練り物のもやもやとした模様も作れそうですね!
できたおでんの具材は、鍋の形に切り出した画用紙に貼っていき、おでんの鍋を完成させましょう!
おでんのお手軽な作り方
@hoikusi1 【おでんの製作】 壁面にもなる作り方を保育士が解説!(2歳児~) おでん製作の手順を保育士が教えます。 壁面にもなるカンタンな作り方です。 《対象年齢》 2歳児以上 #保育#保育士#保育士さん#保育士一年目#保育製作#保育園製作#製作遊び#おりがみ#折り紙#折り紙遊び#保育教材#保育ネタ#保育士の卵#立体#工作#簡単#壁面#冬#おでん
♬ オリジナル楽曲 – 保育士1年目のトリセツ – 保育士1年目のトリセツ
画用紙で作ったスープ入りのお鍋に、おでんの具材を貼っていきましょう!
ハサミを使える年齢の子達には、画用紙に補助線だけを描き、自分で具材の形に切ってもらってくださいね。
それをスープの上にのりで貼り、模様を描いていきますよ。
ハサミを使えない年齢の子には、具材のパーツを事前に用意し、裏面に両面テープを貼ってシール貼り感覚で楽しんでもらいましょう。
定番の大根、こんにゃく、たまご、餅巾着のほか、どんな具材を入れるか考えるのも楽しい制作ですね。
冬に楽しい!おでん屋さんごっこ
@taisougakuen_osaka_ikuno そら組(年中さん) おでんの製作です🍢 チョキチョキと、おでんの具材を好きなだけ作ってお鍋へ入れました🍲 美味しそう😍 特徴を捉えて、形や色使いもバッチリ表現されていますね💮 #体操#保育園#優良認可外保育園#体操大好き#生野#大阪市生野区#楽しい保育#ユニークな保育#体操好きな人と繋がりたい#アインス体操クラブ#fyp#年中さん#製作#おでん
♬ Maido Happy – Ulfuls
子供たちがおでん屋さんの店主に変身する、ユーモアな制作アイデアです。
おでんの具材は画用紙を切ったり貼ったり、ペンで模様を描いたりして作りますよ。
それらを画用紙で作ったお鍋の中に貼り付けましょう。
お鍋を大きめの台紙の下の方に接着し、その上にねじりはちまきをして腕組みした子供たちの写真を貼ってくださいね。
最後に、台紙の上の方にのれんを張ったら完成です!
のれんの文字も子供たちが描いていて、お店の雰囲気がそれぞれ出ていますね。