【ルネサンス音楽】ポリフォニーの魅力あふれる名曲を厳選
一般的に、1600年頃のヨハン・セバスティアン・バッハらが活躍した「バロック時代」から語られることの多い西洋音楽史。
しかし、音楽はそれ以前にすでに存在しており、1400年頃から1600年頃にかけて起こった文化運動「ルネサンス」の最中に生まれた「ルネサンス音楽」は、中世西洋音楽からバロック音楽への橋渡し的存在として、クラシック音楽の歴史の中でも重要視されています。
ルネサンス音楽の特徴は、複数の声部の重なりによって構成された「ポリフォニー音楽」であり、その多くが歌曲、そして宗教曲であること!
本記事では、そんなルネサンス音楽の中でも知名度が高く、現代でも演奏会などで取り上げられている名曲をご紹介します。
【ルネサンス音楽】ポリフォニーの魅力あふれる名曲を厳選(1〜10)
アヴェ・マリアJosquin Des Prez

ルネサンス音楽を代表する作曲家のひとり、ジョスカン・デ・プレが1480年代に作曲した『アヴェ・マリア』。
このモテットは、文法的模倣の技法を駆使し、各声部がグレゴリオ聖歌を彷彿とさせる形で効果的に反響しあっています。
各声部が織りなす複雑でありながらも均衡を保つ美しい響きは、聴く者の心をとらえて離しません。
神聖な雰囲気を醸し出しながらも、ジョスカンの遊び心も感じられる本作は、現代にまで受け継がれる不朽の名作です。
クラシックをこれから深く知りたい方に、ぜひとも聴いていただきたい1曲です!
祝福の賛美歌Giovanni Pierluigi da Palestrina

ルネサンス音楽界の巨匠であり、「教会音楽の父」とも称されるジョヴァンニ・ピエルルイージ・ダ・パレストリーナ作曲の『祝福の賛美歌』。
複雑で洗練されたポリフォニーが絡み合いながらも、天に届くほどの透明感のあるハーモニーをつむぎ出す、息をのむような美しさを持つ作品です。
この楽曲の各声部は、独立しながらも一つの大きな流れを成すように精密に作曲されていて、聴くたびに新たな発見があります。
パレストリーナの卓越した音楽的技巧と教会音楽への深い信仰心が反映されたこの作品は、歴史を超えて今もなお、多くのクラシックファンを魅了し続けています。
Now Is The Month Of MayingThomas Morley

トーマス・モーリーの『Now Is The Month Of Maying』は、1595年に作曲された春の訪れと愛の喜びを祝う曲です。
その軽やかなリズムと「ファ・ラ・ラ」のコーラスからは、当時イギリスで盛んだったメイデーの祝祭の雰囲気を感じ取ることができます。
春がやってくるとなぜかワクワクしてしまうのは、昔も今も変わらないようですね。
穏やで心地よい春の空気に癒されながらこの曲を聴けば、春の訪れにより幸せを感じられるでしょう。
ノートルダム・ミサ曲Guillaume de Machaut

ギヨーム・ド・マショーが1365年に作曲した大聖堂ミサ曲である『ノートルダム・ミサ曲』は、14世紀にフランスで栄えたアルス・ノヴァ様式の特徴を備えポリフォニーの技法を駆使した、4声部による作品。
和声の美しさと宗教的な雰囲気が、聴く者を中世の荘厳な世界へと誘います。
マショーは、音楽を宗教の一要素から芸術へと進化させた最初の作曲家ともいわれています。
そんな彼の代表作である本作は、ポリフォニーの魅力を存分に感じられる1曲といえるでしょう。
入祭唱(「レクイエム」より)Johannes Ockeghem
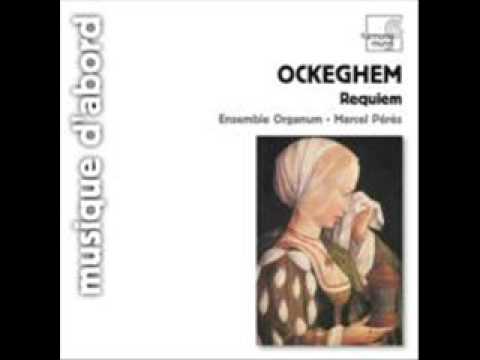
ヨハネス・オケゲムの代表作『レクイエム』は、1491年に作曲された作品。
ポリフォニーの巧みな技術が光る本曲の中でも、その日のミサの内容を告げる『入祭唱』には当時の音楽的技術が凝縮されており、4声の穏やかで重層的な旋律が聴く者の心を引き込み、ルネサンス期の深遠な世界観を感じさせてくれます。
美しさと技巧を兼ね備えた本作は、クラシカルな音楽を愛する人はもちろん、多声音楽の魅力に触れたい人にもピッタリです!
モテット「サルヴェ・レジーナ」Josquin Des Prez

ポリフォニーが特徴のジョスカン・デ・プレのモテット『サルヴェ・レジーナ』。
1521年の発表以来、多くの観客を魅了し続けてきたこの作品は、5声部によって構成されたア・カペラ曲で、宗教音楽の金字塔ともいえる壮麗さがあります。
特に、ヴェーザー・ルネサンスによる2010年の演奏は聴きごたえがあり、その緻密かつ情感豊かな解釈には、本作の神髄を見出すことができます。
3部からなる構造はバリエーションに富み、聴く者を中世の荘厳な雰囲気へといざなってくれるでしょう。
クラシック入門者から熟練者まで、幅広い層にオススメの名曲です!
怒りの日(グレゴリオ聖歌より)

中世ヨーロッパで発展した、カトリック教会で歌われる『グレゴリオ聖歌』。
中でも『怒りの日』は、中世カトリック教会のレクイエムミサから現代の映画音楽まで、幅広く受け継がれてきた作品です。
13世紀にトーマス・デ・セラーノが選定したこのメロディからは、豊かな歴史と審判の日の不安を織り交ぜた重厚な雰囲気が感じられます。
ベルリオーズの『幻想交響曲』やサン=サーンスの『死の舞踏』をはじめとする多くのクラシック作品に影響を与え、モーツァルトやヴェルディがそれぞれのスタイルで再解釈したことも、『怒りの日』を語るうえで特質すべき点といえるでしょう。



