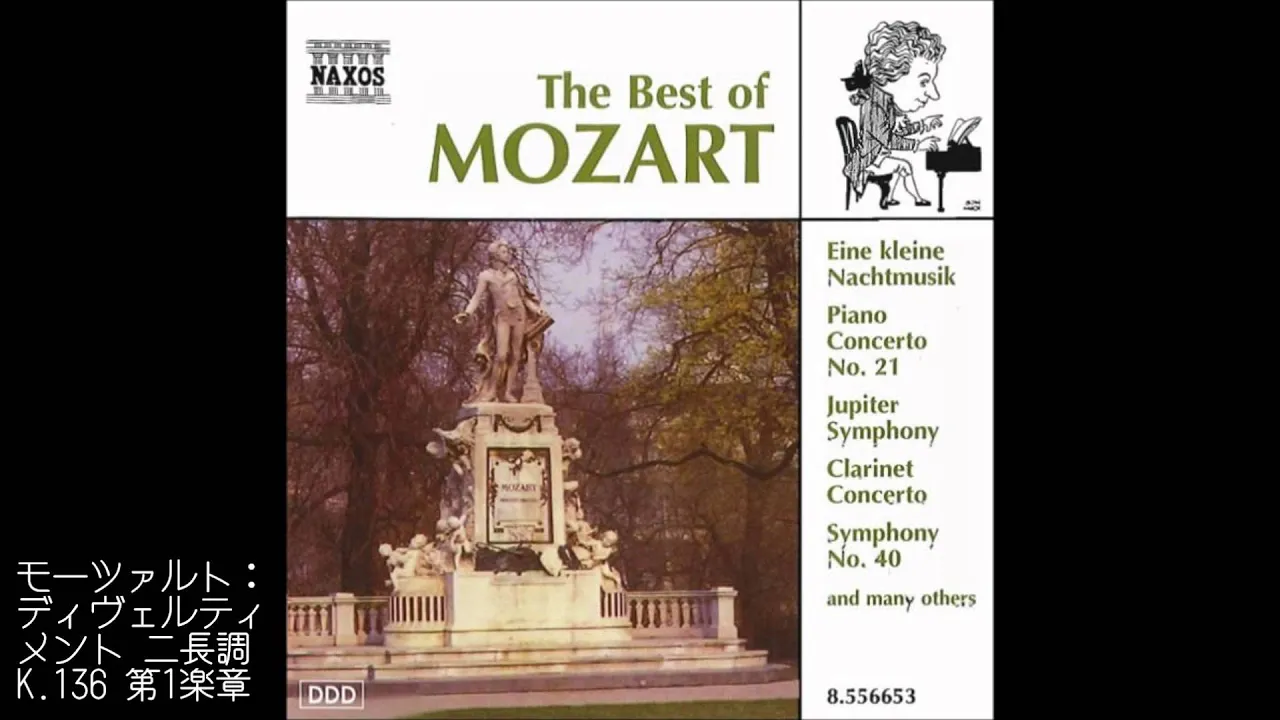【モーツァルト】代表曲、人気曲をご紹介
クラシック音楽に大きな影響を与えた、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト。
5歳で作曲を始め、ヨーロッパの王室の前で演奏するなど幼少期から才能を発揮し、35年の生涯の中で800以上もの作品を残しました。
また、当時の音楽ジャンル全てにおいて名曲を残し、作曲だけでなく指揮者、ピアニスト、オルガニスト、ヴァイオリニストとしても優れていたことから、音楽の天才と呼ばれていました。
本記事では、そんなモーツァルトの代表曲、人気曲をご紹介します。
耳に残りやすく馴染みやすい旋律ながら、質が高く一言では言い表せない魅力を感じられる彼の音楽を、ぜひお楽しみください!
【モーツァルト】代表曲、人気曲をご紹介(1〜10)
ディベルティメント ニ長調 K.136 – 第1楽章NEW!Wolfgang Amadeus Mozart

1772年の初めにザルツブルクで書かれたとされ、「ザルツブルク・シンフォニー」の愛称でも親しまれているヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトの作品。
その第1楽章は、イタリア旅行の影響を感じさせる明朗で疾走感のある旋律が印象的な、弦楽合奏の名曲です。
池袋駅の発車メロディとして使用されていたこともあるため、耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
心地よい弦の響きと推進力のある展開は、停滞しがちな作業や勉強の時間を軽やかなものに変えてくれますよ。
頭をすっきりさせて集中したいときに最適な、オススメのクラシックナンバーです。
ディベルティメント ニ長調 K.136 – 第3楽章NEW!Wolfgang Amadeus Mozart

古典派を代表する天才、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトの数ある作品のなかでも、弦楽合奏の定番として広く親しまれている本作。
明るく快活な「プレスト」のテンポで駆け抜ける躍動感は、コンサートのアンコールでも頻繁に演奏されるため、耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか?
1772年、当時16歳だったモーツァルトがザルツブルクで書き上げたとされるこの楽曲は、シンプルながらも洗練された構成が魅力です。
爽やかな疾走感は、停滞気味な作業の空気を入れ替え、リフレッシュしたい瞬間に最適ですよ。
レクイエム ニ短調 K.626Wolfgang Amadeus Mozart

モーツァルトが35歳で亡くなる直前に手掛けた未完の傑作。
死者のためのミサ曲として荘厳な雰囲気が漂う本作は、神への祈りと死者の魂の安息を願う内容となっています。
入祭唱から始まり、怒りの日を描いた『ディエス・イレ』、涙の日を歌う『ラクリモーサ』など、多彩な楽章で構成。
とくに『ディエス・イレ』は最も有名で、テレビや映画などでも頻繁に使われています。
この動画内ですと8分13秒からの部分にあたります。
また『ラクリモーサ』は、モーツァルト自身が8小節まで書き残した部分で、その美しさが人々の心を打ちます。
この動画内ですと22分49秒。
深遠な音楽性と宗教的な意味合いを持つ本作は、モーツァルトの人生が詰まっているように感じられます。
オペラ「フィガロの結婚」序曲Wolfgang Amadeus Mozart

モーツァルトのオペラ序曲の中で最も有名な曲です。
どこかで一度は聴いたことがある方も多いのではないでしょうか?
テーマを聴けば誰もが分かるようなキャッチーなメロディが最大の特徴。
明るく華やかに、これから始まるオペラの雰囲気を聴衆に伝える重要な役割を果たしています。
オペラ「魔笛」序曲Wolfgang Amadeus Mozart

モーツァルトが最後に手がけたオペラ『魔笛』の序曲は、オペラ全体の主題を導入する重要な役割を果たしています。
フリーメイソンの思想を背景に、善と悰、光と闇、試練を通じての成長など、普遍的なテーマを扱った本作。
短く力強いコードで始まり、その後に追従する軽快で活気ある旋律が特徴的です。
モーツァルトらしい華やかさと深みを持ち合わせた本作は、聴く者をすぐに魅了します。
序曲らしい、物語の始まりを感じさせるこちらの曲をぜひ聴いてみてください。
アイネ・クライネ・ナハトムジークWolfgang Amadeus Mozart

モーツァルトの代表作の一つとして知られるこちらの弦楽セレナードは、軽やかで優雅な旋律が印象的です。
1787年8月、31歳のモーツァルトがウィーンで完成させた本作。
もともとは5楽章構成でしたが、現在は4楽章で演奏されることが多く、弦楽合奏や弦楽四重奏などさまざまな編成で演奏されています。
第1楽章の明るく活気に満ちたメロディはとくに有名で、広く親しまれていますね。
今でも多くの演奏家に楽しまれているこちらの名作を、ぜひ聴いてみてはいかがでしょうか?
オペラ「ドン・ジョバンニ」序曲Wolfgang Amadeus Mozart

冒頭の悲劇的なオーケストラの響き、そしてその後奏でられる鬱々としたメロディが、このオペラの最後を示唆しているようです。
しかし曲が進んでいくうちに、コミカルで溌剌とした雰囲気に移り変わっていきます。
1787年の初演以来頻繁に上演され、数あるオペラの中でもかなりの人気を誇る作品の一つです。