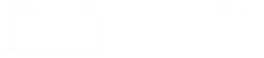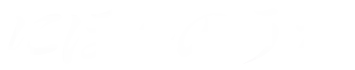日本の浪曲。伝統の浪花節(なにわぶし)
「浪花節」(なにわぶし)とも呼ばれる日本の浪曲の中から、スタジオスタッフがおすすめする名曲をご紹介します。
日本の義理・人情を今に伝える貴重なプレイリストです。
日本の浪曲。伝統の浪花節(なにわぶし)(21〜30)
壺坂霊験記浪花亭綾太郎

幼い頃に病気で失明し、様々な苦難の道を歩きながら、1903年に初代浪花亭綾造門下となり、21歳で綾太郎を襲名しました。
夫婦愛を描いた代表作「壺坂霊験記」の一節は、昭和中期なら浪曲通ならずとも知れ渡っていたほどです。
昭和の名人の一人。
仙台の鬼夫婦玉川奈々福

会社勤務の傍ら玉川福太郎門下で浪曲を学び、曲師(三味線奏者)からのちに浪曲師に専念。
大小の会場での浪曲会やプロデュース公演、新作の口演なども手掛け、現在最も行動力のある浪曲師と言っても過言ではないでしょう。
紀文戻り船天龍三郎
1915年生まれ。
戦前の大相撲力士(のち解説者)の天竜三郎になぞらえて改名、2014年に98歳で亡くなるまでこの名前でした。
この音源では、三味線とエレキギターによるツイン伴奏という珍しい演出を試みています。
からかさ桜澤孝子
1939年生まれ。
1954年に二代目広沢菊春に入門、1961年に澤孝子と改名。
ピンと張りのある声と、明るく歌い上げる調子が特徴的。
2008年から日本浪曲協会第十七代会長を二期務め、その後は相談役として会を支えています。
灰神楽道中記(一)初代相模太郎

1900年生まれ。
17歳で入門後、戦前レコードを吹き込んだ際に相模太郎と改名。
「灰神楽三太郎」が代表作。
1972年没。
次男の二代目相模太郎は「怪物くん」などテレビアニメ初期時代の声優としても活躍した人でした。
木村の梅富士路子

1994年に女流浪曲師の富士琴路に入門。
凛とした歌い口調で着実に実力を高め、2013年からは第十八代日本浪曲協会会長に就任。
その一方で、カルチャースクールにて浪曲教室の講師も務めるなど浪曲の普及に努めています。
天保水滸伝 平手造酒の最後三代目玉川勝太郎

1933年生まれ。
1948年に二代目勝太郎門下(のちに娘婿)、1964年に三代目襲名。
お家芸「天保水滸伝」や任侠物など先代の芸を継承しました。
浪曲コミックバンド「玉川カルテット」の元リーダー・玉川ゆたかはこの人のお弟子さんです。