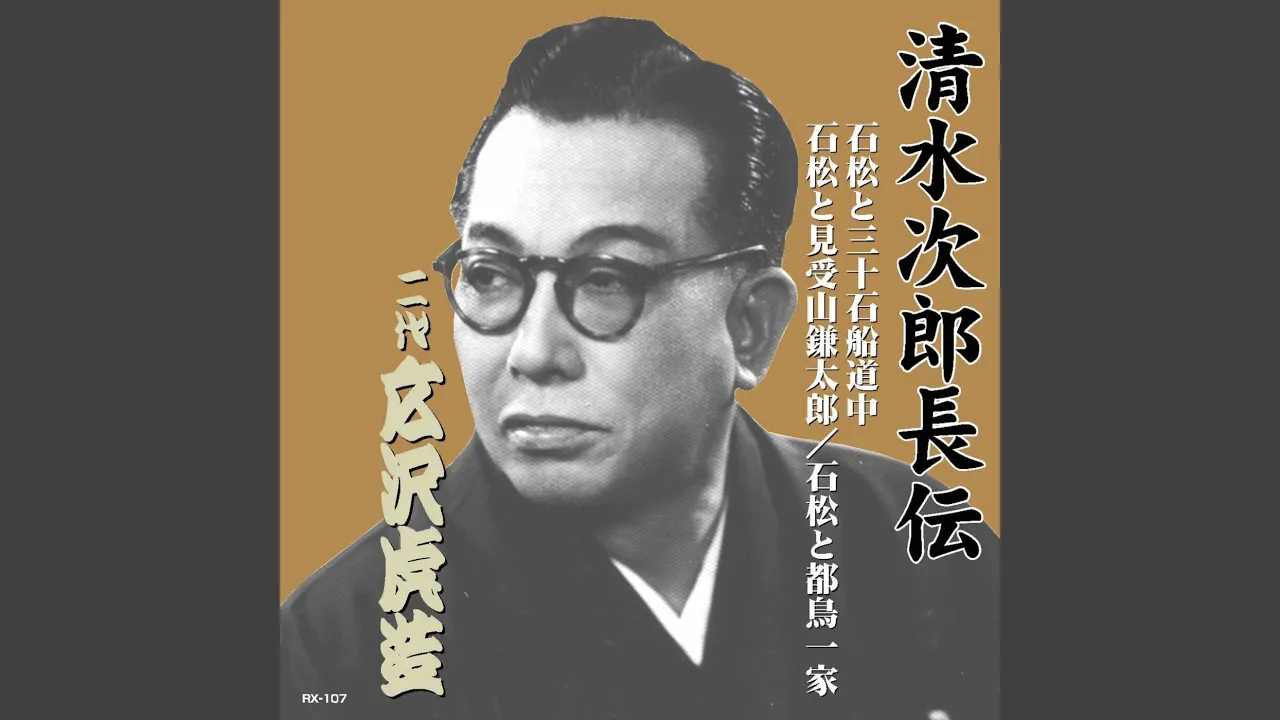江戸時代から続く日本の伝統芸能である浪曲は浪花節とも呼ばれ、打楽器三味線の伴奏に乗せて、人情噺や歴史物語を情感豊かに語る独特な語り芸です。
一人の語り手、つまり浪曲師が複数の登場人物を演じ分け、歌と語りを巧みに使い分けながら物語を展開していきます。
庶民の喜怒哀楽を描いた義理人情物や、歴史上の英雄を題材にした時代物など、その作品世界は実に多彩。
近年では若手浪曲師の活躍も目覚ましく、現代的な解釈や新作の上演にも積極的に取り組んでいます。
そんな浪曲に興味を持たれた方に向けて、代表的な作品をここでは紹介します。
入門編としてもぴったりな記事をぜひお楽しみください。
- 昭和の名曲まとめ。必聴の懐メロ&ヒットソング特集
- 【ご当地ソング】日本全国の名曲&郷土愛の詰まったおすすめソング
- 【日本の心】三味線の名曲・人気曲まとめ
- 女の演歌。女性の心情を歌った演歌の名曲まとめ
- 【大阪の歌】情熱的&人情味あふれる大阪ソングをピックアップ
- 日本海を歌った演歌。大海原をテーマにした名曲まとめ
- YouTubeショートのBGMにおすすめ!令和リリースの人気曲
- 【2026】長崎を歌った演歌・歌謡曲の名曲まとめ【ご当地ソング】
- 【花便り】竹島宏の歌いやすい曲まとめ【2026】
- 【日本の伝統音楽】雅楽・神楽の名曲。おすすめの日本の伝統音楽
- 『日本の伝統』純邦楽の日本の祭ばやし
- 男の演歌。男性の生きざまや心意気が描かれた名曲まとめ
- 【初心者向け】カラオケでおすすめの演歌の名曲~女性歌手編
【入門編】日本の伝統芸能~浪曲の名作を紹介【浪花節】(1〜10)
石松と三十石船道中二代目広沢虎造

清水次郎長一家の子分・森の石松が、金比羅参りの帰路に三十石船へ乗り込み、大坂から伏見への道中で繰り広げる人情噺。
本作は二代目広沢虎造さんが得意とした「清水次郎長伝」シリーズの一席で、船中での軽妙な掛け合いと啖呵が魅力です。
石松の自尊心と人間味が滲み出る語り口は、笑いと義理人情が見事に調和しています。
1958年4月にシングルとしてリリースされた本作は、その後アルバム『清水次郎長伝 石松と三十石船道中』に収録され、2015年11月には復刻盤『新・浪曲名人特撰シリーズ 二代 広沢虎造』でも聴くことができます。
浪曲独特の三味線伴奏に乗せた「虎造節」の語りは、江戸時代の船旅の雰囲気を鮮やかに描き出しており、浪曲の入門としても最適な一作です。
佐渡情話寿々木米若

佐渡島と柏崎を舞台に、漁師の男女の悲恋を描いた本作。
1931年1月にレコード発売された寿々木米若さんの代表的な演目です。
嵐の海で遭難した若者が佐渡の親子に救われ、娘と恋に落ちるものの、横恋慕する者の策略により悲劇が訪れるという物語。
民謡「佐渡おけさ」の旋律を織り込んだ独特の節回しと、哀切に満ちた語り口が聴く者の心を揺さぶります。
レコードは大ヒットを記録し、映画化もされました。
浪曲という芸能に初めて触れてみたい方や、故郷の海を懐かしむ方にぴったりの作品です。
日本海の荒波と人間模様が交差する情緒豊かな世界観を、ぜひ味わってみてください。
小鉄と新門辰五郎初代京山幸枝若
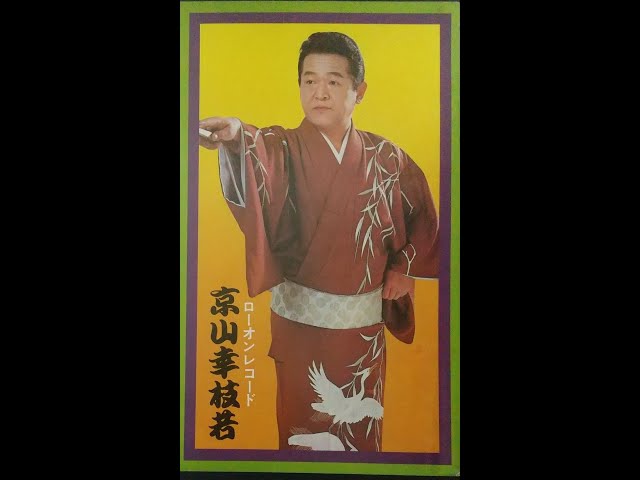
侠客の生き様を三味線の音色に乗せて語る浪曲シリーズの一編。
会津の小鉄と江戸の侠客・新門辰五郎との出会いと因縁を描いた人情譚で、初代京山幸枝若さんの十八番として一門で「お家芸」と称される演目です。
義理と人情、男の友情と対立が交錯するドラマチックな展開が特徴で、語りの中で複数の登場人物を声色豊かに演じ分ける技巧が見どころとなっています。
1995年11月にテイチクエンタテインメントから発売され、2015年11月にはアルバム『新・浪曲名人特撰シリーズ』として復刻されました。
侠客物語の醍醐味を味わいたい方や、浪曲ならではの語り芸の迫力と情感を体験したい方にオススメの一作です。
大野の宿場二代目広沢虎造

江戸時代から受け継がれる、浪曲の世界を代表する演目です。
清水次郎長という侠客を描いた物語の一幕で、宿場を舞台に次郎長が代官屋敷に捕らわれた仲間を救い出す緊迫の展開が語られます。
二代目広沢虎造さんによる力強い啖呵と情感豊かな節回しが、登場人物たちの心情や場面の緊張感を見事に表現しており、聴く者を物語の中へと引き込んでいくのです。
収録作品『清水次郎長伝/大野の宿場/代官斬り』は1995年9月にテイチクエンタテインメントから発売され、長年にわたり多くの復刻盤がリリースされてきました。
浪曲という芸能に初めて触れる方、また義理人情の物語が好きな方には、虎造節の真髄を味わえる入門作としておすすめです。
赤城の血煙り二代目広沢虎造
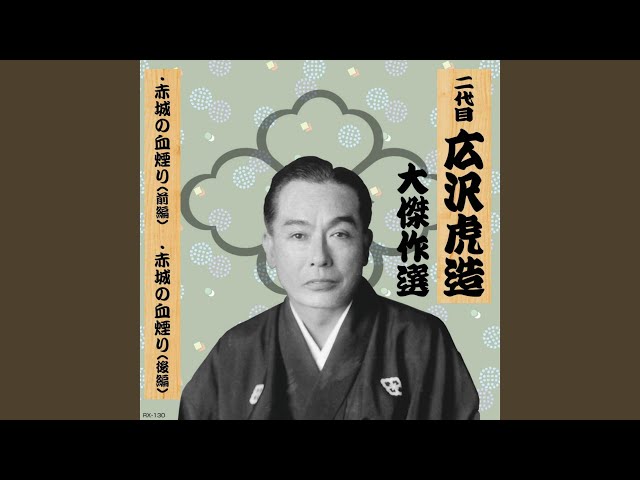
江戸時代から続く語り芸である浪曲の真髄を味わえる、国定忠治の世界を描いた名演です。
赤城山のふもとを舞台に、破戒僧・頑鉄が忠治一家の危機を救うという侠気あふれる物語で、義理と人情が交錯する展開が胸を打ちます。
二代目広沢虎造さんの「虎造節」と呼ばれる独特の語り口は、関東と関西の節回しを融合させたもので、威勢の良い啖呵や緩急自在の間が聴く者を引き込みます。
1995年11月にテイチクエンタテインメントから発売されたCD『国定忠治(忠治・赤城の血煙り)』に収録され、2015年11月には復刻版もリリースされました。
浪曲入門として、また日本の伝統芸能に触れたい方に最適な一作です。
天野屋利兵衛初代春日井梅鶯

忠臣蔵の物語を題材とした浪曲演目のひとつであり、初代春日井梅鶯さんの代表作として知られる作品です。
1995年にテイチクエンタテインメントから発売されたCDに収録されており、かつて1969年や1973年に録音された演目が現代に甦った音源となっています。
三味線の伴奏にのせて繰り広げられる本作の語りは、赤穂義士にまつわる義理人情を描いており、武士の忠義と覚悟をテーマに据えた重厚な内容です。
梅鶯さんの明快な節回しと美声が存分に発揮された本作は、緩急のあるドラマティックな展開で聴く者をぐいぐいと物語の世界に引き込んでいきます。
浪曲ならではの語りと節の交錯を味わいたい方、時代物の人情噺に興味がある方にぜひ聴いていただきたい一作です!
高橋お伝国本はる乃

明治期に起きた実在の女性殺人事件を題材にした作品ですが、浪曲では単なる「毒婦」として描くのではなく、難病の夫を救いたい一心で名医を求めて東京へ向かう貞女として人間讃歌のテーマを込めて描かれています。
襲いかかる男たちを避けながら必死に夫のために行動するお伝の姿を、語りと三味線の節回しで情感豊かに表現した物語は、愛憎と哀しみが交錯する人間ドラマとして胸を打ちます。
2021年6月に浅草・木馬亭の定席興行で初演され、国本はる乃さんが師匠から許しを得て継承した演目です。
歴史上の人物を新たな視点で描き直した本作は、浪曲という伝統芸能の奥深さと、一人の女性の切ない人生を知りたい方におすすめの一席といえるでしょう。