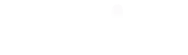【音楽教育をもっと楽しく】子どもの成長が目に見えるリトミックの魅力
最近、ちまたで小さなお子さんを対象としたリトミック教室が増えてきたのをご存じですか?
「え、なにそれ?
新手の幼児教育?」というアナタに、今日はリトミックの魅力をたっぷりお伝えしていきます!
リトミックってなに?
リトミックとはスイスの作曲家・音楽教育家のダルクローズが考案した音楽教育法で、近年では単なる音楽教育としてだけではなく、お子さんの感性や知性、運動機能などを育むことを目的とした幼児教育として幅広く活用されています。
リトミックは、一見するとただ子どもたちが音楽に合わせて楽しく遊んだり踊ったりしているだけなのですが、その実はたくさんのねらいを盛り込んだ教育的プログラムのため、お子さんたちは知らず識らずのうちに内なる能力をどんどん伸ばしていきます。
リトミックってどんなことをするの?

それでは、リトミック教室では実際にどんなことをしてお子さんたちの能力をぐいぐい引っ張り上げているのかご紹介しましょう!
小さなお子さんでも簡単にできて楽しめる基本プログラム!
「歩いて、止まって!」
これは「歩く音楽」の最中にわざと音楽を止めて、「止まれ」という無言の指示を出します。
つまり、
- 音の有無を自主的に気づく(音を聞く=人の話を聞く基礎、集中力作り)
- 音止まる=自分も止まるというルールを知る、守る(協調性の土台作り)
- 動いていた体をピタッと止める(運動機能アップ!
)
というのが目的のプログラムです。
大人からするととても単純な「歩いて、止まって」の繰り返しですが、小さな子どもたちからするととても楽しい音楽遊びの一つです。
みんな最初は音楽が止まったことに気づかず歩き続けてしまったりしますが、だんだん慣れてくるとピタッと止まれるように。
そして、いつしか「今度はいつ音が止まるのかな?」とワクワク顔で音の停止を期待するようになります。
つまり、ルールのある遊びの楽しさに気づくわけです。
そうなれば、こっちのもの!
音に対する集中力はどんどん上がっていき、動から静への切り替えもビックリするほど上手になっていきますよ!
音楽遊びだけではなく工作もしたり!

http://www.photo-ac.com/
もちろん、いつも同じプログラムだと子どもたちが飽きてしまうので、随時、季節に応じたプログラムや工作を用意してお子さんの感性や知的好奇心をいっぱい刺激していきます。
音感だけではなく手先も鍛えていくよ!
「雨の日のお散歩 with 手作り傘」
これも「歩く音楽」をベースにしたプログラムですが、今度は「雨の音楽」も加えていきます。
プログラムは「お散歩に行こう!」→「あ!
雨が降ってきた!
濡れちゃうから走るよ!」という流れで、これも集中力&ルール意識&運動機能を鍛えていきます。
でも、このプログラムではもう一工夫して「雨の日のお散歩には傘が欲しいね!」と折り紙傘の製作にもつなげていきます。
そう、指先の訓練です!
「指先を鍛えれば、いつまでもボケない!」と言われるくらい指先と脳は密接な関係にあり、指先を鍛えれば脳の活性化にもつながります。
なので、教室にもよりますが、折を見ては音楽遊びだけではなく製作なども入れているリトミック教室は多いんです。
ちなみに、わたしの教室でこのプログラムをやった時は、こんな傘を折り紙とストローで作りました。
 これ、一見むずかしそうに見えますが、年長さんくらいなら2~3分でささっと作れちゃいます。
これ、一見むずかしそうに見えますが、年長さんくらいなら2~3分でささっと作れちゃいます。
一人で作るのが難しい年齢の子にはあらかじめ大部分を作っておいて、傘の飾りつけとしてシールを貼ってもらうなど、できる範囲での製作を楽しみます。
ちなみに「シールを貼る」という動作は指先の訓練にうってつけなので、うちの教室ではよくやっています。
そして、その際にはいくつか気を付けてるポイントは、
- 「5枚貼ってね!」など最初から枚数を決めておき、一緒にシールの数を数える。
(数の概念を覚える)
- 「目印の上に貼ってね!」など、はる場所を決めておく。
(狙いをピンポイントでとらえる指先の微妙なコントロールを覚える)
などなどです。
どんなときも、リトミックは教育的ねらいを忘れません!
そうやって各自で作った思い思いの製作物を持ちながらリトミックをすると、子どもたちはより熱中してプログラムに入り込むようになり、リトミック効果は倍増!
面白いほど子どもたちはぐんぐん成長していきます!
子どもの笑顔とやる気を楽しく引き出して、それを自然と成長につなげていくリトミック。
音楽教育だけではなく、知育だけでもない。
それがリトミックの魅力です。