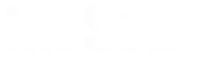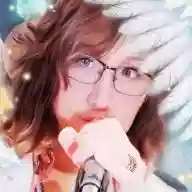【昭和50年代】邦楽のヒット曲まとめ
昭和50年代と言えば、日本が見事に第二次世界大戦からの戦後復興を果たし一気にバブル経済へと向かう…そんな活気に溢れた時代でした。
音楽関連でも、シンセサイザーやシーケンサーの開発~普及、マルチトラックレコーダーの高性能化等、音源制作でそれまでになかったサウンドや表現手法がたくさん生まれた時代だったように思います。
そんな時代背景を反映してか、ヒット曲もまさに百花騒乱!! 演歌からニューミュージックまで非常に多岐に渡るジャンルのヒット曲が生み出されました。
そんな群雄割拠の中、生き抜いて現代まで聴き継がれる名曲の数々、ぜひお楽しみいただければと思います。
- 昭和40年代の日本のヒット曲
- 50代におすすめのいい歌。邦楽の名曲、人気曲
- 70年代懐かしの邦楽アイドルの名曲・ヒット曲
- 1960年代懐かしの邦楽ヒット曲。昭和の人気懐メロ集
- 60年代懐かしの邦楽ポップスの名曲・ヒット曲
- 昭和のかっこいい曲。色気や情熱、渋さが光る昭和の名曲
- 今こそ聴いてほしい!日本を明るくした昭和の元気ソングたち
- 人気の昭和ポップス。色褪せないヒット曲
- 50代の方が聴いていた邦楽のダンスミュージック。懐かしの名曲
- 懐かしくて新鮮!?1970年代、80年代の懐かしの邦楽ロックの名曲
- 心に響く、昭和の泣ける名曲
- 懐かしすぎて新しい?高度経済成長期の日本を彩った昭和レトロの名曲
- 【懐メロ】昭和世代にヒット!女性歌手の歌う名曲・人気曲
【昭和50年代】邦楽のヒット曲まとめ(1〜10)
君は薔薇より美しい布施明

布施明さんの通算42作目のシングルで、リリースは1979年(昭和54年)1月。
1979年度春のカネボウ化粧品のコマーシャルソングに起用されていました。
ちなみに作曲を担当されたのは、当時飛ぶ鳥を落とす勢いだったゴダイゴでキーボードを担当されていたミッキー吉野さん。
バックトラックの演奏にもゴダイゴのメンバーさんたちが参加されています。
まさに春の陽射しを感じさせるような明るく爽やかなメロディの上に、布施さんの少しカンツォーネ風でダイナミックなボーカルが映える名曲です。
こういうスタイルのシンガーさんって、今はあまり見かけないので、そういう意味でも今の時代にあらためて再評価されてもいい楽曲なのではないでしょうか。
UFOピンクレディー

昭和のビッグアイドル、ピンクレディーの6作目のシングルで1977(昭和52年)年12月リリース。
10週連続オリコンチャート1位を獲得し、ミリオンヒットを記録しました。
筆者はこの曲のリリース当時、小学生でしたがクラスの女の子たちが列をなしてこの曲を歌って踊っていたのを覚えています。
ピンクレディーのお2人の卓越した歌唱力もさることながら、まさにUFOの飛来を表現するようなシンセサイザーのサウンドがとても新鮮に響きました。
読者の皆さんもこの曲を久しぶりにカラオケ等で歌って踊ってみると楽しいかもしれないですよ?
贈る言葉海援隊
武田鉄矢さん率いる海援隊の通算16作目のシングルで、1979年(昭和54年)11月リリース…と、そんな説明をするよりも、昭和の大ヒットドラマ「3年B組 金八先生」第一シリーズの主題歌と言った方が早いですよね!
筆者は同番組の放送当時、まだ小学6年生でしたが、小学校の卒業式でこの曲が流された途端に涙が溢れ出たことを今でもはっきりと覚えています。
当時をリアルタイムで過ごされた方の中には、同じようなご経験のある方もきっと多いのでは?
そんなことからも、リリースから40年以上経った今でも、卒業式の定番ソングのひとつになっているようですね。
とても暖かい昭和の名曲です!
【昭和50年代】邦楽のヒット曲まとめ(11〜20)
北の宿から都はるみ

都はるみさんの通算67枚目のシングルで、1975年(昭和50年)12月リリース。
これはもう演歌、昭和歌謡の名曲として時代を超えた評価を得ている楽曲ですね。
売り上げとしても140万枚以上を記録する大ヒット曲となっています。
切ないメロディと聴いているだけで情景が浮かんでくるような歌詞を都はるみさんが非常に高い歌唱力、歌唱表現力で切々と歌い上げています。
これからの世代の方たちにもぜひ伝えていきたい名曲です!
テクノポリスイエローマジックオーケストラ(YMO)

イエローマジックオーケストラ(YMO)のファーストシングルで1979(昭和54年)年10月リリース。
おそらくボコーダー(マイクを通した声を加工するシンセサイザー)で作られたと思われる「トキオ」と言うワードのサウンドがとても印象的で、筆者は当時、FMラジオで流れていたこの曲を聴いて、すぐにレコード屋さんにレコードを買いに走ったのを今でも覚えています。
今、本稿を書くために聴いてみても、当時のアナログシンセサイザーのサウンドはとても魅力的だったなーと感じますね。
今のデジタルシンセサイザーにはない、何処か有機的な表現力を感じてしまいます。
日本のテクノポップの名曲、ぜひお楽しみくださいませ!
微笑みがえしキャンディーズ

これもまた昭和のビッグアイドルグループだった、キャンディーズの活動期間内ラストシングルで1978(昭和53年)年2月リリース。
ラストシングルとして制作された楽曲だけあって、その内容はまさにキャンディーズの集大成と言えるもので、歌詞の随所に過去のヒット曲のタイトルが散りばめられていたり、曲中の振り付けにもそれらの楽曲で使われていた振り付けをモチーフにしたものが多く取り入れられています。
メジャーキーの明るい楽曲ですが、それでも聴いていると何処かもの悲しさを感じさせてくれるところもなかなかニクい一曲ですね!
キャンディーズのお三方の素晴らしいコーラスワークも秀逸です!
与作北島三郎

北島三郎さんのシングルで、1978年(昭和53年)3月リリース。
これはもう当時をリアルタイムで過ごした方なら誰もがお耳にされたことのある昭和の名曲でしょう!
民謡に近いようなシンプルなメロディと歌詞の中に出てくる、とてもインパクトのある擬音等の数々、そして北島さんの卓越した歌唱力によって、聴く人の年代を超えた支持を得てロングセラーの大ヒット曲になりました。
北島さんの他にも何人もアーティストにカバーされたり、この曲のヒットにインスパイアされたと思われるゲームなども発売され、そんなことからもこの曲の影響力を強く感じさせてくれます。
擬音の部分だけを一緒に歌ってみるのも楽しい昭和の名曲です!