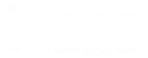【本日のピアノ】繊細な音色で紡がれる珠玉の名曲・人気曲
ピアノのために作られた作品でなく、ピアノ用にアレンジされた作品など、ピアノ演奏で親しまれている楽曲は、演奏形態やジャンルを問わず無限に存在します。
本記事では、そんなピアノ音楽のなかから、今日オススメしたい名曲を集めました。
掲載楽曲は毎日更新されますので、さまざまな作品でピアノの音色を存分に楽しみたい方は、ぜひこまめにチェックしてみてください。
たくさんの曲に触れながら、お気に入りリストを増やしていきましょう!
- 切なく美しい!おすすめのピアノ曲まとめ
- ピアノで弾けたらかっこいい!魅力抜群の名曲たちをピックアップ
- 【ピアノの名曲】聴きたい&弾きたい!あこがれのクラシック作品たち
- かっこいいジャズピアノ。定番の人気曲から隠れた名曲まで
- 【2025】ピアノが美しい感動の洋楽。最新の名曲まとめ
- 【クラシックピアノ名曲】涙なしでは聴けない感動する曲を厳選
- 【大人向け】ピアノ発表会にオススメ!聴き映えする名曲を厳選
- 【クラシック】有名ピアノ作品|一生に一度は弾きたい珠玉の名曲たち
- 【現代曲】ピアノの不思議な響きに惹かれるクラシック作品を厳選!
- 【和風のピアノ曲】日本らしさが心地よいおすすめ作品をピックアップ
- 【初級】大人のピアノ初心者におすすめ! 美しい&おしゃれなピアノ曲
- 【ワルツの名曲】ピアノのために書かれたクラシック作品を一挙紹介!
- 【ピアノ連弾×J-POP】超絶かっこいいピアノ連弾のアレンジを一挙紹介
【本日のピアノ】繊細な音色で紡がれる珠玉の名曲・人気曲(21〜30)
パッヘルベル:カノン松田華音

6歳の時にロシアへ渡り、名門音楽学校に入学。
幼い頃から才能を発揮していたこともあり「ロシアの神童」とも呼ばれていた人物です。
香川県高松市出身。
また、その見た目の美しさから「美しすぎるピアニスト」としても注目を集めています。
Baby, God Bless You清塚信也

ユニークで親しみやすい人柄でテレビ番組でも活躍している、ピアニストの清塚信也さん。
2020年の紅白歌合戦では、島津亜矢さんの伴奏をつとめ話題となりました。
『Baby, God Bless You』は、TBS系金曜ドラマ『コウノトリ』のメインテーマ曲として2015年にリリースされた楽曲。
歌詞もない、ピアノの演奏のみですが、こんなにも人の心を動かすのかと感動する、心あたたまる曲です。
どんなシーンにも合う曲なので結婚式などの演奏にもオススメです。
ピアノソナタ 第0番「奏鳴」角野隼斗

新世代のピアニストとして注目を集める角野隼斗さん。
クラシックの技術と現代的な感性を融合させた角野さんの作品は、多くの音楽ファンを魅了しています。
本作は、ソナタ形式を用いながらも、即興的な要素や自由な表現を取り入れた意欲作。
ラフマニノフ作品をほうふつとさせる壮大な響きと、ジャズの影響を感じさせる斬新なアプローチが見事に調和しています。
2020年12月に発表された本作は、角野さんの音楽的な探求心と豊かな感性が詰まった1曲。
クラシックの枠にとらわれない新しい音楽表現に興味がある方にぜひ挑戦していただきたい作品です。
ハナミズキ一青窈

印象的なピアノイントロの楽曲は数多く存在しますが、一青窈さんの『ハナミズキ』もそのうちの一つといえるのではないでしょうか。
オリコンシングルチャートで第4位にランクインした一青窈さんの代表作品であり、カラオケでも大人気のこの曲。
唯一無二の歌声を持つ一青窈さんを支えるピアノ伴奏もステキで、演奏するポジションをパートごとに高音域や低音域と使いわける細やかさが、楽曲のサウンドを支えています。
ぜひ挑戦して、弾き語りのレパートリーにしてほしい楽曲です!
Merry Christmas, Mr Lawrence坂本龍一

第二次世界大戦をテーマに1983年に日本で公開された映画『戦場のメリークリスマス』のメインテーマです。
音楽プロデューサーやミュージシャンとして幅広く活躍する坂本龍一さんが手掛けたこの曲は、英国アカデミー賞作曲賞をはじめとする国内外の賞を数多く受賞し、世界的にも有名となりました。
どこか切なく繊細なメロディーが心の奥深くに染みていくのをじっくり味わいながら、1音1音丁寧に、静かに降り積もる雪をイメージしながら演奏しましょう。
多分、風。岡崎英美

エレクトリックバンド、サカナクションのキーボード担当です。
北海道小樽市出身。
ロックバンドという枠にとらわれないサカナクションの音楽性になくてはならない存在です。
ラジオ番組で音楽講座のコーナーを担当したことも。
空中裁判日食なつこ

弾き語りスタイルのシンガーソングライター、日食なつこ。
その感情的な音楽性はピアノの伴奏、というよりもロックロールを感じさせます。
そのセンスが認められ、日本人として初めて「Spotify Session」に選出されました。
ピアノ連弾デュオとして有名なレ・フレールから影響を受けています。