青森の民謡・童謡・わらべうた|津軽や八戸に息づく心に響く日本の歌
豊かな文化と芸能の伝統が息づく青森県。
津軽や八戸の地には、情感豊かな民謡の調べが今も響きわたります。
津軽三味線の力強い音と相まって、青森の民謡は私たちの心に深く訴えかけてきます。
本記事では、山々や海、厳しい気候が育んだ人々の暮らしのなかから生まれた「青森の民謡、童謡、わらべうた」を厳選。
時代をこえて大切に歌いづ画れてきた名曲をご紹介します。
青森県の心の歌と呼べる楽曲の世界へ、耳を傾けてみませんか?
青森の民謡・童謡・わらべうた|津軽や八戸に息づく心に響く日本の歌(1〜10)
津軽三下り

民謡のなかで最もテンポや間の取り方が難しいといわれる『三下り』。
民謡界ではかなりの上級者でないと歌いこなせない、弾きこなせない歌として知られています。
民謡を得意とする演歌歌手の福田こうへいさんなどの演奏を耳にすると、いかに上級者かわかりますね。
りんごのひとりごと

真っ赤な果実が自らの旅路を語る、とても愛らしい視点で描かれた童謡です。
北国の畑から汽車に揺られ都会の市場へと向かう様子が、リズム感あふれる表現で歌われています。
作詞を手掛けた武内俊子さんが病床で見舞いのリンゴから着想を得た背景を知ると、自由な世界への憧れや郷里への思いがより深く感じられるかもしれませんね。
この楽曲は1940年2月に河村順子さんの歌声でレコード化された作品です。
JR五能線藤崎駅では入線メロディにも採用され、青森を色濃く感じる1曲として親しまれています。
ホーハイ節

ヨーデルのようにどこまでも伸びる裏声の掛け声が大変印象的な、津軽地方の民謡。
山の草花や実り豊かな稲穂、そして腰の痛みに耐えながら働く母の姿など、厳しい自然とともに生きる人々の日常が描かれています。
この楽曲の最大の魅力は、祈りのように響く澄んだ裏声と、大地を踏みしめるような地声の美しい対比。
この抑揚が、聴く人の心をぐっとつかむのです。
津軽三味線奏者の中村滉己さんは、2023年4月リリースのEP『歩‑AYUMI‑』で本作を披露。
また、地酒ブランド『豊盃』のテーマソングとして現代的にアレンジされるなど、楽しみ方も広がっています。
南部あいや節

青森県南部地方を代表する民謡の一つ。
港町の酒席や祝宴の場で、手踊りをともなう楽しい唄として広く親しまれてきました。
明るくリズミカルな旋律と、唄の冒頭に入る威勢の良い掛け声が印象的ですよね。
三味線の軽快な音色と合わさり、人々が輪になって踊るにぎやかな情景が目に浮かぶようです。
青森に生きる人々によって口伝えで大切に歌い継がれきた本作を通して、青森の港に根付く、人々の陽気な心意気に触れてみてはいかがでしょうか。
南部よされ節

青森県南部地方を代表する、にぎやかな座敷踊りの民謡です。
南部七大民謡の一つに数えられる本作は、津軽三味線が刻む軽快なリズムと、陽気な掛け声が特徴的。
聴いているだけで自然と体が動き出してしまいそうですよね。
「よされ」という言葉には「よしなさい」といった控えめな意味も含まれ、ただにぎやかなだけでなく、どこか品のある趣を感じさせます。
宴の席で女性たちが手首を柔らかく使い、優雅に踊る情景が目に浮かぶようです。
この歌に耳を傾け、人々が集う温かなひとときに思いをはせてみてはいかがでしょうか。
南部甚句
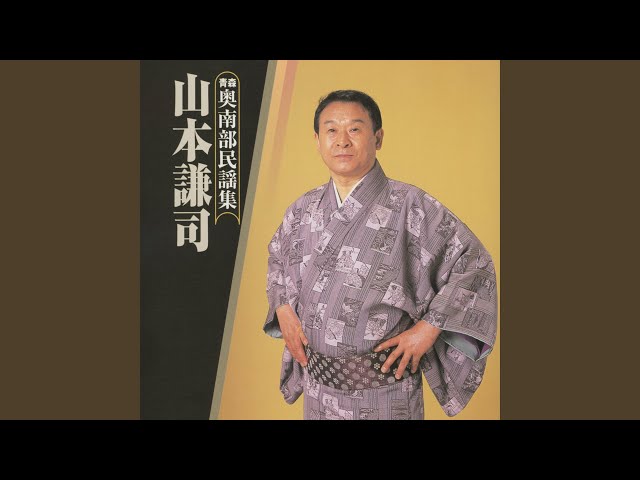
青森県南部地方で100年以上にわたり踊り継がれてきた、代表的な手踊り唄です。
江戸時代天保期に江戸で流行した粋な歌が、北の地に伝わり、この地の言葉や風土と溶け合って定着したといわれています。
七七七五の短い詞の中に、労働の合間の息抜きや日々の暮らしの機微が巧みに織り込まれ、聴く人の心に温かく響きます。
本作は特定の作者を持たず、人々の間で大切に歌い継がれてきました。
現代では、地域の盆踊り唄を集めたアルバムに収録されたり、地域のイベントで演奏されたりするなど、この地の芸能に欠かせない1曲となっています。
津軽ばやし
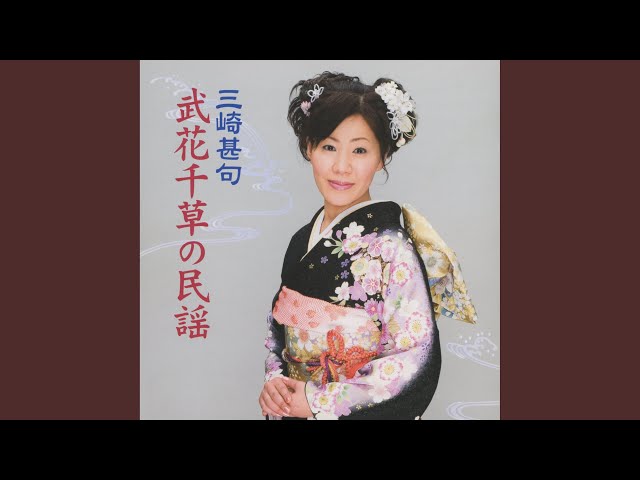
新潟県の村上方面へ出稼ぎに行った津軽の人たちが、村上の盆踊りを持ち帰って歌ったのが始まりとされている『津軽ばやし』。
酒宴の歌として親しまれていたこの民謡は、『村上甚句』が原曲となっており、戦前は津軽芸人が客寄せに歌っていたそうです。
当初はもともと新潟民謡だったためか『越後甚句』と呼ばれていましたが、戦後に現在の曲名で広く知られるようになりました。





