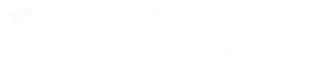こどもの日に楽しめるゲームや遊び。工作遊びも
5月5日は「こどもの日」。
以前は「端午の節句」と呼ばれていましたが、子供の健やかな成長を願う「こどもの日」として、近年は定着してきましたね。
まだ男の子のお祝いの日という印象が強いですが、実は性別を問わずに全ての子供をお祝いし、生んでくれたお母さんに感謝する日でもあるのです。
この記事では「こどもの日」にぴったりの遊びやレクリエーションゲームを紹介します。
こどもの日やこいのぼりなどにちなんだゲームなどをたくさん紹介しています。
ご家庭はもちろん、保育現場でのお祝いの際に、ぜひ参考にして遊んでみてくださいね!
- 【子供会】簡単で楽しい室内ゲーム。盛り上がるパーティーゲーム
- 【保育】こどもの日に盛り上がる遊び・出し物
- 【こどもの日】手作りできる鯉のぼりのアイデア
- 【こども向け】放課後デイサービスで楽しむ、室内ゲームのアイデア特集
- こどもの日にオススメのゲーム。盛り上がるパーティーゲームも
- お祭りで盛り上がるゲーム。子供たちが楽しめるアイデア
- 昔の遊び。楽しいこどもあそび
- こどもの日にオススメ!手作り兜アイデア集【5月5日】
- 【子供向け】本日の手作り工作アイデア集
- 【親子レク】親子で楽しむレクリエーション、ゲーム。運動会にも
- 関西の子供の楽しい遊び。レクリエーションゲーム
- 【こども向け】英語であそぼ!楽しいレクリエーションやゲーム特集
- 【子ども向け】5月に楽しめる簡単な折り紙のアイデア
こどもの日に楽しめるゲームや遊び。工作遊びも(21〜30)
フラフープこいのぼり

フラフープにつかまって、大人に引きずってもらうという単純な遊びを、ポールにはためくこいのぼりにみたてています。
お洋服は汚れますが、腕の力がきたえられるので、体の発達にもいい影響がありそうですね。
子供は歩かずに移動する遊びが大好きなので、大喜びでフラフープにぶらさがってくれると思います。
大人は中腰になり、力もいるので腰痛や脱臼に注意してください。
箱の中身はなんでしょう?

レクリエーションなどでも定番となっている箱の中身はなんでしょうゲームは、その時々でお題が変わるため飽きずに楽しめるゲームですよ。
お子様が好きなおもちゃや端午の節句にちなんだ食べ物など、こどもの日らしいお題を準備すればイベントとしても楽しめるのではないでしょうか。
ただし、過激なバラエティー番組などで見かける危険なものや生き物などはゲーム自体を怖がってしまうため避けましょう。
出かけられない時に室内ならではの楽しみ方ができる、おすすめのゲームです。
こどもの日に楽しめるゲームや遊び。工作遊びも(31〜40)
紙相撲

子供のころ、誰もが一度は遊んだことがあるのではないでしょうか?
箱の上に紙で作ったお相撲さんを乗せて箱の端をトントンたたき、お相撲さんを動かし勝負する遊びです。
土俵は簡単な作り方から凝ったものまでたくさんありますが、ただの箱だけでも大丈夫です。
こどもの日なので、お相撲さんの代わりにこいのぼりを描いてもいいですね!
絵合わせゲーム

同じ絵柄を2枚用意してダンボールに貼り付けます。
始めは絵柄を表に向けておいてどこに何があるかを覚えます。
裏返して同じ絵柄の場所を思い出しながらめくっていきます。
そろったカードを多く取れた人の勝ちです。
カードは自分で絵を描いても楽しいので、こいのぼりやかぶと、五月人形やしょうぶなど、こどもの日らしい絵柄にしてもいいかもしれませんね!
こいのぼり鬼ごっこ

5月を迎えると庭先などで飾られる、こいのぼりをテーマにした鬼ごっこです。
幼稚園や保育園の庭や運動場など、広い空間でトライするのがオススメです。
まずは、こいのぼりのシルエットをイメージした模様を線で描きます。
オニと逃げる人を線上に配置して、追いかけっこするというもの。
オニにタッチされたら、こいのぼりの絵の中にしゃがんでうろこになりましょう。
ほかの子供がうろこを触ると復活できるというルールです。
最後まで、逃げ切ったら子供たちの勝利。
子供たちが助け合いながら取り組むことで、コミュニケーションも取れる遊びです。
春の暖かい陽気につつまれながら、5月の季節感を体験できる鬼ごっこにトライしてみてください。
こいのぼりのリズム遊び

こいのぼりにちなんだ歌でリズム遊び!
みんなで手をつないでまわったり、手をたたいたり、足踏みしたり、さまざまな振り付けで、子供たちが主役の1日を楽しく過ごしましょう。
こいのぼりや端午の節句にちなんだ歌を歌うのは、おそらく1年のうちで、5月5日当日やこどもの日を迎えるまでの数日間だけ。
せっかくなら、いつもやっているリズム遊びや手遊びを、こどもの日バージョンで楽しんでみるのも新鮮でよいのではないでしょうか?
兜とこいのぼりのリース

こいのぼりと兜、端午の節句を象徴するモチーフを使って作る手づくリリースです。
兜のモチーフが入っているリース、ミニこいのぼり。
こいのぼりのポール、ポールの先に取り付ける風車のパーツをそれぞれ折り紙で作り、貼り合わせていきます。
つり下げ用のひもを取り付ければできあがりです!
それぞれのパーツは、シンプルな折り方で子供たちと一緒に作ったり、複雑なものだけ先生や保護者の方が先に作っておいたり、すべてのパーツを用意して置き貼り合わせるのを子供にお任せしたり、子供たちに合わせて作り方を工夫してみてくださいね。