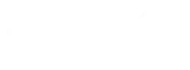【運動会BGM】会場を盛り上げる定番のクラシック曲をピックアップ
運動会のBGMには有名なクラシックの曲がたくさん使用されていますが、「メロディを鼻歌で歌えるけど、曲名がわからない曲」も数多くあるのではないでしょうか?
そこで本記事では、運動会のBGMで流す曲をお探しの方に向けて、オススメのクラシックを一挙に紹介していきます!
聴けば走り出したくなるあの曲から行進にぴったりなあの曲まで、定番曲を網羅しましたのでぜひ参考にしてください。
どのシーンで流すかを考えながら曲を聴いてみてくださいね。
- 【運動会】かけっこに合う曲。子供たちが走りたくなる曲【定番&J-POP】
- 【行進曲・マーチ】運動会や体育祭の入退場にオススメの人気曲を厳選!
- 定番から人気の曲まで!運動会が盛り上がる音楽・BGMカタログ集
- 【運動会】リレーBGMにおすすめの疾走感あふれるナンバーを一挙紹介!
- 【行進・かけっこ・ダンス】運動会を盛り上げる元気ソング&最新曲
- 運動会にオススメの退場曲。駆け足の退場によく似合う楽曲まとめ
- 運動会・体育祭で盛り上がる曲ランキング【2026】
- 【運動会・体育祭】選手入場で盛り上がる曲
- 【ダンス曲】運動会や体育祭におすすめ!楽しく踊れる人気ソングを厳選
- 【運動会・体育祭BGM】感動の名曲&練習を支えてくれる応援歌
- 組体操におすすめの曲。演技を盛り上げる楽曲まとめ【2026】
- 【マーチ】ピアノで奏でる行進曲の名作をピックアップ!
- 【ダンシング玉入れ】運動会にオススメの玉入れの楽しい曲
【運動会BGM】会場を盛り上げる定番のクラシック曲をピックアップ(31〜40)
組曲「惑星」Op.32 第4曲「木星、快楽をもたらす者」Gustav Holst

グスターヴ・ホルストが手掛けたこの曲は、運動会の感動シーンを彩るのに最適な1曲。
荘厳で祝祭的なメロディが特徴で、聴くだけで感極まってしまうかも。
1914年から1916年にかけて作曲され、1918年9月に初演。
後に、イギリスの愛国歌やラグビーワールドカップのテーマ曲にも採用されるなど、幅広く親しまれています。
オーケストラ作品ですが、吹奏楽版の楽譜も出版されているため、運動会の開会式や閉会式での演奏にもピッタリ。
壮大なスケール感と感動的な旋律で、参加者全員の心に残る思い出を作れること間違いなしの楽曲です。
トリッチ・トラッチ・ポルカJohann Strauss II

ドイツの作曲家ヨハンシュトラウス2世が手がけたポルカ。
『トリッチ・トラッチ・ポルカ』とはドイツ語で女性のおしゃべりのことだそうです。
曲中にフルートの高音が響き、女性が高い声でしゃべっている様子がよく表現されていますよね。
テンポも速く軽快なリズムなので運動会にもオススメの楽曲です。
複数人で走るリレーや2人3脚、ムカデ競争などの団体競技に最適!
みんなで曲にのってテンポよく息を合わせて勝利を目指しましょう!
ワシントン・ポストJohn Philip Sousa
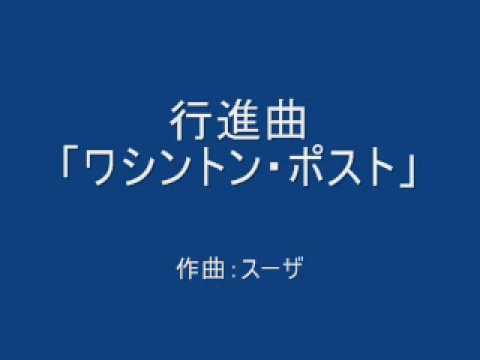
アメリカの作曲家であるジョン・フィリップ・スーザによる行進曲で、アメリカ人にはなじみのある楽曲です。
アメリカの有名な新聞『ワシントン・ポスト』のオーナーが、新聞紙上で募った作文コンテストの表彰式で流す音楽をスーザに依頼。
当時平凡な新聞だったそうですが、新聞と同じタイトルを曲に付けたことで注目を浴びたそうですよ!
堂々としたイントロから軽やかな金管楽器の音色、シンバルの音もポイントになっています。
運動会では入退場にオススメ!
この曲と一緒に歩けば自信をもって歩けそうですよね!
タイプライターLeroy Anderson

アメリカの作曲家であるルロイ・アンダーソンが手がけた、タイプライターを打楽器として用いたユーモアあふれる名曲です。
タイプライターは文字盤を打つことで字を紙に打ち付けて印字する現在のパソコンのような機械。
このタイプライターの打ち付け音と行の最後を知らせるチーンというベルの音、紙を固定するシリンダーを次行の先頭へ戻す時のザッという音を使っています。
ユニークな演出が楽しい楽曲なので、運動会の余興やお昼休憩、競技と競技の間のBGMとしてオススメです!
威風堂々 第1番Edward Elgar

イギリスの作曲家であるエドワード・エルガーが手がけた管弦楽のための行進曲。
第1番から第6番までで構成されており、第1番が最も有名な楽曲でもあります。
さまざまな管弦楽器の調和が耳にも体にも心地よいですよね!
曲の終盤ではゆったりとまさに威風堂々なたたずまい、行進曲ということもあり運動会では入退場や競技と競技の間のBGMにオススメです。
親子で楽しめる曲なのでお昼休憩のBGMに選曲するのもいかがでしょうか。
【運動会BGM】会場を盛り上げる定番のクラシック曲をピックアップ(41〜50)
双頭の鷲の旗の下にFranz Wagner

オーストリアの作曲家であるワーグナーによる楽曲で、冒頭から明るくリズミカルな曲調が続きます。
ワーグナーがオーストリア=ハンガリー帝国時代、軍の楽隊長であった頃に作曲したそうで曲のタイトルにある「双頭の鷲」はオーストリア=ハンガリー帝国の象徴でもあるそうです。
日本でも行進曲として運動会ではよく使われている楽曲。
曲を聴けば自然と軽やかに足を踏み出せるので、入場や退場のBGMとして選曲してみてはいかがでしょうか。
ラデツキー行進曲Johann Strauss I

オーストリアのウィーン出身の作曲家であるヨハンシュトラウスによる行進曲。
クラシック音楽の中でもとても人気の高い楽曲ですよね!
「ラデツキー」とはオーストリアの将軍の名前で、当時の激しい民族統一紛争を鎮圧したとても優秀な人物。
『ラデツキー行進曲』は鎮圧に成功した記念の祝典のために依頼された楽曲だそうです。
小太鼓で始まる軽やかなイントロから緩急のあるメロディが秀逸で1歩1歩楽しく行進できますね。
運動会の入退場にはぜひこの曲を選曲してみてはいかがでしょうか。