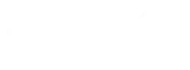【運動会BGM】会場を盛り上げる定番のクラシック曲をピックアップ
運動会のBGMには有名なクラシックの曲がたくさん使用されていますが、「メロディを鼻歌で歌えるけど、曲名がわからない曲」も数多くあるのではないでしょうか?
そこで本記事では、運動会のBGMで流す曲をお探しの方に向けて、オススメのクラシックを一挙に紹介していきます!
聴けば走り出したくなるあの曲から行進にぴったりなあの曲まで、定番曲を網羅しましたのでぜひ参考にしてください。
どのシーンで流すかを考えながら曲を聴いてみてくださいね。
- 【運動会】かけっこに合う曲。子供たちが走りたくなる曲【定番&J-POP】
- 【行進曲・マーチ】運動会や体育祭の入退場にオススメの人気曲を厳選!
- 定番から人気の曲まで!運動会が盛り上がる音楽・BGMカタログ集
- 【運動会】リレーBGMにおすすめの疾走感あふれるナンバーを一挙紹介!
- 【行進・かけっこ・ダンス】運動会を盛り上げる元気ソング&最新曲
- 運動会にオススメの退場曲。駆け足の退場によく似合う楽曲まとめ
- 運動会・体育祭で盛り上がる曲ランキング【2026】
- 【運動会・体育祭】選手入場で盛り上がる曲
- 【ダンス曲】運動会や体育祭におすすめ!楽しく踊れる人気ソングを厳選
- 【運動会・体育祭BGM】感動の名曲&練習を支えてくれる応援歌
- 組体操におすすめの曲。演技を盛り上げる楽曲まとめ【2026】
- 【マーチ】ピアノで奏でる行進曲の名作をピックアップ!
- 【ダンシング玉入れ】運動会にオススメの玉入れの楽しい曲
【運動会BGM】会場を盛り上げる定番のクラシック曲をピックアップ(21〜30)
フニクリ・フニクラLuigi Denza

聴きなじみ深いメロディーに体が自然とリズムを取ってしまいます!
こちら『フニクリ・フニクラ』は、もともとはイタリアの鉄道運営会社が作曲家のルイージ・デンツァへ依頼して制作された、鉄道の宣伝ソング。
「世界最古のCMソング」なんて呼ばれているんですよ。
日本では童謡『鬼のパンツ』など替え歌として親しまれていますよね。
にこやかかつ牧歌的な雰囲気なので、行進曲や競技スピードがゆったりめなものにぴったりだと思います。
「くるみ割り人形」より トレパックPyotr Tchaikovsky

ロシアの作曲家チャイコフスキーによるバレエ楽曲。
テンポが速い曲で軽やかであり華やかさも感じられますよね!
少女クララがクリスマスの夜にプレゼントされたくるみ割り人形が、真夜中に美しい王子様となり王女になったクララをお菓子の国へ誘うというストーリーが表現された楽曲でもあります。
運動会にもよく用いられ、借り物競争や競技と競技の間などのBGMにオススメです!
耳に心地よいので親子で参加する競技にもぴったりですね。
フィドル・ファドルLeroy Anderson

明るくてにぎやかな雰囲気が、運動会を盛り上げるのにぴったりだと思います!
アメリカはマサチューセッツ州出身の作曲家、ルロイ・アンダーソンが手がけた『フィドル・ファドル』。
彼が「アメリカ軽音楽の巨匠」と呼ばれている理由が、この曲を聴くだけでわかってしまうんじゃないでしょうか。
それぐらいに軽快でポップなクラシックナンバーです。
徒競走には間違いなく合いますし、駆け足で移動する退場曲としても良さそうですね。
錨をあげてCharles Zimmerman

海軍兵学校のフットボールチームを鼓舞するために作られた、力強い管楽器とパーカッションの響きが印象的な行進曲。
チャールズ・A・ツィマーマンが1906年に作曲したこの楽曲は、誇り高き海軍の精神を見事に表現しています。
聴く人の背筋が伸びるような勇ましいメロディと力強いリズムは、新たな航海へと出発する瞬間の高揚感を見事に描き出しています。
1945年公開のミュージカル映画でタイトル曲として採用されるなど、アメリカ文化にも大きな足跡を残しました。
フットボールの応援曲として生まれた本作は、式典や入隊式などで広く演奏され、運動会のBGMとして使用しても勇気と希望を感じさせる楽曲として多くの人々の心を揺さぶり続けることでしょう。
歌劇「アイーダ」より「凱旋の合唱」「凱旋行進曲」Giuseppe Verdi

壮大なサウンドが特徴的なこの楽曲は、運動会の入場行進や表彰式にピッタリの1曲です。
勇壮なブラス演奏と力強い合唱が、勝利と栄光を祝福する雰囲気を醸し出しています。
1871年12月にカイロで初演されたオペラの一部として生まれ、以来多くの人々に愛され続けてきた本作は、フィリピン国歌にも影響を与えるなど、世界中で親しまれている曲でもあります。
運動会の開会式や閉会式で流せば、会場全体が華やかな雰囲気に包まれること間違いなし。
子供たちの士気を高めるだけでなく、保護者の方々にとっても心に残る思い出になるはずですよ。
熊蜂の飛行Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov

まるで坂道を転がり落ちていくような、スピード感のある主旋律が特徴の『熊蜂の飛行』。
ロシアの作曲家、リムスキー・コルサコフによって書かれました。
演奏速度の速さから超絶技巧曲としても知られている作品で「どれだけ速いテンポで『熊蜂の飛行』をギター演奏できるか」というギネス記録があるほどです。
本当に、熊蜂がぶんぶん飛び回っているイメージが湧く曲調なんですよね。
大勢で走り回るような競技の時にぴったりではないでしょうか。
カルメンGeorges Bizet

こちらはジョルジュ・ビゼーの歌劇『カルメン』第1幕の前奏曲にあたります。
1875年にオペラ・コミック座で演奏され親しまれました。
運動会ではリレーやかけっこのBGMとして一度は誰もが聴いたことがあるのではないでしょうか。
トットコトットコとスキップしたくなるような、ハネるリズムも聴いていて楽しいですよね。
なんだか気持ちだけでも足が速くなりそうな気がしてきます!
親子で協力して進む二人三脚のような競技にも良さそうですね。