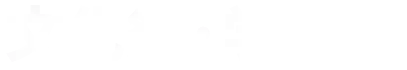びっくり!文化祭にオススメのトリックアートのデザイン
平面の絵が立体的に見えたり、見る位置によって絵が変化したりするトリックアート。
錯覚を利用した不思議なアートに、お子さんだけでなく大人もその世界観に引き込まれてしまいますよね。
そんなトリックアートを文化祭の展示に取り入れたい、と考えている方必見!
この記事では、文化祭で展示するトリックアートのオススメデザインを紹介します。
「手作りなんて難しそう」と思われるかもしれませんが、陰影のつけ方などを工夫すれば意外に手軽にできちゃうんです!
ぜひチャレンジしてみてくださいね。
- 文化祭にオススメのフォトスポット。フォトジェニックな空間を作ろう
- 高校の文化祭でインスタ映えするアイデア。喜ばれるフォトスポット
- 【文化祭】出し物の人気ネタランキング
- オシャレ&かわいくて目立つ!文化祭・学園祭の映える看板アイデア
- 【文化祭・学園祭の出し物に】迷路のオススメのアイデア・トラップ
- 【文化祭・学園祭】教室でできる珍しい出し物
- 【文化祭のアーチ】来場者をひきつけるインパクト大のアイデアを厳選!
- 【高学年向け】小学生の簡単な手品。驚き&感動のマジック
- 文化祭の展示作品にオススメの工作。会場装飾にもぴったりのアイデア
- 【ドッキリ】文化祭・学園祭にオススメなサプライズネタ
- 【写真映え抜群】文化祭・学園祭の飾り付け・装飾アイデア
- 映える!文化祭を彩る内装の装飾アイデア
- 高校生だから作れる!?文化祭のアトラクションアイデア
びっくり!文化祭にオススメのトリックアートのデザイン(11〜20)
地面の穴から浮世絵が!
思わず写真に収めたくなる!
地面の穴から浮世絵が!
のアイデアをご紹介します。
トリックアートといえば、人がアートの中に入り込んで撮影できるものもありますが、アートだけで成り立つデザインもありますよね。
今回は、浮世絵を使ったユニークなアイデアで来場者をあっといわせましょう。
投稿されている写真では、地面に穴があいているかのようなデザインが施されています。
穴の中には、おでんと一緒に、おでんが煮える鍋に落ちないように踏ん張る男性がいますよ。
ぜひ、取り入れてみてくださいね。
巨大な動物と記念撮影
夢のようなシチュエーション!
巨大な動物と記念撮影のアイデアをご紹介します。
「動物と視点を入れ替えてみたい!」「自分の体が小さくなって、世界を見てみたい!」という願望を持ったことのある方も多いのではないでしょうか?
今回は、まるで体のサイズが小さくなったような感覚が体験できる、ユニークなトリックアートを作ってみましょう!
投稿された写真は、ゴロンと寝転がる猫のおなかに乗る女性が映っていますね。
ぜひ、取り入れてみてくださいね。
忍者と遭遇
ドキドキ感のある写真が撮影できる!
忍者と遭遇のアイデアをご紹介します。
忍者と遭遇する場面は、現実では難しい話ですがトリックアートを活用することで、実現するのがおもしろいですよね。
投稿された写真は、2人組の女性が仕掛けのある壁から飛び出す忍者と、バッタリ出くわしたような瞬間を撮影しています。
非現実的な写真で、話題になること、間違いなし!
ユーモアのあるトリックアートを作りたいという方にオススメのアイデアですよ!
真実の口
印象に残る写真を撮影できる!
真実の口のアイデアをご紹介します。
映画『ローマの休日』といえば、『真実の口』を思い出す方も多いのではないでしょうか?
サンタ・マリア・イン・コスメディン教会の内部に飾られている『真実の口』は、イタリアのローマに訪れたら見てみたい有名な彫刻です。
映画の中では、ウソをついた人が『真実の口』に手を入れると、かまれて手が抜けなくなるというシーンがあり、そのワンシーンの再現が楽しめそうなトリックアートですね。
閉じ込められちゃった!?
大人数でも撮影できる!
閉じ込められちゃった!?
のアイデアをご紹介します。
トリックアートを撮影する際に、仕掛けの都合で1人しか映れないということもあるのでは。
今回は、4人でも撮影できるトリックアートを作ってみましょう。
投稿された写真は「人間用、ミニマシーン」と表記されたカプセルの中に、閉じ込められてしまったかのような仕掛けで撮影されています。
手前には、閉じ込められている様子を発見した人も映っているので、ユニークなストーリー性がおもしろいですよね。
重いものを持ち上げる
圧倒的な画力で、人を不思議な世界に連れて行ってくれるこちらのトリックアート。
こちらは、リアルな絵によって、前に立つ人を力持ちのように見せてしまう錯覚が楽しい参加型ギミックで、文化祭にオススメですよ。
立体的な重くて大きいものや、普通なら持ち上げられない筋肉モリモリの人間を丁寧に描くことで、その奇妙さを巧みに演出してくださいね。
筋肉を描くコツは、バランスとシルエットだそう。
人が立つ場所を調整しながら、しっかりと描きましょう。
びっくり!文化祭にオススメのトリックアートのデザイン(21〜30)
飛び出す文字

見た人が思わず「う〜ん」とうなってしまうような、文字を浮かせて見せる3Dトリックです。
まず、一点透視図法という技法を使って、一つの点から広がっているような角度をつけて文字を描きます。
定規などを使って丁寧に文字を描き、しっかりと濃い部分と薄い部分の色わけをしましょう。
下の影部分をこすってぼやかしておくのもポイント。
下の部分とつなげて、文字を切り取ってできあがり。
展示するときは、展示物と壁の間に少し距離を開けると、よりいっそう立体感が生まれますよ。