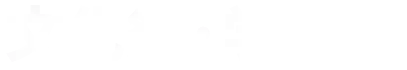びっくり!文化祭にオススメのトリックアートのデザイン
平面の絵が立体的に見えたり、見る位置によって絵が変化したりするトリックアート。
錯覚を利用した不思議なアートに、お子さんだけでなく大人もその世界観に引き込まれてしまいますよね。
そんなトリックアートを文化祭の展示に取り入れたい、と考えている方必見!
この記事では、文化祭で展示するトリックアートのオススメデザインを紹介します。
「手作りなんて難しそう」と思われるかもしれませんが、陰影のつけ方などを工夫すれば意外に手軽にできちゃうんです!
ぜひチャレンジしてみてくださいね。
- 文化祭にオススメのフォトスポット。フォトジェニックな空間を作ろう
- 高校の文化祭でインスタ映えするアイデア。喜ばれるフォトスポット
- 【文化祭】出し物の人気ネタランキング
- オシャレ&かわいくて目立つ!文化祭・学園祭の映える看板アイデア
- 【文化祭・学園祭の出し物に】迷路のオススメのアイデア・トラップ
- 【文化祭・学園祭】教室でできる珍しい出し物
- 【文化祭のアーチ】来場者をひきつけるインパクト大のアイデアを厳選!
- 【高学年向け】小学生の簡単な手品。驚き&感動のマジック
- 文化祭の展示作品にオススメの工作。会場装飾にもぴったりのアイデア
- 【ドッキリ】文化祭・学園祭にオススメなサプライズネタ
- 【写真映え抜群】文化祭・学園祭の飾り付け・装飾アイデア
- 映える!文化祭を彩る内装の装飾アイデア
- 高校生だから作れる!?文化祭のアトラクションアイデア
びっくり!文化祭にオススメのトリックアートのデザイン(21〜30)
どっちに回っているの?

文字やイラストが3Dに見えるアート作品は、見ている側も作っている側も純粋に楽しめますよね。
そんな錯覚画像のネタをたくさん展示するのも、文化祭にピッタリではないでしょうか。
イラストを切り取ってつるし、どちらに回っているのかわからなくなるようなアートや、飛び出して見える文字、浮いて見えたり、逆に深い穴が空いたりしているように見えるイラストなど、楽しい仕掛けがいっぱいのマジックアート。
黒いペンと鉛筆、ハサミがあればできるので、たくさん作ってみてくださいね!
名画とのコラボ
世界に数多くある名画をモチーフに、トリックアートを作っていきましょう!
例えば、レオナルド・ダ・ヴィンチの名作『モナ・リザ』の口元をぐにゃりと曲がったような笑顔にするなど。
最初にトリックアートにしたい部分を決めておき、それ以外の部分をもともとの作品を模写して描き上げます。
最後にトリックアート部分を描き足せばOK。
人物がモチーフの名画は、トリックアートとの相性がいいのでオススメです。
周りと相談しながら、どの題材を選ぶか考えてみてくださいね!
吸い込まれそうな穴

動画サイトなどでもよくネタに使われることの多い「吸い込まれそうな穴」。
例えば「家で飼っているペットがトリックアートを見やぶれるのか?」というような動画などで目にすることがあります。
この不思議な穴は、間をあけながら黒い長方形を円形に描いていくことで簡単に作れちゃうんです。
外側に向けて黒い長方形が大きくなるように描くのがポイント。
また、最後は中心部に影ができるように、ペンを横に向けてグラデーションになるようにグレーでぬっておきましょう!
これでまるで吸い込まれそうな立体的な穴の完成です。
手に穴が開く

省スペースの展示物として楽しめるトリックアートです。
とにかく絵が苦手という方でも取り組める手軽さが魅力!
まずは、適当なイラストを描き、その一部を手の上に乗るサイズのハート型や丸型に切り取り、一部に薄く影を描きます。
それから手のひらに、赤いカラーペンで血に見えるようにハート型や丸型の周りを塗れば、手を貫通したように見えるイラストのできあがり。
実際にスッと手を差し出すのもよし、前もって撮った写真を展示しておくのもいいですね。
物が浮いているように見える

物が空中に浮いているようなトリックアートは、文化祭でもウケそうなインパクト抜群のアイデア。
作り方はシンプルで、まずは斜めの線を使いつつ立方体を描きます。
このときに奥行きの部分は、斜めの線が平行になるようにしっかりそろえておくのがポイント。
次に、平らな面に色つきの正方形と白い正方形が交互に並ぶように配置していきます。
色は茶色や赤などを使って側面にも塗ればOK。
最後に黒色を指で伸ばしながら影をつけていけば完成です!
遠近感がおかしく感じる部屋
大きくて、部屋に入るのがギリギリかに見える巨人と、対照的に小人に見える錯視型トリックアートです。
実際に自分たちが中に入って体験できるトリックアートとして有名な「エイムズの部屋」といわれるもので、指定された位置から普通の四角い部屋のように見えますが、実際の部屋の形はいびつな四角形。
そのため見ている人は距離を錯覚し、大きさの錯視が生じます。
部屋を作るのは少し難易度が高いですが、盛り上がることは必至なので、ぜひチャレンジしてみてくださいね!
危ない橋
下にぽっかりと空いたホールがあまりにリアルで、思わず絵の橋に乗ることさえためらってしまうようなトリックアートです。
こちらは、なんといっても穴の奥に広がる深く暗〜い闇や、高い空の上をいかにリアルに描けるかがポイント。
吸い込まれそうな大きな穴の場合は、黒の濃い部分と少し薄い部分の境界線をぼかしながら描いてくださいね。
お客さんが、一歩を踏み出すことを少し恐れながらもドキドキワクワクできる、スリリングさが絶妙な錯覚イラストですよ!