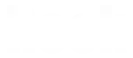【邦楽ポストロックのススメ】代表的なバンド、人気グループ
ポストロックというジャンルを聴き始めて間もないという方のほとんどは、洋楽を起点として作品をチェックしている最中だと思われます。
実はここ日本におけるポストロック・シーンは、世界的に評価されているバンドが多く存在しているという事実をご存じでしょうか。
彼らが試みた音作りは、実はメジャーでヒットしている楽曲の音作りにも大きな影響を与えています。
とはいえ基本的に商業的な音楽ではないからこそ、実際に探すとなると初心者の方であれば敷居が高いかもしれません。
そんな音楽ファンに向けて、今回の記事では日本のポストロックを代表するバンドたちを紹介しております。
邦楽ロックがお好きな方も、ぜひご覧ください!
- 【初心者向け】洋楽ポストロックの人気曲。おすすめの名曲まとめ
- 邦楽のエモの名曲。おすすめの人気曲
- 【邦楽】若手から伝説まで!日本の必聴オルタナティブロックバンド
- 2000年代の邦楽ロックバンドの名曲【邦ロック】
- 【感動】心が動くオススメのロックバラードまとめ
- 日本のプログレッシブロックバンドまとめ【前衛的】
- サーフミュージックの魅力。海の音色に誘われる極上の癒し空間
- 邦楽パンクの名曲。おすすめの人気曲
- 女性におすすめの邦楽ロックの名曲
- 邦楽ロックバンドのかっこいい曲。コピーバンドにオススメの曲まとめ
- ロックンロールな日本のバンド特集【邦楽ロック】
- 春に聴きたいロックの名曲、おすすめの人気曲
- 海外でも話題の3人組ロックバンド、マルシィの人気曲ランキング
【邦楽ポストロックのススメ】代表的なバンド、人気グループ(1〜10)
爆裂パニエさんtricot

フロントに女性3人、ドラマーのみ男性という4人組のtricotは、高度な演奏技術と複雑な楽曲展開、独自のポップネスを持った楽曲を武器として日本のみならず海外で高い評価を受けるバンドです。
2010年に中嶋イッキュウさん、キダ モティフォさん、ヒロミ・ヒロヒロさんの3人で結成され、翌年には初代ドラマーのkomaki♂さんが正式に加入、自身が運営するレーベル「BAKURETSU RECORDS」を始動させてインディーズ・シーンにおいて知名度を上げていきます。
2013年にはイギリスの老舗音楽雑誌「NME」に取り上げられるなど海外で評判を呼び、世K都市にはヨーロッパの複数の音楽フェスティバルに出演を果たすなどワールドワイドな活動を続け、2019年にはメジャー進出も果たしました。
彼女たちの音楽はとにかく個性的で、マスロック的な変拍子を多用した難解なバンド・アンサンブルで構成された楽曲ながらも、前述したように非常にポップでキャッチーなメロディが必ず盛り込まれており、マニアックな音楽性とJ-POP的な耳になじむ歌が、ごく自然に同居しているバランス感覚が絶妙なのですね。
そんな彼女たちはメジャー進出後の2020年に2枚のフル・アルバムを、2021年にはメジャー3枚目となるアルバム『上出来』を発表するなど、とどまることを知らない創作ペースにも驚かされます。
ポストロックと言われても難しそうで……といった敷居の高さを感じている方であれば、まずはtricotの音楽からポストロックの要素に親しんでみるというのも良い選択かもしれませんよ。
VIPRega

テクニカルで複雑な演奏やバンド・アンサンブルは好きだけど、やっぱり聴きやすいメロディがほしいという方にオススメのインストゥルメンタル・バンドが、2007年に結成された4人組のregaです。
2017年の活動休止までに4枚のアルバムをリリースしており、エモーショナルなインストゥルメンタル・ロックを愛する音楽ファンから熱狂的な支持を受けるバンドです。
2019年に活動を再開しましたが、残念ながらギタリストの四本晶さんが脱退してしまったようです。
そんな彼らの鳴らすサウンドは、高度な演奏技術に裏打ちされたインストゥルメンタル・ロックであり、最初から最後まで変化を続ける楽曲構成はたしかに複雑ではあるのですが、あくまでさらりと難解なことをやってのけるセンスが素晴らしいのですね。
何より彼らの最大の武器は、どの楽曲においても抜群にキャッチーなフックが多く盛り込まれているということでしょう。
冒頭で述べた意味はつまりそういうことであり、インストゥルメンタルに苦手意識を持っている方であればこそ、ぜひ一度は聴いて体感していただきたいサウンドなのです。
もちろん、LITEなどのバンドがお好きな方でregaを知らなかったという方も必聴ですよ!
atomjizue

「ジズー」と読む京都のインストゥルメンタル・トリオであるjizueは、卓越したテクニックとハイセンスなソングライティングを武器として海外ツアーなども精力的にこなす実力派バンドです。
2006年に結成、翌年にはピアニストの片木希依さんが加入して4人組として本格的な活動を開始した彼らはジャズやラテン、プログレッシブロックにポストロックの要素がちりばめられたサウンド展開し、クラブミュージックにも当たり前のように触れている世代ならではのセンスが光るサウンドがたちまち話題を集めます。
クラシックの素養を持つ片木さんのアグレッシブなピアノが時に叙情的に、時に攻撃的な旋律を奏でつつ、ロック的なダイナミズムも兼ねそなえた力強いバンド・アンサンブルは、オルタナティブロックを愛する方にも響くはず。
ライブ・パフォーマンスにも定評があり、フジロックなどの大型ロック・フェスティバルなどの参加や海外ツアーなども成功させています。
2019年には地元の京都市交響楽団を迎えてオーケストラとの共演も実現させており、幅広い分野で活躍している存在なのですね。
そんなjizueは2019年にドラマーの粉川心さんが脱退するという危機に見舞われますが、その後も活動ペースを緩めることもなくサポートのドラマーにfox capture planの井上司さんを迎え、冒頭で述べたように現在はトリオ編成として活動中です。
【邦楽ポストロックのススメ】代表的なバンド、人気グループ(11〜20)
Worn heels and the hands we holdenvy

一口にポストロックと言ってもその音楽性はバンドやアーティストによってさまざまですが、言葉を失うほどの壮絶なハードコア・サウンドからスタートし、深遠なポストロックの領域にまで達したenvyという存在は、邦楽ポストロックを深掘りしたい方にもぜひ推薦したいバンドです。
伝説的なバンドのBLIND JUSTICEを前身として1995年に結成されたenvyは、改名後のデビュー・アルバムとなった『Breathing and dying in this place…』の時点では長くて2分、曲によっては1分にも満たないカオティックなショート・チューンを軸としたハードコアを鳴らしていましたが、徐々に音楽性を変化させ、2001年に発表された大傑作サード・アルバム『all the footprints you’ve ever left and the fear expecting ahead – 君の靴と未来』では壮絶な日本語による叫びとドラマチックな轟音、複雑な楽曲展開で激情ハードコアの極限を提示、アンダーグラウンドのシーンにおいてすさまじい衝撃を与えたのです。
彼らの素晴らしさはこれだけのアルバムの後に、さらなる進化を遂げたことでしょう。
ポストロックが好きという方は、2006年にリリースされた通算4枚目のアルバム『a dead sinking story』以降のenvyをまずは聴いてほしいですね。
ポストロックやアンビエントといった要素を大幅に取り入れて、ドラマチックな長尺曲を中心に展開していく音世界は、根底にある精神は変わらずとも、より深い精神世界へと没入していくような展開を見せるのです。
中心人物のボーカリスト、深川哲也さんの脱退や再加入、他のメンバーの脱退劇など多くの困難を乗りこえた彼らは2002年代の今も3人組として活動を続けています。
日本のハードコア・シーンが生んだ孤高のバンドによる芸術的な作品群を、ぜひ手に取ってみてください。
雨ペトロールズ

椎名林檎さんが率いる東京事変の中で「浮雲」としても活躍するギタリスト、長岡亮介さんがボーカル兼ギタリストとして在籍するペトロールズは、もともとはヒップホップ・バンドをやっていたベーシストの三浦淳悟さん、ビジュアル系やメタルがルーツというドラマーの河村俊秀さんという個性的なメンバーによるトリオです。
2005年の結成以来、ライブを主戦場として会場で作品を手売りするといったようなDIYな活動を続けていた彼らは活動当初からインディーズ・シーンにおいて絶大な人気を誇り、初の全国流通版となったミニアルバム『Problems』がリリースされたのは212年のことなのですね。
徹頭徹尾インディーズでの活動にこだわる彼らはCDというスタジオ音源のフォーマットにあまり興味がないそうで、ライブで演奏してその変化を楽しんでいるというスタイルは、ライブ・バンドならではの音楽的態度だと言えそうです。
ジャンルとしてのポストロックはあくまで彼らの一面でしかなく、オルタナ・カントリーやファンク、ジャズにサイケデリックなど多くの音楽性を内包しつつも、ファルセットを使った長岡さんのボーカルによるメロディは聴きやすく、高い演奏技術に支えられたトリオ編成ならではの隙間のあるアンサンブルは、やはりライブで体験していただきたいですね!
風になるまでonsa

2000年代の邦楽インディーズ・シーンに詳しい方であれば、onsaの名前を記憶している人は多いのではないでしょうか。
2002年に東京は下北沢にて結成された4人組で、老舗音楽レーベル「UK.PROJECT」より作品をリリースして人気を博していたバンドです。
残念ながら2009年に解散していますが、アメリカのエモ、ポストハードコア、ポストロックといったインディー系のサウンドから影響を受けた繊細かつ緻密なバンド・アンサンブルが織り成す珠玉の楽曲群は、洋楽ファンからの注目を集めていましたね。
海外のバンドが来日した際にはよく前座を務めていたこともありましたから、そこで初めて彼らの存在を知ったという洋楽好きもいらっしゃるのでは?
ナイーブな少年性を宿したボーカリストの岡崎孝和さんの声、日本語で歌われる叙情的なメロディ、青春の輝きがそのまま形となって疾走していくようなサウンドは、限りなく「エモーショナル」としか言いようのない代物。
ポストロックとは少し違いますが、日本にも2000年代にこういうバンドがいたことはぜひ知っておいていただきたいですね。
余談ですが、ドラマーの大浦勝也さんは会社の代表を務めつつ、現在ミュージシャン支援プラットフォーム「unitive」を運営しているそうです。
PERSON! PERSON!!Mudy On The 昨晩

邦楽ポストロック・シーンにおいて大きな役割を果たした残響レコード所属、いわゆる「残響系」の代表的なバンドの1つにして、意味深かつパンチの効いたバンド名も気になるmudy on the 昨晩は、2006年に名古屋にて結成されたインストゥルメンタル・バンドです。
結成当初は大学生だったという若さながら、高い演奏能力を武器として強烈なライブ・パフォーマンスを展開、インディーズ・シーンにおいて注目を集めた彼らは、翌年の2007年には早くも強烈な海外勢がそろうライブ・イベント「EXTREME THE DOJO」に参戦するなど、その知名度を急激に上げていきます。
2008年には先述した残響レコードよりデビュー・ミニアルバムをリリース、その後も自主企画イベントなども積極的に開催するなど、独自の活動でシーンをかき回します。
そんな彼らのサウンドはポストロックやマスロック、カオティックなハードコアなどをブレンドさせた強烈なもので、トリプル・ギターならではの複雑怪奇なアンサンブル、それでいて踊れるグルーヴを兼ね備えた楽曲はやはりライブでこそ味わいたいといった代物。
9mm Parabellum Bulletといったバンドが好きという方でmudy on the 昨晩を知らない、という人がいれば必ずチェックしてください!