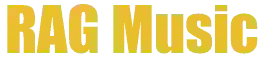【洋楽ジャズ】一度は聴いたことのあるスタンダードナンバー特集
ジャズのスタンダードナンバーと言われて、皆さんはどのような楽曲を思い浮かべますでしょうか。
実はテレビのCMやデパートの店内BGMなどで一度は耳にしている楽曲の多くが、ジャズのスタンダードナンバーであったりするのですね。
今回はジャズ・ミュージックとして長年愛され続けている「スタンダードナンバー」をテーマとして、映画用に作られてそのままジャズ界のアーティストたちに繰り返しカバーされた名曲から、ジャズ・ミュージシャン自身が作曲したナンバーまでを一挙ご紹介。
戦前の有名曲から戦後のモダン・ジャズ、70年代のフュージョン系の名曲に80年代のポピュラー音楽などにも目を向けた幅広いラインアップでお届けします!
- 【ジャズの王道】モダンジャズの名曲。一度は聴きたい人気曲
- 【ジャズ入門】初めて聴く人におすすめのジャズの名曲
- 洋楽ジャズの名曲。おススメの人気曲
- ジャズのCMソング。人気のコマーシャルソング
- ジャズの人気曲ランキング
- 【まずはここから!】ジャズロックの名曲。おススメの人気曲
- 冬に聴きたいジャズ。クリスマスソングだけじゃない名曲・名演たち【2026】
- 【2026】ジャズボーカルの名盤。一度は聴きたいおすすめのアルバム
- スウィングジャズの名曲。おすすめの人気曲
- 洋楽のジャズバラードの名曲。世界の名曲、人気曲
- 【初心者向け】モダンジャズの名盤。まずは聴きたいおすすめのアルバム
- 入門!ジャズ初心者におすすめの名曲・スタンダードナンバーまとめ
- 【2026】おすすめのジャズメドレー動画を紹介!
【洋楽ジャズ】一度は聴いたことのあるスタンダードナンバー特集(11〜20)
A Night in TunisiaDizzy Gillespie

『チュニジアの夜』という邦題でも有名な『A Night in Tunisia』は、著名なジャズ・トランペッターのディジー・ガレスピーさんとピアニストのフランク・パパレリさんが共作して生まれた曲で、作曲された時期は1942年と言われていますが1943年、または1944年という説もあるそうです。
ガレスピーさんはいわゆるモダン・ジャズの原型となった「ビバップ」の立役者であり、新世代のジャズの名曲として早い段階で多くのジャズ・アーティストがライブのレパートリーに取り上げ、50年代の時点ではすでにスタンダードナンバーとしての地位を確立していたという楽曲なのですね。
ラテン・ジャズを世に知らしめた一面も持つガレスピーさんらしいアフロ・ビートを用いたパートと、王道のジャズ的な4ビートのパートが組み合わさった楽曲展開が何ともクールでカッコいいです!
この楽曲については後に歌詞が付けられて歌曲としても愛され続けており、中でもあのチャカ・カーンさんは『And The Melody Still Lingers On (A Night in Tunisia)』というタイトルで自ら作詞してファンク・バージョンとしてリメイク、作曲者のガレスピーさんも参加してのレコ―ディングが実現しています。
1981年にリリースされたアルバム『What Cha’ Gonna Do for Me』に収録されていますから、そちらもぜひチェックしてみてください!
My Favorite ThingsJohn Coltrane

こちらの『My Favourit Things』もまた、大抵の人が一度は耳にしているであろう超有名曲です!
日本では『私のお気に入り』という邦題でも著名なこちらの楽曲は、言わずと知れたミュージカルの傑作『サウンド・オブ・ミュージック』のうちの1曲として誕生した名曲であり、映画版でも印象的な場面で登場人物のマリア先生が歌っているのをすぐに思い出される方も多くいることでしょう。
『私のお気に入り』はジャズ・ミュージシャンによってインストゥルメンタル曲としても頻繁にカバーされており、特に有名なものといえばジャズの歴史において最重要人物の1人と言える巨人、ジョン・コルトレーンさんが1961年に発表した同名のアルバムに収録されているバージョンではないでしょうか。
最も知名度の高く人気のある『私のお気に入り』のカバーであり、コルトレーンさん自身も好んでコンサートで演奏し続けていたのだとか。
歌入りでもインストゥルメンタルでも、親しみやすいメロディを聴いていると不思議と楽しい気持ちにさせられますよね。
ちなみにあのアリアナ・グランデさんが2019年に発表したヒット曲『7 Rings』のメイン・フレーズは、聴けば分かりますが『My Favourit Things』を引用したものです。
原曲と聴き比べてみるのもおもしろいですよ!
Fly Me To The MoonFrank Sinatra
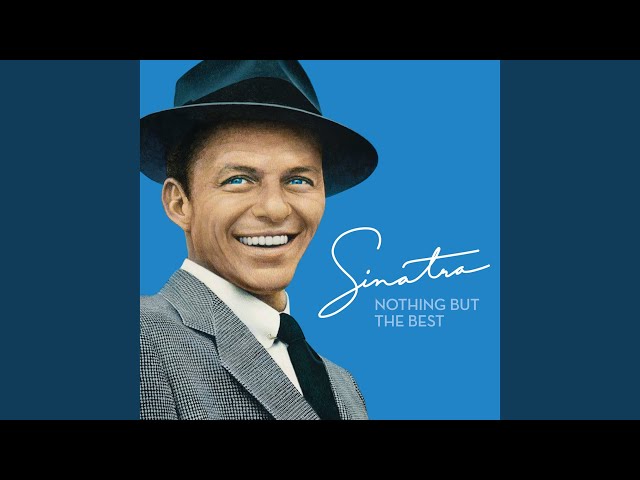
この楽曲をスタンダードナンバーとしてではなく、名作アニメーション作品『新世紀エヴァンゲリオン』のエンディングテーマとして初めて触れたという方、実は私自身もそうなのですが、一定の世代の日本人であれば結構多いかもしれませんね。
こちらの『Fly Me to the Moon』は、世界的に有名なジャズのスタンダードナンバーとして歌い継がれている名曲であり、先述した『新世紀エヴァンゲリオン』をはじめとして、ここ日本でもドラマやCM曲などで繰り返し使われている楽曲です。
そんな『Fly Me to the Moon』ですが、実は1954年にアメリカの作詞家兼作曲家、バート・ハワードさんが手掛けた『In Other Words』という曲が原曲ということをご存じでしたか?
リズムも4分の3拍子と現在のバージョンとは違ったアレンジが施されており、初めて録音した歌手はケイ・バラードさんという方で、1954年にレコードがリリースされています。
その後は紆余曲折を経て『Fly Me to the Moon』というタイトルが定着し、1962年にはジョー・ハーネルさんという作曲家・編曲家がボサノバ調にアレンジ、2年後にはあのフランク・シナトラさんが歌唱したバージョンが大ヒットを記録して現在にいたる、という経緯があるのです。
Yardbird SuiteCharlie Parker

モダン・ジャズの原型と言われている「ビバップスタイル」をトランペット奏者のディジー・ガレスピーさんと生み出し、34年間という短い生涯ではありましたが、天才的なアドリブ・プレイでジャズ・シーンを一変させたジャズ界の偉人「バード」ことチャーリー・パーカーさん。
パーカーさんは不世出のプレイヤーというだけではなく作曲家としてもいくつかの名曲を生み出しているのですが、今回は1946年にパーカーさんが作曲した『Yardbird Suite』を紹介しましょう。
『ヤードバード組曲』という邦題で親しまれているこちらの楽曲は、ビバップの代表的な名曲とされており、ジャズのスタンダードナンバーとしてさまざまなアーティストがカバーしている楽曲です。
パーカーさんの愛称でもあった「ヤードバード」と、クラシック音楽用語である「組曲」を組み合わせたタイトルがなんともユニークですよね。
いわゆる32小節のAABAと呼ばれる形式を用いた楽曲で、ジャズのアドリブを練習する際に課題曲として挑戦した方も多いのではないでしょうか。
ちなみにピアニスト兼シンガーソングライターとして知られているボブ・ドローさんが1956年に発表したアルバム『Devil May Care』には、彼自身が作詞した歌曲としての『Yardbird Suite』のカバーが収録されており、その歌詞の内容がパーカーさんに対する限りない敬意を感じさせるものなっていますから、興味のある方はぜひチェックしてみてください!
BirdlandWeather Report

メイナード・ファーガソンさんのバンドやマイルス・デイヴィスさんのグループのメンバーという共通点を持つ、シンセサイザー奏者のジョー・ザヴィヌルさんとサックス奏者のウェイン・ショーターさんを中心として1970年に結成されたウェザー・リポートは、フュージョン~クロスオーバーを代表するグループです。
高度なテクニックを持つミュージシャンたちによる、ジャンルの枠内をとびこえた自由度の高いアンサンブルと先鋭的なセンスが生み出す作品の数々が後続のアーティストやバンドに多大なる影響を及ぼしたことは、いまさら語るまでもないでしょう。
そんな彼らが作り上げた名曲もスタンダードナンバーの地位を確立した楽曲が多く、中でも1977年にリリースされて大ヒットを記録した名盤『Heavy Weather』のオープニングを飾る『Birdland』は、フュージョンの歴史においても非常に重要な楽曲として評価されている名曲中の名曲です。
不世出のベーシスト、ジャコ・パストリアスさんのフレットレス・ベースによるピッキング・ハーモニクスを駆使したプレイのインパクトは絶大ですし、メイン・フレーズのメロディも覚えやすくて素晴らしいですよね。
実際、ジャズ・コーラス・グループのマンハッタン・トランスファーがボーカル曲としてカバーしてヒットさせているのですよ。
ちなみにこちらの楽曲のタイトルは、チャーリー・パーカーさんのニックネームにちなんだ名前を持つ、1949年から1965年までニューヨーク市マンハッタンに存在したジャズクラブをオマージュしたものです。
Time After TimeMiles Davis

スタンダードナンバーと言われると、大抵が戦前や50年代60年代といった時代に生まれた曲というイメージですが、本稿で紹介する楽曲は80年代に生まれた珠玉のスタンダードナンバーです。
大の親日家としても有名なアメリカ出身の女性シンガーソングライター、シンディ・ローパーさんが1983年にリリースした特大ヒットアルバム『She’s So Unusual』に収録されている『Time After Time』は、80年代を代表する名バラードとして2020年代の今も愛される名曲ですよね。
CMなどでも何度となく起用されていますし、若い音楽ファンであっても切ないメロディを聴けばすぐにそれと分かるはず。
実はこの『Time After Time』ですが、ジャズ界においてもスタンダードナンバーとして多くのアーティストがカバーし続けているのです。
ジャズ界における帝王、マイルス・デイヴィスさんが『Time After Time』が発表されて間もない時期の1984年にインストゥルメンタル・バージョンとして録音、翌年の1985年にシングルとしてもリリースしたことが直接的なきっかけとなっています。
その後はマイルスさんのライブ・パフォーマンスにおいても、繰り返し演奏されたという経緯があるのですね。
もちろん、ジャズに限らずさまざまな分野でカバーされ続けている永遠の名バラードを、オリジナル・バージョンでもマイルスさんのカバーでもぜひ楽しんでくださいね!
【洋楽ジャズ】一度は聴いたことのあるスタンダードナンバー特集(21〜30)
How High the MoonElla Fitzgerald

感動的な恋愛物語を紡ぐジャズスタンダードが、ここにあります。
ジャズの女王と呼ばれるエラ・フィッツジェラルドさんが歌う本作は、愛する人との距離感を月の高さに例えた切ない歌詞が印象的です。
彼女の澄んだ歌声とスキャットの妙技が、曲の魅力を一層引き立てています。
1947年9月、カーネギー・ホールで初演されて以来、多くのファンを魅了し続けてきました。
ジャズファンはもちろん、恋に悩む人にもぴったりの一曲。
静かな夜にゆったりと聴きたい名曲です。