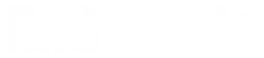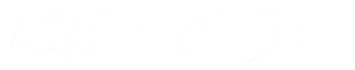宮城県で歌い継がれる美しき民謡|郷土の心を奏でる名作集
宮城県に息づく民謡の数々は、東北の文化と人々の暮らしを鮮やかに映し出す音の宝物です。
雄大な山々を舞台にした山唄から、豊かな海の恵みを歌い上げる漁師唄まで、大地と人々の営みが生み出した味わい深い歌声が今も各地に残されています。
この記事では、仙台を中心に受け継がれてきた宮城県の民謡を集めました。
四季折々の風景や祭りのにぎわい、農作業の喜びなど、先人たちの思いが込められてた優しい調べに、耳を傾けてみませんか?
宮城県で歌い継がれる美しき民謡|郷土の心を奏でる名作集(41〜50)
新さんさ時雨大西玉子

「新さんさ時雨」は、東北民謡研究家の武田忠一郎さんが戦前に作曲した唄です。
この唄の歌謡曲調なところを嫌った宮城県の民謡研究家、後藤桃水さんによって、「新さんさ時雨」は発表の場をなかなか与えてもらえませんでした。
時代とともに歌謡曲調の民謡が流れ始め、ようやく日の目を見ることができました。
おいとこ節我妻桃也

江戸末の天保の頃、関東・東北地方を中心に俗曲「おいとこそうだよ」が広く唄われていました。
明治末~大正の頃東京で再び流行しましたがその後次第に忘れ去られ、宮城県にだけ「おいとこ節」として残りました。
元は余興踊りとして唄い踊られていましたが、後に酒席の踊り唄として盛んに唄われるようになりました。
どんぐりころころ諸月りんね

「どんぐりころころ」は大正時代に作られました。
作詞をした青木存義さんは宮城県松島町の大地主の家に生まれ、いわゆる「坊ちゃん」として育ちました。
広大な屋敷の庭にナラの木があり、その横に大きな池がありました。
これが「どんぐりころころ」に出てくる「どんぐり」が実る木と、どんぐりがはまってしまう「お池」です。
そして、朝寝坊な青木さんを何とか起こしたい思いで母親が取った行動が、この池にどじょうを放すことでした。
こうして「どじょう」が坊ちゃんを遊びに誘う訳です。
今までなんとなく聴いていた歌に色がついた感じがします。
嵯峨立甚句てんてん

宮城県登米郡錦織村(現在の登米市東和町錦織)の一村落・嵯峨立は、北上川の港町で、出船、入船でとても賑わった町です。
港に吹き降ろす北西の風を「さが」と呼び、帆船はさがが立つ日に出港していったそうです。
船乗りたちによって塩釜や石巻の甚句が持ち込まれ、「嵯峨立甚句」として唄い継がれてきました。
遠島甚句高田登月

「遠島甚句」は、金華山の漁場、宮城県の沿岸部一円の漁村で唄われてきた酒盛り唄です。
牡鹿半島突端にある金華山付近には大小10の島があって、俗にこれを十島と呼ぶため、いつからか遠島の字があてられるようになりました。
おわりに
宮城県の民謡には、先人の暮らしや願い、喜びが込められています。
県内各地域の民謡は、郷土の誇りであり、心の故郷でもあります。
これからも大切に歌い継がれていく宮城の民謡が、世代をこえて多くの人々の心に響き続けることでしょう。