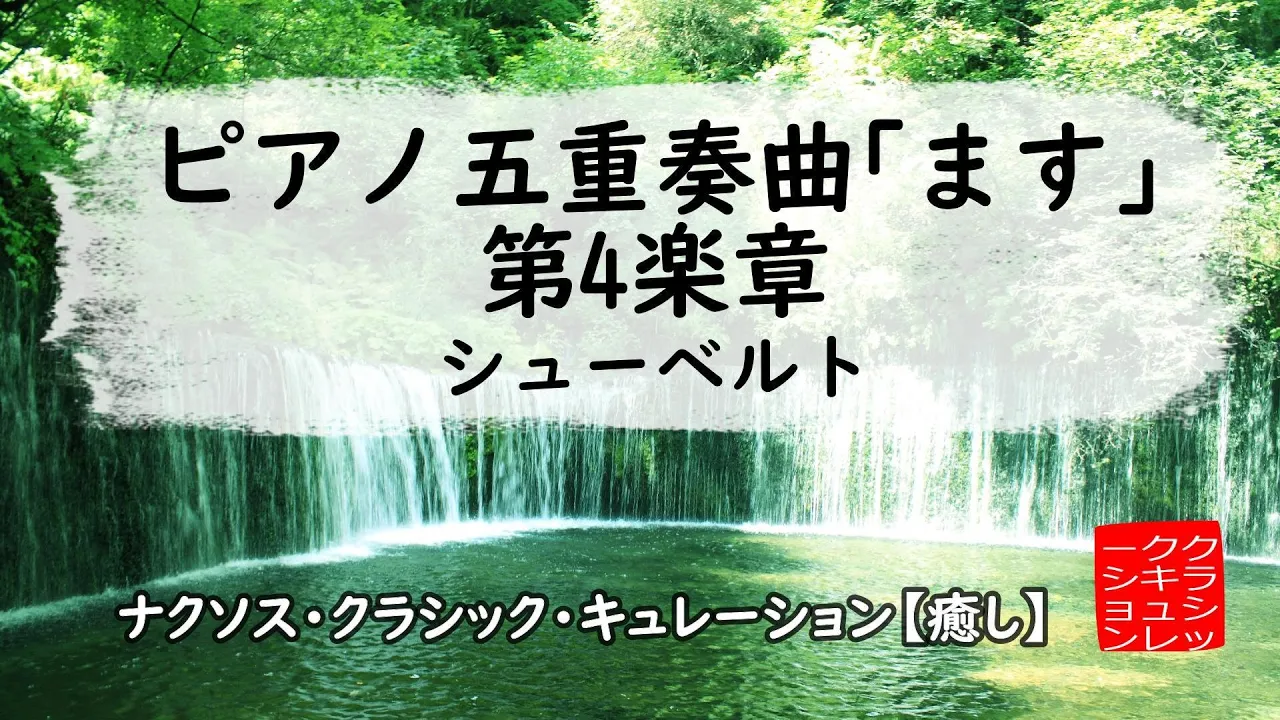朝のクラシック|気持ちよく目覚めたい方にオススメのクラシック音楽名曲選
クラシック音楽にはさまざまな効果があると言われています。
特にリラックス効果に関しては学術的にも認められているところがあり、例えば畜産業界でも動物にクラシック音楽を聴かせるなど、実践的な使われ方をしています。
もちろん、それは人間に対しても同様で、心が落ち着く作品が多く存在しています。
今回はそんなクラシック音楽のなかでも、朝にピッタリな名曲をピックアップしました。
朝からクラシック音楽を聴くと一日の勉強も仕事も捗るはず!
朝のクラシック|気持ちよく目覚めたい方にオススメのクラシック音楽名曲選(1〜10)
美しきロスマリンNEW!Fritz Kreisler

ウィーンの舞踏会を思わせる、軽やかで愛らしい旋律がとても印象的ですね。
オーストリア出身の名バイオリニスト、フリッツ・クライスラーさんが作曲した『美しきロスマリン』は、可憐な花を音楽で描いたようなバイオリンとピアノのための小品です。
ワルツのリズムに乗って跳ねるような音色は、聴く人の心を自然と明るくしてくれます。
本作は1910年に楽譜が出版され、1912年12月にはクライスラーさん自身による録音も行われました。
『愛の喜び』『愛の悲しみ』と並ぶ3部作のひとつですので、あわせて聴いてみるのもオススメです。
CMや映像作品のBGMとしてもよく使われていますから、作業の合間のリフレッシュや、穏やかな気分の勉強用BGMとしてぜひチェックしてみてください。
ディベルティメント ニ長調 K.136 – 第1楽章NEW!Wolfgang Amadeus Mozart

1772年の初めにザルツブルクで書かれたとされ、「ザルツブルク・シンフォニー」の愛称でも親しまれているヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトの作品。
その第1楽章は、イタリア旅行の影響を感じさせる明朗で疾走感のある旋律が印象的な、弦楽合奏の名曲です。
池袋駅の発車メロディとして使用されていたこともあるため、耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
心地よい弦の響きと推進力のある展開は、停滞しがちな作業や勉強の時間を軽やかなものに変えてくれますよ。
頭をすっきりさせて集中したいときに最適な、オススメのクラシックナンバーです。
愛の喜びNEW!Fritz Kreisler

華やかで気品あふれるウィーンの舞踏音楽。
そんな雰囲気が好きな方には、フリッツ・クライスラーさんが手掛けた本作がオススメ。
『愛の悲しみ』『美しきロスマリン』と合わせて3部作として語られることも多い名曲です。
1905年前後に出版され、1911年にはSPレコードが発売されたという歴史を持ち、テレビ東京系の番組「100年の音楽」でも特集されました。
セルゲイ・ラフマニノフさんによるピアノ編曲版も有名ですから、興味のある方はぜひチェックしてみてください。
作業中のBGMにすれば、優雅な気分で集中力も高まることでしょう。
ジークフリート牧歌NEW!Richard Wagner

穏やかで親密な空気に包まれたい気分のときにオススメ。
本作は「楽劇王」として知られるリヒャルト・ワーグナーによって作曲されました。
妻コジマの誕生日を祝う贈り物として1870年12月に奏でられた作品で、自邸の階段で家族のためだけに演奏されたという心温まるエピソードを持っています。
ワーグナーといえば重厚長大なオペラのイメージが強いですが、ここでは小編成のオーケストラが奏でる繊細で優しい響きが特徴です。
クリスマスシーズンの定番曲としても親しまれており、鳥のさえずりや朝の光を感じさせる牧歌的な旋律は、BGMとして作業の手を止めることなく、心地よい集中力をもたらしてくれるでしょう。
静かに勉強や仕事を進めたい方にぴったりのクラシックナンバーです。
ピアノ五重奏曲「ます」4楽章NEW!Franz Schubert

歌曲の王と称されるフランツ・シューベルトが1819年の夏に作曲した、清涼感あふれる室内楽の名作です。
川面を跳ねる魚の様子をピアノで描写した歌曲を主題とし、変奏という形式で展開されます。
コントラバスを加えた5つの楽器が織りなす会話は、明るく幸福感に満ちており、聴く人の心を軽やかにしてくれるでしょう。
本作はシューベルトの死後、1829年に出版された作品です。
その親しみやすさから、多くの映像作品でBGMとして使用されています。
爽やかな朝のスタートや、リラックスしながら作業を進めたいときにオススメです。
心地よいリズムが、勉強やデスクワークの効率を自然と高めてくれるはずですよ。
ペール・ギュント 第1組曲 ホ長調 作品46 「朝」Edvard Hagerup Grieg

朝をイメージさせるクラシックといえば、まっさきにグリーグの『ペール・ギュント 第1組曲 ホ長調 作品46「朝」』をイメージする方も多いのではないでしょうか?
本作はタイトルからも分かるように、朝を意識した作品です。
劇付随音楽として作られたため、朝のBGMとして聞き心地が良いのが特徴です。
平日の朝に聴く作品というよりは、休日のゆったりとした朝にピッタリな楽曲と言えるでしょう。
そういった朝を過ごしたい方は、ぜひチェックしてみてください。
ひばりFranz Joseph Haydn

クラシック音楽の名曲と言えばこの曲!
美しい旋律と巧みな構成が魅力です。
作曲したのは、交響曲や弦楽四重奏曲の父と呼ばれるフランツ・ヨーゼフ・ハイドン。
1790年に作曲され、第1楽章の冒頭でひばりのさえずりを思わせる旋律が印象的です。
全4楽章からなり、軽快で明るい曲調が特徴。
ゆったりとした第2楽章、快活な第3楽章、そして活気があふれる第4楽章と、変化に富んだ構成になっています。
朝に聴くとすっきりと目覚められそうですね。
クラシック音楽入門としてもおすすめの1曲です。
ハイドンの才能が光る名作から1日をスタートしませんか。