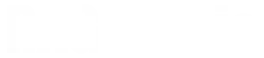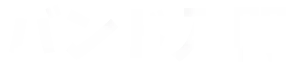未来はそんなに悪くないよ!音楽シーンの過去・現在・未来を考える 2/3
第一回に続き今回も「CD売上の減少」を、今度は社会的現象の視点から振り返ってみたいと思います。
1982年の誕生からソフト・ハード面一体となり一気に普及したCDは、成熟期と言える1990年代に黄金時代を迎えます。
イカ天:三宅裕司のいかすバンド天国
同じくテレビ関係では、バンドマンにとって「イカ天」は関係性の高い番組であり、放送当時のCD売上を考える上でも重要な番組ではないでしょうか。
1989年2月11日~1990年12月29日まで、約2年という短い放送期間ながら、勝ち抜きバンドコンテストであるこの番組から、Blanky Jet CityやFLYING KIDS、BEGIN、JITTERIN’ JINNらを輩出しました。
実は私は直接番組を見たことはありませんでしたが、バンドをやっている仲間連中では知らない者はいない程の名物番組でした。
数々のビッグネームを輩出したことはもちろん、こういった形式の音楽番組が作れるくらいに、当時はバンドブームでありバンド人口は多かったのでしょう。
歴史的には「第二次バンドブーム」と言われるようで、BOφWYやレベッカ、ハウンドドッグ等の台頭により喚起され、この「イカ天」がブームに火をつけたとされています。
当時のバンド人口がどれ程だったのか、客観的に明示できる資料がないので分からないのですが、
・恐らくバンドをやっていたであろうボリュームゾーン:18歳~24歳を中心とした年齢層でバンド人口率がどの程度か高まった。
・バンドマンはそうでない人よりCDを多く買うウォンツもニーズもある。
・当時バンドマンに必要な知識・技術等が得られるのは雑誌や教則本、VHSビデオ、そして何よりCDだった。
・18歳~24歳頃は可処分所得が多く好奇心・学習意欲も高い、また他にお金を費やす対象も今より少なかった。
等の理由から、第二次バンドブーム期前後のCD売上を、(僅かなのかも知れませんが)バンドマンが底上げしていた可能性を指摘します。
人口動態
単純に、年齢・年代別人口数というものも、CD売上には大きく関わってくるでしょう。
私自身を振り返っても、CDを一番多く購入していた時期は20歳前後であり、購入した枚数を年齢毎にカウントすればおそらくそこをピークに山なりのグラフになると思うのです。
そして、それは多くの人に当てはまる傾向ではないかと思います。
その理由としては、20歳前後が
・音楽に対する興味が高い≒まだ知らない音楽や聴きたい音楽が沢山ある。
・可処分所得が多い。
バイトや仕事である程度収入があり、使い道も比較的自由。
・値段が高過ぎる訳ではない。
・趣味の一つや日常生活の一部として少なからず音楽は聴く。
からです。
これは京都市の人口構成なので若干全国的な傾向と違いますが(京都は大学が多いので18-22歳あたりが増えますが、全国的には年齢毎に減少しているでしょう)、例えば1991年に18-24歳頃であった現41歳~47歳は、現在の18~24歳に比べ30%程人口は多くなっています。
もちろん他の年代の方もCDを買いますし、「年代別人口減少=CD売上減少」と一概に合致はしないでしょうが、ボリュームゾーンは当時より縮小しておりその傾向は今後も続くのは確実かと思います。
インターネットと携帯・スマホの普及
1990年代との比較で言うと、大きく変わった点がインターネットと携帯電話(近年ではスマホ)による情報革命です。
仕事においても日常生活においても、ネット&携帯はもはや必須の存在となりました。
インターネットの普及により、
・ファイル共有による音楽データの違法ダウンロード
・YouTube等動画サイト閲覧による視聴の代替、もしくは音源データ化
等が、CD売上の減少に関わる悪影響としてたびたび指摘されます。
「全く同一もしくは劣化コピーの流布と原本流布との相関関係」については、MDの登場やレンタルCDという業務形態においてと同様、「デジタルデータ」であるCDが根本的に生まれ持つ問題です。
業界からは、その関係については売上を妨げる悪としてやり玉に上がることが殆どだと思いますが、一方で単純に悪ではなくむしろCD売上を補完する・音楽ファンの裾野を広げるといった指摘・研究もあります。
参考1:音楽 CD 売上減少の要因についての考察 | 愛知工業大学
http://aitech.ac.jp/lib/kiyou/41B/B22.pdf
参考2:CDレンタルがCD売り上げに与える影響(docファイル)
http://www.geocities.jp/gindama_mos/mitasai.doc
CD(及びダウンロードも)が常に抱えてきたこの問題は、「複製権を買う」から「アクセス権を買う」ストリーミング・サブスクリプションによって解決するのかも知れませんね。
そして、携帯電話の普及は、「着うた」ダウンロード販売にはかなり寄与したようですが、ここ最近のスマホシフトによりその販売量は減っているようです。
「(携帯の)通信費が高くて、CDに回すお金がないのでは?」という話も聞きますし、実際よく通話される方は万単位で支払っているとも聞きます。
通信費の他にも、ソーシャルゲームやLINEのスタンプ等、1990年代には存在せず今の若い方を魅了する有料コンテンツは沢山あり、音楽CDはその競合相手に苦戦しているところはあるのでしょう。