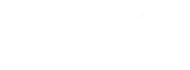障害物競走にオススメの障害物アイデアまとめ
運動会の定番競技の一つである障害物競走。
スタートからゴールまでの間にさまざまな障害物が用意されており、それらを乗り越えながら1位を目指すレースですね。
どんな障害物を用意するかは、障害物競走をおこなう上で競技の難易度や盛り上がり度を大きく左右します。
そこでこの記事では、障害物競走に取り入れたい障害物のアイデアを一挙に紹介します。
足の速さだけでなく、器用さや運が必要な障害物もたくさん取り上げました。
みんなで楽しめる障害物競走になるよう、ぜひ参考にしてくださいね!
- 【障害物リレー】運動会に取り入れたいおすすめアイデア&おもしろネタ
- 幼稚園の運動会に!障害物競走のアイデア一覧
- 【盛り上がる!】運動会の定番競技。人気の種目・ゲームのアイデア
- 【ユニーク】子供も大人も楽しめる運動会のおもしろい種目
- 【中学生向け】体育祭にオススメの面白い競技を一挙紹介!
- 【ミニ運動会】室内開催にピッタリの盛り上がる種目を厳選!
- 運動会・体育祭で盛り上がる曲ランキング【2026】
- 運動会やレクにオススメ!踊りやすいディズニーの名曲&人気ダンス曲
- 定番からおもしろいものまで借り物競争を盛り上げるお題
- 【運動会の応援歌】定番応援ソング・替え歌にオススメの曲まとめ
- 【運動会】かけっこに合う曲。子供たちが走りたくなる曲【定番&J-POP】
- 【年長競技】5歳児の運動会が盛り上がる競技のアイデア集
- 運動会にぴったり!2歳児にオススメの障害物競争アイディア
障害物競走にオススメの障害物アイデアまとめ(11〜20)
ハードル

障害物をこえる競技として最もポピュラーなのがこちらのハードル走ではないでしょうか。
ハードル走の歴史は古く、昔馬に乗れなかった人たちが障害物を跳び越して楽しんでいたのが始まりだそうです。
陸上競技としては1864年にイギリスのオックスフォード大学でおこなわれたものが最初の記録として残っています。
1896年の第一回アテネオリンピックでも競技としておこなわれました。
なるべくロスが少ないように低い位置で飛ぶことがポイントです。
三輪車

中学生や高校生、大人の方などが参加する障害物競走にオススメなのが三輪車です。
障害物競走のコース内で一定の区間を三輪車で走るというものですが、三輪車に乗るのって体が大きくなった大人にとってはとっても難しいんですよね!
大人が一生懸命に三輪車に乗っている姿もおもしろくて盛り上がりますし、難しい中で上手に乗る人がいても盛り上がるので、楽しい雰囲気の障害物競走にしたいときにはピッタリの障害物アイデアですよ。
鉄棒

参加者全員にスポットライトが当たる鉄棒。
前回りや逆上がりなど、鉄棒を使った定番の技を披露しましょう。
それぞれの運動能力や体格に合わせて、鉄棒の高さを変えてやってみてくださいね。
鉄棒を準備するだけなので、すぐに取り組めるのもいいですね。
声援を送ったり拍手することで、会場の一体感も高まる競技です。
その場にいる誰もが応援したくなる競技に、ぜひ取り組んでみてくださいね。
筋トレ
急きょ障害物を増やしたいなという時には、筋トレもオススメです。
例えば、途中で腹筋や腕立て伏せを決めた回数だけやるなどですね。
これならアイテムを準備しなくてもOKです。
またチームごとのハンデにも使えます。
筋トレの量が多ければ時間がかかるのはもちろん、体力も奪われるはずです。
ほどよい内容と回数で設定してみてください。
カードを複数枚用意しておいて、引いたカードに書かれている内容に合わせて取り組むというのも楽しそうです。
でんぐり返し

コースの途中にマットを敷いておき、その区間はでんぐり返しで進んでいくという障害物です。
とくに幼稚園児や小学校低学年の子供たちが参加する障害物競走にピッタリだと思います。
競技に参加している選手同士がぶつかってしまわないように各レーンに1つずつマットを用意しておくと安全面でも安心ですね。
またでんぐり返しができない人はゴロゴロ転がっていくだけでもOKという補助ルールを設けておくとみんなで楽しめると思います。
ドリブルダッシュ

ドリブルダッシュは小学生以上の方が参加する障害物競走にオススメです。
コース内の一定の区間をバスケットボールのドリブルをしながら進むというもの。
バスケ経験者の方であれば難なくできますが、あまりバスケをしたことがない方にとってはかなり難しいかもしれません。
学校の運動会でおこなう場合はバスケ部は参加不可にしたり、バスケ部の方はサッカーのリフティングをするなど、特別ルールを用意しておくといいかもしれません。
障害物競走にオススメの障害物アイデアまとめ(21〜30)
はしごくぐり

障害物リレーの定番競技のはしごくぐりは、シンプルで奥が深い競技になっています。
体形などによって、やりやすいやりにくいの差がかなりある競争ですが、簡単に潜り抜けるポイントとしてははしごの奥の方に手をつき、ぶつかることを気にせずにするっと通り抜けるイメージで体を動かすといいそうです。
以前は一般的な木のはしごなどを使っていたようですが現在でははしごくぐり競技用のはしごというものも売っていたり、レンタルできたりするそうですよ。
ぜひ楽しんでみてくださいね。