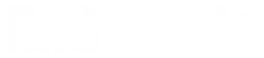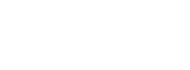障害物競走にオススメの障害物アイデアまとめ
運動会の定番競技の一つである障害物競走。
スタートからゴールまでの間にさまざまな障害物が用意されており、それらを乗り越えながら1位を目指すレースですね。
どんな障害物を用意するかは、障害物競走をおこなう上で競技の難易度や盛り上がり度を大きく左右します。
そこでこの記事では、障害物競走に取り入れたい障害物のアイデアを一挙に紹介します。
足の速さだけでなく、器用さや運が必要な障害物もたくさん取り上げました。
みんなで楽しめる障害物競走になるよう、ぜひ参考にしてくださいね!
障害物競走にオススメの障害物アイデアまとめ(31〜40)
缶積み

缶積みとはその名の通り空き缶を高く積み上げていく遊びです。
障害物競走に取り入れるときには「〇個積み上げたらクリア」といったようにあらかじめルールを決めておきましょう。
ルールで定めた個数を積み上げられたらクリアで先へ進めますが、積んでいる途中で崩れてしまったらもちろん初めからやり直しです。
参加者の年齢や競技時間に合わせて何個積み上げるのかを決めていくといいと思います。
小さい子供から大人まで、ルールをアレンジすることで楽しめる障害物アイデアです。
縄跳び

とってもシンプルですが縄跳びを取り入れるのもオススメです。
その理由は、参加者の年齢や体力に合わせてルールを自由に設定できるからなんです。
もっとも簡単なルールであれば、「コースの一定区間を縄跳びを飛びながら走る」「〇回跳んだらクリア」といったもので、難易度を上げたければ「二重跳びを〇回できたらクリア」など技の難易度を上げるといいでしょう。
さらなるアレンジとして、三重飛びやはやぶさなど、さらに高難易度の技ができた人には追加ポイントなどのルールがあってもおもしろいかもしれませんね。
ボールを落とさずゴールを目指せ!

ボールを決められた地点までに落とさずに運んでいくという内容、ボールを運ぶ手段によって難易度が変わるところもポイントですね。
道具の上にボールをのせて運ぶなどのひとりでおこなうパターン、背中でボールをはさんで運んでいくといった二人でおこなうパターンなど、さまざまな方法で楽しめます。
ボールを落としたときの判定、どの場所から再スタートするのかも、公平に競技を進めていくための重要なポイントなので、審判を配置して状況をしっかりとチェックしてもらいましょう。
バランス感覚や、パートナーとの絆など、どの部分を発揮してもらうのかで、内容を考えるのがよさそうですね。
けんけんぱ

幼稚園の運動会でおこなう障害物競走であれば、けんけんぱを取り入れるのもいいでしょう。
小さいフラフープを置いたり、ロープを輪っか状にして置いておき、1つの輪っかは「けん」、2つの輪っかは「ぱ」で通過していきましょう!
小さい子供たちなら普段からけんけんぱで遊んでいると思うのできっと楽しく取り組めると思います。
あえて大人の方が参加する障害物競走に取り入れてみても、意外と転んでしまったりして盛り上がるかもしれません。
みのむしダッシュ

みのむし競走ってご存じでしょうか?
運動会でも定番競技の一つとして親しまれていて、腰くらいまである麻袋の中に入った状態でピョンピョンと飛び跳ねてゴールを目指すものです。
これを障害物競走のコースの一区画に取り入れてみましょう。
コツをつかんで要領よく飛び跳ねるのが速く進むポイントなので、単純に足の速さだけで勝敗が決まらないのがおもしろいところです。
急ぎすぎるとコケてしまったりもするので、意外と白熱した勝負が期待できます。